
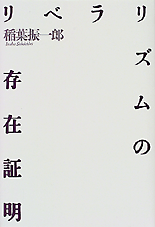
稲葉振一郎
2000年11月15日 ver.0
2000年11月21日 ver.01
2000年11月29日 ver.02
2000年12月6日 ver.03
2000年12月8日 ver.04
2000年12月11日 ver.05
2001年1月25日 ver.101
2001年2月14日 ver.102
2001年4月8日 ver.1021
2001年5月16日 ver.1022
2001年8月3日 ver.201
2001年8月8日 ver.2011
2002年9月27日 ver.301
*明治学院大学社会学部講義「社会倫理学」と演習を念頭に置いて作成。
「野望としての教養」(浅羽通明)「新教養主義」(山形浩生)に多少とも資することをも念じて。
とりあえずは「教養」であるが、最後の倫理学の項目だけはやや専門的であるかもしれない。
古典はさしあたり除外する。
*全点へのコメントはもう少し待ってほしい。
*原則的に入手が容易なものを選んだ。リンクは オンライン書店bk1 に通じている。
*入門の入門
橋本治『青空人生相談所』ちくま文庫
「自分でものを考えるとはどういうことか」の入門書として好適。
本書をゼミ選考のテキストとして用いた際、著者の主張への批判の論法として学生諸君が用いた切り口は、ほぼ例外なく、社会学、心理学、ケースワーク等の専門的知見の観点から、著者の議論の素人臭さを突く、というものであった。まだ自分は専門家でも何でもないにもかかわらず、というか、それゆえに、というか。
しかし著者橋本氏の身の上相談は、専門家のひとりとして素人さんの代わりに困難な問題について考えてあげよう、というものでは全くない。言っておくが、専門家に相談したところで、専門家がやってくれるのはせいぜいが情報提供であって、最終的に何をするのかを決めるのは、素人自身なのだ。橋本氏はその事実を常に相談者の前に突きつける。
専門家になる前に、筋金入りの素人にならねばならない。
浅羽通明『大学で何を学ぶか』『教養論ノート』幻冬舎
前者は、現代日本の大学とはどのようなところなのか、を縦横に論じた名著である。特に、若者が大学に入ったらとたんに勉強しなくなるのは充分に理由が……ことによったら正当な理由があるということ、それどころか逆に大学では、真面目に勉強することこそが、一種の現実逃避以外の何ものでもなくなる場合もあるということを初めて喝破した。
そして後者は、それでもなお学問を学びたいという者は何を目指すべきか、についての指針として読むことができる。
村上龍『希望の国のエクソダス』文藝春秋
著者がここに描き出した将来の日本の行き詰まりのシミュレーション、そしてそこから自分たちの才覚で脱出していく子どもたちの姿は、ある意味荒唐無稽だが、ある意味限りなくリアルだ。ここに具体的に描かれた、子どもたちの戦略構想こそが「希望」であるというわけではない。著者もそんなことが言いたいのではあるまい。具体的にはその時その時で様々だが、とにかく「希望」というものは何らかの形で存在するのだ――それこそが、彼の言いたかったことだろう。
野矢茂樹『論理トレーニング』産業図書
大学の論理学の授業の副産物だそうだ。「論理学」というのは独立した専門的学問で、それなりに固有のテーマがある。つまり普通の人が日常的な生活の場面で、より合理的に考え、議論するためのノウハウを教えてくれるわけではない。(まあ全然無関係というわけではないけど。)で、本書はそういう普通の意味での論理的な思考と討論のためのドリルブックである。続編に『論理トレーニング101題』(産業図書)がある。
山内志朗『ぎりぎり合格への論文マニュアル』(平凡社新書)
これさえあれば他の「論文・レポートの書き方」本はもういらない。というとほめすぎか。
*哲学入門
野矢茂樹『哲学の謎』講談社現代新書
新書の哲学入門としてはベストであろう。偉い哲学者の名前とか哲学固有の用語とかはほぼ一切使わずに、哲学的に考えるとはどういうことか、哲学でいう「問題」とはどのようなものか、を平易な会話体で具体的に展開する。
永井均『〈子ども〉のための哲学』講談社現代新書『翔太と猫のインサイトの夏休み』ナカニシヤ出版
現在日本で一般読書人の間で人気ナンバーワンの哲学者である著者の哲学入門書。世間の雑音に惑わされず、あくまでも自分にとって(だけ?)大切な疑問を大事に大事に考えていったら、なぜかそれが世間で「哲学」と呼ばれるものとぶつかり、更にどういう訳か少なからぬ一般読者の共感を引き起こすことになった、それがこの著者である。極端に私的な(はずの)問題が、なぜか他人の理解と、あろう事か共感を呼び起こすということの不思議。あるいはそれはただの誤解なのだろうか? しかしそもそも「誤解」と「正解」を分かつものは何か?
門脇俊介『哲学教科書シリーズ 現代哲学』産業図書
戸田山和久『哲学教科書シリーズ 知識の哲学』産業図書
いずれも普通の意味での教科書としてよく考えられてうまく書かれている。これを読めば学問としての現代哲学が何をやっているのか、がよくわかる。
ダニエル・デネット『心はどこにあるのか』草思社
信原幸弘『考える脳・考えない脳』講談社現代新書
デイヴィッド・J・チャーマーズ『意識する心 脳と精神の根本理論を求めて』(林一訳、白楊社)
柴田正良『ロボットの心 7つの哲学物語』(講談社現代新書)
20世紀半ばまでの哲学のもっとも中心的なテーマは「言語」だった。人間がものを考えるためには、言語がなければいけない。言語がなくてもものを考えられないわけではないかもしれないけど、そういう言語なしの思考を他人が外側から観察することはできない。だから人間の思考が何であり、どのようにはたらくかを考えるためには、まず言語とは何かを考えなければならない――大ざっぱに言うとこんな感じだ。
現代哲学の中心テーマはそれに対して「心」である。言語哲学全盛の時代には、外側から観察不能なブラックボックスとして敬遠されがちだった「心」だが、コンピュータ技術とコンピュータ科学の発展、脳神経科学の発展、更にそれらを承けての心理学の変貌によって事情は変わってきた。神経科学の発展は話され書かれた言葉以外のルートから人間の心を観察し、更にそれを他の動物と比較する可能性を開き、コンピュータの発達は、コンピュータの行う「計算」と人間の思考はどこがどう違ってどこがどう似ているのか、という問題を提出した。
我々は自分で考え自分で判断するロボットを作れるのだろうか。いやそもそも、そのロボットが何ができたときに、我々はそれが「自分で考え自分で判断している」と判定できるのだろうか、いったいその規準は何か? 現代哲学の中心問題の一つは、たとえばこういうものだ。そういう事情について学ぶには、たとえばこれらの本からはいるといい。
大庭健『はじめての分析哲学』産業図書
イアン・ハッキング『言語はなぜ哲学の問題となるのか』勁草書房
では、一昔前の言語中心の哲学はどのようなものだったのか? それは本当に過去のものと化したのか? 仮にそうだとしても、一体どのような歴史的意義があったのか? はなお知っておいて損はないテーマである。言語というテーマはなお重要な脇役であるにかわりはないのだから。
*論理学・数学・計算機科学
野矢茂樹『論理学』東京大学出版会
戸田山和久『論理学をつくる』名古屋大学出版会
共に大学の(哲学的)論理学の教科書であり、現時点ではベストである。
前者は「筋金入りの素人」という名文句を生んだ。論理学の専門家になるための本ではなく、素人が「論理学ってどんな科学なんだろう?」と見物するための本だ。広範囲に渡る話題がコンパクトにまとめられている。
後者はより本格的な本で、読者に対して、自分で実際に論理学という建物を造ってみるよう促す。
ダニエル・ヒリス『思考する機械コンピュータ』草思社
コンピュータ科学とは、数学からも、論理学からも、物理学からも独立した――しかしもちろんそれらすべてと密接に関係した独自の科学である。その対象であるコンピュータとは、私たちが普通お付き合いする「電子計算機」のことではない。「電子計算機」は「コンピュータ」の一例でしかない。では、「コンピュータ」って一体なんだ?
*生物学・心理学
リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子』紀伊国屋書店
進化生物学の一般向け啓蒙書、なのだが、それにとどまらない衝撃を広く科学界、思想界に引き起こした問題の書。彼によれば、ダーウィン的進化のメカニズムは遺伝子を持つ生物の世界にのみ当てはまるわけではない。遺伝子と同じような振る舞いをするものがあれば、そこにおいてただちにダーウィン的進化のメカニズムは作動をはじめる。たとえば脳のなかのシナプス結合において。またコンピュータ・シミュレーションのなかで。あるいは言葉を備えた人間の文化の世界において! つまりダーウィン進化論とは単なる生物学の理論ではなく、より包括的な、独立したひとつの世界観、形而上学なのだ。
真木悠介『自我の起源』岩波書店
日本の代表的社会学者がものした、素人の素人による素人のための進化生物学の入門書。内容はおおむね正確で、「文系」読者には非常に取っつきやすい。
ジャレド・ダイアモンド『人間はどこまでチンパンジーか?』新曜社
どうも社会学というのは、というか社会科学全般は、人間というのは特別な生き物だと(また近代というのは特別な時代だと)思いたがるきらいがある。だが人間は生物学的に見ればチンパンジーのごく近い仲間というかその一種であるという事実もまた動かしようがない。更に言えば、環境破壊も大量殺戮も必ずしも人間の(そして当然に近代社会の!)専売特許というわけではないのだ! 進化生物学の観点から人類史を通観した好著。
アントニオ・ダマシオ『生存する脳』講談社
長谷川寿一/長谷川真理子『進化と人間行動』東京大学出版会
ドナルド・E・ブラウン『ヒューマン・ユニヴァーサルズ』(新曜社)
スーザン・ブラックモア『ミーム・マシーンとしての私』草思社
下條信輔『サブリミナル・マインド』中公新書『〈意識〉とは何だろうか』講談社現代新書
ダニエル・デネット『ダーウィンの危険な思想』青土社
ジュディス・ハーマン『心的外傷と回復』みすず書房
*法律・法学
副島隆彦/山口宏『新版 法律学の正体』洋泉社
長尾龍一『憲法問題入門』ちくま新書
平井宣雄『法政策学』有斐閣
内田貴『契約の時代』岩波書店
前田雅英『刑法入門講義』成文堂
ローレンス・レッシグ『CODE インターネットの合法・違法・プライバシー』翔泳社
*犯罪・非行
頼藤和寛『賢い利己主義のすすめ』人文書院
マイケル・ゴットフレットソン/トラヴィス・ハーシ『犯罪の基礎理論』文憲堂
加藤尚武『子育ての倫理学』丸善ライブラリー
*経済・経済学
海外投資を楽しむ会編『ゴミ投資家のための人生設計入門』メディアワークス
インターネットトレーディングへの無責任な煽りとか色々問題はあるが、それでも掛け値なしの名著である。不動産、生命保険、社会保障、子供の教育、と要するに普通の個人(著者たちのいう「ゴミ投資家」)にとっての「資産」「財産」を、長期的な損得勘定を立ててきちんと運用し、「経済的独立」(身も蓋もなくいえば「安定した老後」なんだが)を達成するための基本スキルを指南する。本来こういうことを中学高校の「公民」ではまず教えるべきだし、大学教養課程の経済入門でやるべきなんだけど、自分で稼いで自分の家計を切り盛りするようにならないと、こういうことのありがたみって分からないんだろうな。
ポール・クルーグマン『クルーグマン教授の経済入門』メディアワークス『経済政策を売り歩く人々』日本経済新聞社
世に「経済学入門」は数々あれど、「経済入門」は、それも経済学をきっちり生かしつつ書かれた「経済学入門」ではなく「経済入門」はあまり例を見ない。前者はその意味で出色である。いずれはノーベル経済学賞確実といわれる著者は、専門論文だけでなしに一般読者向けの軽妙な、しかし科学的にしっかりとツボを押さえた経済エッセイのすぐれた書き手として知られている。後者の方は良質の「経済学入門」として使える。
深尾光洋『コーポレート・ガバナンス入門』ちくま新書
松井彰彦・梶井厚志『ミクロ経済学 戦略的アプローチ』日本評論社
武藤滋夫『ゲーム理論入門』日経文庫
松尾匡『標準マクロ経済学 ミクロ的基礎・伸縮価格・市場均衡論で学ぶ』中央経済社
吉川洋『転換期の日本経済』岩波書店
石見徹『世界経済史』東洋経済新報社
ジョセフ・スティグリッツ『世界を不幸にしたグローバリズムの正体』(徳間書店)
岡崎哲二/奥野正寛編『現代日本経済システムの源流』日本経済新聞社
ジェイン・ジェイコブズ『経済の本質 自然から学ぶ』日本経済新聞社
小島寛之『サイバー経済学』(集英社新書)
野口旭・田中秀臣『構造改革論の誤解』(東洋経済新報社)
玄田有史『仕事のなかの曖昧な不安 揺れる若年の現在』(中央公論新社)
*政治・政治学
ブルクハルト・ヴェーナー『レオニーの選択』光文社
物語仕立てで「民主主義政治」とは、その意義と限界とは何か、欠点だらけであるにもかかわらずそれでもなお「民主主義政治」を捨てるわけにはいかないとしたら、それはなぜか、をきっちり論じた政治版『ソフィーの世界』。いやたぶん『ソフィーの世界』よりいい本だ。
何より重要なことは、今先進諸国で多くの人々が政治的無関心に陥っているのは理由のないことではない、それはまた道徳的に責められることではない、と言いきっているところだ。つまり、問題があるのは現代民主政治の制度的枠組み(もちろんそこには公民教育も含まれるが)の方なのであり、政治的無関心を嘆き、責めるよりも前にやることがある、と。すぐれた、普通の人々のための政治入門であると言えよう。
的場敏博『政治機構論講義』有斐閣ブックス
山口定『政治体制』東京大学出版会
大嶽秀夫『「行革」の発想』TBSブリタニカ
加藤朗『現代戦争論 ポストモダンの紛争LIC』中公新書
金子勝『市場と制度の政治経済学』東京大学出版会
坂野潤治『日本政治「失敗」の研究』(光芒社)
ロバート・パットナム『哲学する民主主義 伝統と改革の市民的構造』NTT出版
橋爪大三郎『政治の教室』(PHP新書)
杉田敦『デモクラシーの論じ方』(ちくま新書)
*現代社会・社会学
ヤン・エルスター『社会科学の道具箱』ハーベスト社
佐藤俊樹『近代・組織・資本主義』ミネルヴァ書房
盛山和夫『制度論の構図』創文社
畠山弘文『動員史観へのご招待 絶対王政から援助交際まで』(五絃舎)
石原英樹・金井雅之『進化的意思決定』(朝倉書店)
竹内洋『日本のメリトクラシー 構造と心性』東京大学出版会
苅谷剛彦『階層化日本と教育危機――不平等再生産から意欲格差社会〔インセンティブ・ディバイド〕へ』(有信堂)
ゲスタ・エスピン=アンデルセン『福祉資本主義の三つの世界 比較福祉国家の理論と動態』ミネルヴァ書房『ポスト工業経済の社会的基礎 市場・福祉国家・家族の政治経済学』桜井書店
ラルフ・ダーレンドルフ『現代の社会紛争』世界思想社
平田オリザ『芸術立国論』(集英社新書)
三浦展『マイホームレス・チャイルド 今どきの若者を理解するための23の視点』(クラブハウス)
*社会調査
高根正昭『創造の方法学』講談社現代新書
谷岡一郎『「社会調査」のウソ』文春新書
前者は、調査を中心とした社会(科)学方法論の入門書。社会(科)学において、仮説を構成し、それを検証する、とはどういうことなのか、具体的に例を挙げて説明していく。パソコンが普及して誰にでも簡単に統計分析の真似事ができるようになった今日でこそ読み返されるべき名著である。後者は関連するテーマを扱った最近の本としてお勧めである。
小池和男『聞きとりの作法』東洋経済新報社
佐藤郁哉『フィールドワーク』新曜社
岩井 紀子・佐藤博樹編『日本人の姿 JGSSにみる意識と行動』(有斐閣)
*考古学・歴史学
ジャレド・ダイアモンド『銃・病原菌・鉄』草思社
E・L・ジョーンズ『ヨーロッパの奇跡』名古屋大学出版会
フェルナン・ブローデル『歴史入門』太田出版
柴田三千雄『近代世界と民衆運動』岩波書店
石原保徳『世界史への道』(前後編、丸善ライブラリー)
エリック・ホブズボーム『20世紀の歴史』三省堂
カルロ・マリア・チポッラ『経済史への招待』国文社
塩川伸明『現存した社会主義』勁草書房
君たちにはピンとこないかもしれないが、20世紀という時代は社会主義の時代だった。それは社会主義国にとってだけのことではなく、「西側」、自由主義、資本主義の世界にとってもそうだったのだ。だから、社会主義とは何だったのか? を問うことは実は未だに非常にアクチュアルな作業なのだ。
あと知恵的に振り返れば、社会主義はうまくいかなくて当然のシステムだったように見える。しかしそれではなぜ、いまにして思えば当然のことが、みんなには分からなかったのだろうか?
中村隆英『昭和史』東洋経済新報社
松山巌『群衆』読売新聞社
*環境問題
河宮信郎『必然の選択』海鳴社
岡敏弘『環境政策論』岩波書店
*思想史
シェルドン・ウォーリン『西欧政治思想史』福村出版
アンドリュウ・ギャンブル『現代政治思想の原点』三嶺書房
ピエール・ロザンヴァロン『ユートピア的資本主義』国文社
松沢弘陽『近代日本政治思想』(放送大学テキスト)
*倫理学・社会哲学
加藤尚武『現代倫理学入門』講談社学術文庫
田中成明『法理学講義』有斐閣
ジョン・マッキー『倫理学』皙書房
ジェイン・ジェイコブズ『市場の倫理 統治の倫理』日本経済新聞社
身も蓋もなく言うと、商売人の道徳と役人の道徳とは互いに性質が違っていて、どちらが上等とかいうものでもなくて、どちらもそれぞれの局面において有用であり必要なものだけど、取り違えたり折衷したりすると腐敗堕落や破局のもとになる、というお話。読みやすい言葉で今日の政治倫理、経済倫理の根幹にかかわるテーマを論じてくれた名著であり、就職してからもう一度こそ読んでほしい。とりわけ、会社でも役所でも、少しばかり責任ある地位についたときに、再読してみてほしいのだ。
アマルティア・セン『自由と経済開発』日本経済新聞社
開発と貧困、福祉と公正についての経済学・哲学的研究で1998年度ノーベル経済学賞を受賞した著者の、世界銀行における講義録。スケールの大きい碩学の全貌を1冊で望むことができる。より立ち入った著作として他に『貧困と飢饉』『不平等の再検討』(岩波書店)『合理的な愚か者』『集合的選択と社会的厚生』(勁草書房)などが読める。
リチャード・ディジョージ『ビジネス・エシックス』明石書店
井上達夫『共生の作法』『他者への自由』創文社
立岩真也『私的所有論』勁草書房『弱くある自由へ』青土社
ここ20年の日本の倫理学書のなかで、国際的に通用する、と言うより世界に広く紹介されるべきものを1冊だけ選ぶとすれば前者だ。(著者は「社会学者」だが。)生命倫理、障害者問題を焦点に、普通「自己決定」という言葉で語られてきた問題について、原理的に深く論じている。後者は関連するテーマを扱った論文集。
R・M・ヘア『道徳的に考えること』勁草書房
ジョン・ロールズ『公正としての正義』木鐸社
ロバート・ノージック『アナーキー・国家・ユートピア』木鐸社
平尾透『倫理学の統一理論』ミネルヴァ書房
永井均『〈魂〉に対する態度』勁草書房
小泉義之『弔いの哲学』河出書房新社
大庭健『他者とは誰のことか』『権力とはどんな力か』勁草書房
デヴィッド・ゴティエ『合意による道徳』木鐸社
ピーター・シンガー『実践の倫理』昭和堂
「実践の倫理」という邦訳題名はいただけない。本当はむしろ「実用倫理学」とでもつけられるべきだった。(原題は"Practical
Ethics"。)いわゆる応用倫理、現代の社会問題を前にしての、政策指針を提供する作業としての倫理学がどういうものか知りたければ、この本を読めばいい。著者の結論に賛成するかどうかは、ひとまずどうでもよい。
マイケル・ウォルツァー『正義の領分』而立書房
ハンス・ヨナス『責任という原理』東信堂
デレク・パーフィット『理由と人格』勁草書房
バカげて分厚い。長い。別に全部読む必要はない。しかし現代哲学というか倫理学の中には、いかにカッ飛んだ常識外れのことを考えている奴がいるか、という例として暇な人は拾い読みだけでもしてみてほしい。「人格の同一性は絶対ではなく、程度問題だ」という本書の主張は大きな議論を引き起こし、未だにそれは続いている。
森村進『権利と人格』創文社『財産権の理論』弘文堂
バナード・ウィリアムズ『生き方について哲学は何が言えるか』産業図書
アラスデア・マッキンタイアー『美徳なき時代』みすず書房
ミシェル・フーコー『監獄の誕生』新潮社
ミリャード・シューメーカー『愛と正義の構造』晃洋書房
市野川容孝編『生命倫理とは何か』(平凡社)