小テスト(11月18日) 時間制限50分
(全体評価の10%に該当。ただし、5%のボーナスがさらに付加されうる)
経済情報特別講義2 服部圭郎
氏名; _______________________________
学籍番号:_____________________________
問1.
人間が住む、働く、憩うという人間の生活目的を達成しようとして、集まって共存している場所が都市である。この「住み」「働き(学び)」「憩う」ための各空間が都市社会で同じ場所にあるといろいろな問題が生じる。そのような問題の例を挙げ、どのような点が問題になるかを説明せよ。(3点)
|
|
問2.
下表は、東京、大阪、ロンドン、ニューヨーク、パリの公共交通の年間利用者数を示している。(a)、(b)、(c)に東京、ニューヨーク、ロンドンを入れて、表を完成せよ。回答は表にそのまま記入すること。(3点)
|
|
利用者数(百万人) |
1998年 |
|
|
地下鉄 |
都市鉄道 |
バス |
|
|
(a) |
1,199 |
207 |
616 |
|
パリ |
1,157 |
909 |
850 |
|
(b) |
832 |
553 |
1,277 |
|
(c) |
2,545 |
6,323 |
609 |
|
大阪 |
926 |
2,040 |
155 |
問3.
下表は、ある都市における公共交通機関と自家用車という交通手段の弾力性について、通勤用と買い物用の両方の場合の推計値を示したものである。この表を参考にして、以下の文章の( )内で適切な方の文字に○を記せ。また、文章中にある____に入るべき数字を、文章中に記せ。(10点)
|
|
|
自己弾力性 |
交叉弾力性 |
||
|
|
|
価格 |
時間 |
価格 |
時間 |
|
公共交通機関 |
通勤用 |
ε11=0.17 |
η11=1.10 |
ε12=0 |
η12=0 |
|
買い物用 |
ε11=0.32 |
η11=0.59 |
ε12=0 |
η12=0 |
|
|
自家用車 |
通勤用 |
ε22=0.56 |
η22=2.26 |
ε21=0.14 |
η21=0.37 |
|
買い物用 |
ε22=2.53 |
η22=2.46 |
ε21=0 |
η21=0.10 |
|
公共交通機関に関しては、自己の価格弾力性が通勤用で0.17、買い物用で0.32と小さく、需要が(弾力的、非弾力的)である。これは、公共交通料金を下げても乗客員数はそれほど(増加、減少)せず、逆に料金を引き上げれば、需要はあまり(増加しない、減少しない)ため、公共交通機関の総収入は増加することを意味する。
自家用車については、通勤用の需要の自己価格弾力性が0.56と、比較的非弾力的であるのに対して、通勤時間外の買物用の需要は自己の価格に対する反応が比較的(小さく、大きく)、弾力性の値は と大きくなっている。
したがって、ガソリン価格の上昇や高速道路料金の引き上げにより、通勤時の自動車数は(大いに減少する、さほど減少しない)が、買い物やレジャー用のマイカーの使用は(大いに減少する、さほど減少しない)であろう。
同様に、通勤のための自家用車の使用も、価格に関しては非弾力的であるのに対して、時間に関する弾力性は比較的(小さな、大きな)反応を示す。したがって、高速道路の整備によってマイカー通勤の時間が短縮されるならば、たとえ高速道路料金が多少引き上げられたとしても、通勤用の自家用車の利用は(減少、増加)するであろう。さらに、この表からうかがえる特徴は、すべての交叉弾力性が一様に(大きい、小さい)ことである。
問4.
以下の文章は道路の交通需要の市場均衡と最適交通量の関係の説明を試みているものである。図を参考にしながら、文章の空白部分に入るべき適切な用語、数字、記号を、文章の空白部分に記せ。また、2語あるものは適切な方に○印をつけよ(10点)
外部効果が存在する場合、一般に市場均衡解と資源配分上の最適解が相違することは、よく知られている。実際、道路の混雑と渋滞によって( )が生じるならば、市場で決定される均衡交通量は、社会的に最適な交通量を上回るであろう。
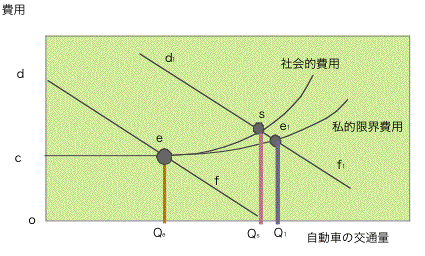
なぜなら、需要曲線と社会的限界曲線の縦の長さの差で表される社会的余剰の合計が最大となる点は下の図における( )であり、それに対応する社会的最適交通量は( )となるのに対して、市場均衡点は需要曲線と私的限界費用曲線が交わる点e1であり、市場均衡交通量Q1が最適量( )を上回るからである。
つまり、各個人は自分の支払う費用が利益よりも小さい限り、道路を利用しようとするが、その際自分の車が混雑の程度を悪化させ、他のドライバー達の負担を(上昇、下降)させることによる社会的費用の増加分は考慮しないから、最適量以上の車が道路を使用し、過度の混雑と渋滞が起こることになる。
問5. 都市の交通問題は、大きく4つにまとめられる。それらの問題を挙げ、それに関して簡単に論ぜよ(4点)