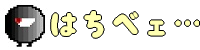
1 絵を描く
私は、絵を描くのが好きだった。子供の頃は、当時の好きだったキャラクターをとにかく模写していた。教科書やノートは落書きだらけだった。中学生の時、絵を描くのが好きな友人たちと、一人一コマずつ順番に描いていく「交換漫画」というものを作って遊んでいた。模写するときは、対象をよく見て描き写すだけでよかったが、漫画となると、自分で絵に表情や動作をつけなければいけない。どうすれば怒っているように見えるか。どうすれば走っているように見えるか。線を描き足したり、角度を変えてみたりするだけで、絵の印象はがらりと変わる。コマの中に空間を感じさせるように、遠近法を駆使したり、構図を考えたりもした。皆で一コマずつ描いていき、やがて頁が埋まる。こうして白紙だったノートは、曲り形にも「漫画」になっていく。
それにしても、絵とは不思議だ。白紙の紙に、ペンで跡をつける。それが何かに見えたとき、私たちはその跡を「絵」と呼ぶ。しかし、実際にそこに人や物、世界があるわけではない。「そう見える」だけの錯覚と言い切ってしまうこともできる。「絵」ではなく、絵の具が塗られたことによって、それらしく見えるただの「紙」だと。私たちが「絵」と言って見ているのは、たくさんの線が描かれた、単なる「紙」に過ぎないのだ。特に漫画的表現とは、簡略化・記号化によって、いかに錯覚を起こすか、というものである。吹き出しによって、いかにも登場人物が話をしているかのように錯覚するが、あれは枠の中に文字が貼られているだけ、とも言えるということだ。
しかし、私たちはその紙を見て、何か連想させられることもあれば、感動することもある。「絵」は単なる「紙」以上の意味合いを持つようになる。現実と見間違えるようなリアルな世界、あるいは超現実的な世界を表象するものとなり得る。猫の視点からすれば、私たち人間は紙を眺めているだけにしか見えないだろうし、実際にその通りである。私たちは、単なる紙に絵を描きこんでいくことによって、意味を創出する。また反対に、何か描きこまれた絵を見て、意味を見出す。絵を描き、絵を見るという体験は、人間の創造力・想像力をわかりやすく表しているように思えるのだ。
2 プラモデル
小学生・中学生の時、私が最も熱中していたのはガンダムのプラモデル、通称「ガンプラ」。他にも好きなことはあったが、費やした金額のことを考えると、プラモデルはケタ違いだった。小学生の頃から、絵を描いたり、何か作ったりするのは好きで、図工・美術の時間はいつも楽しみだった。親戚のおじさんが、いらなくなったガンプラをくれたことが最初の出会い。さらに、同時期に映画『機動戦士ガンダム』を見てしまったことにより、アニメ・プラモデルとの相乗効果で、一気にガンダムを好きになり、プラモデルを買い漁るようになった。
私はプラモデルを作っているとき、「早く完成させたい」という気持ちと「丁寧に取り組みたい」という気持ちがせめぎ合う。早く完成させて、早くそいつで遊びたい。一方で、一つ一つのパーツを丁寧に組み立てて、完成度の高いものを作りたい。こうした葛藤を抱きながらプラモデルは作られる(あくまでも私の場合)。
プラモデルを作るときは、部屋に引きこもる。音楽をかけたりもしない。一人で黙々と作業をすることになる。新聞紙を敷いて、買ってきたプラモデルの箱を開ける。パーツを並べて、説明書をざっと読む。あとは説明書に通りに組み立てていくだけ。だいたい「早く完成させたい」という気持ちが強く、早ければ1時間くらいで完成させる。丁寧に取り組んでも、組み立てるだけなら1日か2日で完成させる。
熱中して何十体もプラモデルを作っただけあって、その風景がすぐに浮かぶ。 ひとり静かな部屋。ニッパーでパーツを切り取る「パチッ」という音。切り取られたパーツをはめるときの感触。段々と出来上がっていくときの静かな興奮。完成したときの達成感。ずっと座っていたことによる足の痺れ。
プラモデルを作るときは、自分だけの集中した時間だ。本を読むときのように頭を使うこともないし、目の前の作業に没頭するだけなので、ひたすら無心に作っていたように思う。今では、その時間は音楽を聴くことによって取って代わられたが、一人で集中して何かを「作る」ときの感覚は、そういえば久しくないかもしれない。なぜ、あれほどプラモデルに熱中していたのか、それは作っているとき独特の空間が心地よかったからかもしれない。
3 プロレス
中学生のとき、私は毎週楽しみにしている番組があった。それはプロレスである。アメリカのプロレス団体WWEの試合の様子が、スポーツチャンネルで週2回放送されていた。全くスポーツは見ないが、これだけは欠かさず見ていた(プロレスをスポーツと言えるかは置いといて)。DVDを買って見てしまうほど好きだった。なぜ華奢な私が、これほどプロレスに熱中してしまったのだろうか。
プロレスはエンターテイメントである。そもそもプロレスは、勝敗を競うスポーツとは姿勢が根本的に異なる。観客を楽しませることが目的なのだ。だからプロレスには、観客を楽しませるための演出(台本)がある。観客を楽しませるために、ストーリーに沿って、戦う理由をつくる。例えば、チームを組んでいたのに裏切られたとか、女を寝取られたとか、馬鹿にされたとか、とにかく観客が感情移入できるように戦う理由を何かしらつける。勝敗は戦う前から決まっており、プロレスラーは台本に従った試合運びをする。
WWEの場合は、そうした観客を楽しませる仕掛けが盛大に盛り込まれている。試合の間には必ず、ドラマのような展開がある。そこで起こった出来事が発展して「勝負はリングで着ける」ということになる。中学生のときは、特に気にならなかったが、最近見直すと「おいおい」と突っ込みたくなる強引な場面がたくさんある。試合中も、関節技が明らかにきまっていない、乱入のタイミングが絶妙であるとか、壮大な茶番劇を目にしているような気になるときもある。
台本がある出来レースとわかっていても、惹きこまれてしまう。これは演劇を見ているときのような感覚に近いかもしれない。目の前に起こっていることは虚構であるとわかっているのに、それを忘れて見入ってしまうように。しかも、プロレスは実際に戦っている。ここが演劇と決定的に違う点であるが、プロレスは戦うフリではない。固いマットに叩きつけられ、コーナーポストからエルボーを投下され、パイプ椅子で思いっきり殴られ、ハシゴから落とされる。これらのことは演技だとしても、実際に体を痛めつけ合う過酷な戦いなのだ。
台本があるとわかっても、試合によっては感動して泣いてしまうことがある。試合後にフラフラになりながらも観客にアピールしている姿を見ると、出来レースであることなど、どうでもよくなる。彼らは観客のために身を削って、本当に命がけの試合をしている。その覚悟が垣間見えると、演技・台本どうこうを凌駕した感動を与えられてしまうのだ。
4 ギター
いろいろな楽器があるが、ギターという楽器は特別な存在感をもっている。今日では、ギターを弾くということは、さほど珍しいことではない。私は軽音サークルに所属していたが、最も人気の高い楽器はやはりギターだ。どの学年もギター人口が一番多い。もちろん、他の楽器にもそれぞれ特異性はある。それを踏まえても「ギター」という楽器の存在は、かなり特殊であると思われる。ギターは、どうしてこれほどまでに普及したのか。
まずギターは、手を出しやすい楽器と言える。安いギターは1万円前後で買える。TAB譜というギター専用の簡単な楽譜があり、五線譜が読めなくてもいい。多くの教則本が出回っていて、独学である程度弾けるようになる。そうした「誰でも手を出せる楽器」であるギターは、同時に「弾けるとカッコイイ楽器」でもある。若者に人気のあるバンドには、必ずギターがいる。ギターはサウンドの要であり、バンドの花形である。しかもボーカルとギターは一緒になっていることが多く、弾き語りも出来る。ギターを弾くのはカッコイイことであり、自己顕示欲を満たしてくれる。こんな好条件だらけの楽器は他にあるだろうか。
私は高校生のとき、ギターで弾き語りができることに憧れた。そこで、父親がアコースティックギターを持っていたことを思い出し、自分の部屋に持っていき、それから弾きはじめたのを覚えている。軽い気持ちで始めたら意外と難しくて、「ちゃんと弾けるようになるのか?」と思いながら、とりあえず教則本を読み進めていた。
ある日、我が家の押し入れには、実は「エレキ」が眠っているという話を母親から聞いた。エレキギターには、アコースティックギターと全く違う印象を抱いていた。上手く言えないのだが、ちょっと怖い人の楽器というか、いわゆる「ロック」という言葉のイメージに代表されるような、暴力的な響きがしたのだ。その反面、「エレキ」を弾いてみたいという好奇心は大きく、これまた上手く言えないのだが、イケないことに手を出すような、大人の世界に飛び込むような、何とも言えないドキドキ感があったように思う。
実際は、思ったようなカッコイイ音が出なくて「あれ?」と思ったものだが、エレキを弾くということに感動したのを覚えている。漫画『本格科学冒険漫画 20世紀少年』(浦沢直樹)には、中学生だった主人公が、憧れの「エレキ」をはじめて手にした自分の姿を見て、「そこにはマシンガンを手にした無敵の男が立っていた」という回想する場面があるのだが、まさにそのような感覚なのである。 それから今までギターを引き続けている。もちろん、どうすれば良い音が鳴るか、どうすれば上手く弾けるか、バンドで弾くときは何を心がけて弾くか、という純粋に楽器としてのギターにも、興味は尽きない。しかし、それと同じくらい「ギター」というイメージに興味がある。「ギターを弾く」という特別な響きの正体を暴いてやりたい。
5 音楽聴取
音楽を聴いているとき、私は何をどう聴いているのか、と我ながら思うことがある。目を瞑って聴くとき、目を開けて聴くときでは、聴いている音楽の印象は違ってくる。姿勢を正して集中して聴くこともあれば、横になって漫画を読みながら聴くこともある。歌を中心に聴くこともあれば、楽器を中心に聴くこともある。このように、そのときの状況・心情・関心に合わせて、聴取のあり方は異なってくるはずだ。
日本の住宅事情では、音楽を大音量で聴くというのは難しい。あまり大きな音で再生すると、親から注意されてしまう。ヘッドホンをつけて聴くことで我慢するが、ずっと聴いていると疲れるし、全身で音楽を聴くという感覚は得られない。だからこそ、ロック喫茶やカラオケ、ライブハウスやクラブなど、大音量で音楽を聴くことのできる空間は、特別な体験となる。音楽を聴く手段は、環境によって限定され、音楽聴取のあり方に影響を及ぼす。
私は、歩きながら音楽を聴くのが好きだ。通学・散歩など、歩きながらiPodで音楽を聴くと、頭によく音楽が入り集中して聴けるのだ。クラシックやジャズなど落ち着いた音楽であれば、家でゆっくり聴きたいと思うが、リズムが強調されたポップスやロックといった音楽は、聴いていて体を動かしたくなるので、歩きながら聴くと丁度いいのだ。テンポの早い曲であればズンズンと進むし、しっとりとした曲ならゆっくり歩く。このように曲にあわせて体が動いてしまうというのも、聴取のあり方として面白い。
また、音楽だけを聴くことより、映像と一緒に音楽を聴く機会は非常に多い。テレビ、映画、ライブDVD、YouTubeなど、音楽・映像はセットになっている。私は、DVDやYouTubeでライブ映像を見ることが好きなのだが、映像があるかないかでも、曲の印象は大きく変わる。何がどう違うのか、自分でもよくわかっていないのだが、だからこそ関心がある。少なくとも、ライブ映像は演奏者のパフォーマンスを見ることができるというのが大きな魅力と言える。さらに言えば、ライブ映像と実際のライブを比較しても、曲の印象は大きく変わる。
ここに挙げた聴取のあり方は、私の経験に即した、ほんの一部に過ぎない。聴取のあり方は、人によって、地域によって、時代によっても違ってくるだろう。音楽聴取には、多種多様な聴取のあり方があり、興味が尽きることはない。
6 観客
初めてのライブ体験は、高校生の時に行ったMr.Childrenのライブである。場所は日産スタジアムで、とにかく人が多かった。慣れないライブで緊張しつつ、開演を楽しみにしていた。バンドが登場して、演奏が始まると、観客のノリ方に驚いた。誰が指定したわけでもないのに、同じ方向に手を振ったり、特定の場所で掛け声があったり、手拍子をしたりするのである。予想していたことではあったが、いざ目の当たりにすると、正直とても不気味に感じた。私の周りの人も同じようにしていたので、自分だけやらないのは逆に恥ずかしく、あまり気が進まなかったが、皆と同じようにした。強制されているわけではないのに、周りの流れを無視したときの居心地の悪さは何だろうか。
このように感じている人は決して少なくないだろう。こうした風習はどうやって出来上がったのか。アイドルのコンサートでも、こういった現象はよく見られる。米米CLUBのライブでは、観客にノリ方を提示するかのようなパフォーマンスが見られる。エンターテイメントの一環として、そういう“ノリ”があるのは特に違和感を感じない。違和感を感じるのは、「ライブ会場が一体となる」「気持ちが一つになる」といった類の“ノリ”である。そういうことを言われると、「じゃあ、ここで冷めている私は何なのでしょう」と思ってしまう。
日本にロックが入ってきた当初は、日本の観客はどう聴いたら良いかわからず、ロックのライブであるにも関わらず、クラシックのように真面目に聴いていたそうだ。また、各国でライブをしてきたミュージシャンの「どこどこの観客は最低だ」「どこどこの観客はクレイジーだ」という発言や、アメリカのプロレス団体WWEが日本公演を行ったときの「日本の観客はちゃんと試合を見てくれるし、礼儀がとても良い」という発言から、時代・地域によって観客のあり方というのは違うようだ。
私たちは会場に行けば「観客」として一括りされ、総体として独特の存在となる。その内の一人ひとりは、一体どのような「観客」となっているのだろうか。
7 サウンド
私たちはなぜ音楽を進んで聴くのだろうか。それは、音楽とは基本的に「聴いていて気持ち良いもの」であるからだと思う。音楽は聴く者に様々な感情を呼び起こす。その中には、緊張、不安、絶望といった負の感情を呼び起こすものもある。そうした負の感情を呼び起こされても、好んで聴き続けることができるのは、音そのものは聴いていて生理的に気持ち良いからではないだろうか。それこそ不快な騒音であったら、進んで聴けたものではないだろう。気持ち良い音で様々な感情を表現するのだから、私たちは音楽を進んで聴き続けることが出来るのではないだろうか。
それでは気持ち良い音とは何なのか。近田春夫は「ロックは音圧」と言った。ロックは大音量で聴くものだ。ロックの中心楽器であるギターは音が割れて、「歪んだ音色」として好まれている。騒音と思われてもおかしくないほど、うるさいのに、それは不思議と聴いていて気持ち良いのである。それはバイクのエンジン音が心地良いというのと感覚は似ているかもしれない。下手な人がドラムを叩くと、ドカドカした騒音になってしまうが、上手い人が叩くと、音量は変わらなくても、聴いていて気持ち良いものになる。
このように考えると、気持ち良い音とは「サウンドになっているかどうか」ということだと思う。サウンドとは面白いもので、同じ音でも、騒音・ノイズと受け取られることもあれば、心地いい「サウンド」として聴こえることもある。ギターのハウリングは、最初はノイズとして、出してはいけないものだったが、今では「フィードバック」としてかっこ良く聴かせることも出来る。ギターの弦と指がこすれて出る音は、聴き方によってはノイズにもなるし、「味のある演奏」として聴くことも出来る。
音楽によって、聴き手の耳は変化するということだろうか。そうでなければ、本来クラシックでは不協和音として使ってはいけないはずのテンション・コードが、ジャズなどで使われるようになったことは説明できないように思われる。それは聴き手の耳が肥えて、不協和音をサウンドとして聴くことができるようになったということだろうか。音を音楽的な「サウンド」にさせているのは、一体何なのか、興味があるところである。
8 身体
私は運動が大の苦手である。体育の授業は本当に嫌で仕方なかった。とにかく体が思うように動かない。いや、それ以前にどう動くべきかわからない。サッカーでパスされても、うまくトラップできない。ボールを蹴ると、強すぎたり弱すぎたり、違う方向に飛んで行ったり、とにかく役に立てない。自分は運動神経が悪いのだと、完全にスポーツは諦めていた。
大学生になってドラムを叩くようになった。本格的に打ち込んだわけではないが、やはりそれなりに上手くなりたいし、ドラムという楽器の特殊性だと思うが、何よりドラムで演奏するのは楽しかったので、ドラムセットに触れる機会があれば叩くようにしていた。そこで、スポーツと同じく「体が思うように動かない」という問題に直面することになる。
ドラムは体全体を駆使する楽器だ。友人のドラマーは「ドラムはスポーツだ」とよく言っていたが、確かにそのような面がある。基本的に楽器を弾くというのは、体を思うように動かせることが大前提だ。どうすれば良い音が鳴るか、理屈でわかっていても、体がついてこなければ意味はない。楽器に合わせた“身体”をつくることが、楽器を習得するということである。
私はギター教室に通っているのだが、重要なのは基礎であると言われる。身体は反復練習を通して、動きを会得していく。トレーニングによって身体に動きを馴染ませて、身体にその回路をつくってやればいい。ただ間違った動きで反復練習をしてしまうと、それは悪い癖になり、改善することは難しい。スポーツにしても楽器にしても、上達するかどうかは、合理的で無駄のない動きを身につけられるか、という基礎にかかっている。私の運動音痴は、反復練習によっていくらでも改善できたということだ。
ギターの先生から教えてもらった興味深い話をもう一つ。よく音楽には「グルーヴ」という言葉が使われる。定義は曖昧であるが、音楽愛好家の間ではよく濫用される言葉である。日本では「ノリ」と言ったりするが、その先生は「グルーヴはリズムの訛り」であるという。地域によって言葉の訛りがあるように、リズムにも訛りがあり、それがグルーヴであると言うのだ。人間の身体は、後天的にいろいろな影響を受けて、動きを獲得しているのだ。
9 夜
私は生活が不規則で、夜は寝ないで起きていることも多い。朝寝坊をしてしまって、夜は眠たくならないからである。それにしても、夜は目が冴える。特に家族の皆が寝静まったとき。夜の静けさは、感覚を研ぎ澄ますかのように、集中を促してくれる。昼間はどうも気が散ってしまうのだが、夜は何をするにしても集中して取り組むことが出来る気がするのだ。
夜道も魅力的だ。飲み会などで帰りが遅くなってしまった時、最寄り駅から自宅まで歩いて変えることが多い。昼間なら車・バス・人で忙しない駅だが、深夜1時頃になると、さすがに車も人も少ない。風景に動きがなくなるのだ。黒い道路に暗い空と、信号や電柱の光が目立つ。昼間よりも、音が鮮明に聴き取れるし、動きに敏感になる。
本当なら集中できる夜にこそ、楽器を弾いたり、音楽を聴いたり、声を出してみたくなる。昼間だと、メールが来れば、部屋に親が入ってきたりもする。昼ごはん、夕ごはんに合わせて作業を中断し、時間に気を遣わなくてはならない。夜だとそうしたことがなく、存分に時間をたっぷり使えるのが良い。明るくなってきたら、そろそろ作業を終わらせるかと、そこで調整すれば良い。
しかし、人間は本来夜行性ではない。私の母も「徹夜は体に良くないから、朝方に切り替えなさい」とよく言う。人間の本来の生活リズムに逆らうことになるのだから、夜型が体に悪いのは当然だ。しかし、私に限らず、夜型の人は少なくないように思われる。仕事から帰るのが夜遅くて遊ぶ時間が夜しかない、という人もいるだろう。大学生で、生活リズムが滅茶苦茶な人は、さほど珍しくはない。高校生だって、試験前などは徹夜して勉強したりする。24時間営業ンのコンビニ・ファミレスなどあることから、夜行性の人は増えているのだろうか。
自戒の念を込めて言うのだが、人間の本能に逆らってまで夜型になって、私たち夜行性の人間は何がしたいのだろうか。個人的には、夜に不思議な魅力を感じてしまうし、夜でも作業が出来てしまうことから、潔く朝方に切り替えることは難しい。
10 スタジオ・ミュージシャン
「スタジオ・ミュージシャンは職人的で、個性がない」と言う人がいた。確かに、スタジオ・ミュージシャンは、基本的には主役のバックで黙々と演奏しているため、上手い人であれば誰が弾いても同じなのではないか、とも思ってしまう。そもそもスタジオ・ミュージシャンに求められるのは、楽曲に合わせた演奏をすることが出来る技術であって、決して個性ではない。
しかし、自分で楽器を弾くようになるにあたって、スタジオ・ミュージシャンの演奏力の高さに憧れをもつようになる。音楽番組では、歌っている主役よりも、バックバンドのほうに目がいってしまう。井上陽水のライブ映像を見ると、バックにいるのは大御所スタジオ・ミュージシャンばかりで、とても見応えがある。「縁の下の力持ち」のようなポジションが好きなのかもしれない。
こうして、スタジオ・ミュージシャンを見ていると、個性がないとは決して思えなくなってくる。彼らは個性を消したように見せて、楽曲に従事する能力があると考えるとどうだろう。そして楽譜を初見で見て、すぐに演奏することが出来る能力を持っている。それらは個性とは違うかもしれないが、スタジオ・ミュージシャンはそうした特別な能力が備わっている。それがプロと言われる所以であるわけだが、私は「あるジャンルは上手く弾けて、あとはよくわかりません」という個性より、「何でも弾けます、サポートします」というほうに惹かれてしまう。
何よりスタジオ・ミュージシャンには、音楽への深い愛情が感じられる。どのように楽曲に貢献するか、どうすれば楽曲を良く聴かせられるか、という自分の主張を超えた、楽曲へ従事する姿勢。スタジオ・ミュージシャン以外はそうでないということではない。人の楽曲を演奏する、スタジオ・ミュージシャンという職業上の基本姿勢が、献身的で素晴らしいと思うのだ。そして、自由な演奏がある程度許される場面で、スタジオ・ミュージシャンが発揮する「本気の演奏」は、速弾きのような曲芸的な凄さではなく、上手く言えないが、芯のしっかりした貫禄のある凄さが滲み出ているように思える。どうやって、そうした凄みが出るようになったのか、素晴らしい演奏を聴くたびに考えてしまうのである。
11 ロック像
「ロック」という言葉に特別な響きを感じる。今さら「ロックとは何か」なんて言い出すのは時代錯誤であると思うが、私にとって「ロック」とは特別な意味合いをもっている。それは音楽雑誌「ロッキング・オン」で、ロックに関する言説を読んできたからだと思われるが、おかげで「ロック」という言葉にこだわるようになってしまった。
ある服装・言動に対して「ロックだねえ」などと言うことがある。それを聞くたびに、この場合における「ロック」とは一体何なのだ、と思ってしまう。こうした偏見にまみれた「ロック」を耳にする機会は多い。最近ではテレビドラマ『ハングリー!』(2012年)の「料理 is ロック!!」というキャッチコピーに違和感を覚えた。それでは自分がもつ「ロック」のイメージは偏見ではないのか、と言われれば、まさにそのとおりで返す言葉もないのだが。
とにかく、違和感のある「ロック」に出会うたびに感じる「ロックとは何か」という疑問は、そのまま関心につながり、「ロック」というイメージが、人によって、時代によって、地域によってどう違うのか、そのイメージはどのように形成されるのか、興味をもつようになった。
「ロック」が時代・地域によって、どのように認識されているのかを比較するのは面白い。映画『ウッドストック』(1970年:マイケル・ウォドレー)と、『ソラニン』(2010年:三木孝浩)を見てみると、両者の「ロック」というイメージが、あまりにかけ離れていることに気づく。それは、時代によるものかもしれないし(ちょうど40年)、アメリカと日本という国の違いによるものかもしれない。個人的な感想では、『ウッドストック』は、欲望が渦巻き薄汚れた、だからこそ生々しくリアルな「ロック」で、『ソラニン』は、そうした薄汚さを一切排除した、クリーンで前向きな「ロック」というようなイメージの違いがあるように思った。
「ロック」は、もちろん音楽もそうだが、それと同じくらい、ファッション・パフォーマンスなど、音楽以外の要素が重要視される。そうした音楽以外の要素は、「ロック」というイメージ作りに大いに貢献している。「ロック」というイメージについて考えることは、音楽性にとどまらない広がりのあるものとして、興味が尽きないのである。
12 流行
私は何となく流行を追うのに抵抗があった。「流行というのはいずれ廃れるもので、いちいちそれに踊らされていたのでは堪らない」など、それらしい理由をつけて自分を納得させようとしていた。一方で、少しくらいは流行に乗っても良かったのでは、と思うこともある。天邪鬼として生きて21年、ここまで来たら天邪鬼を貫き通してやろう、という開き直りもある。この流行に対する心理は何なのか。
私は流行そのものが嫌なわけではない。流行がつくる「流行に乗らないと皆からダサいと馬鹿にされますよ」というような風潮が嫌なのだ。今まではそう思っていたが、それでは流行に乗っていないからといって、実際に馬鹿にされたことはあっただろうか。そう考えると、意外とそんなことはない。では「流行に乗らないと皆からダサいと馬鹿にされますよ」というのは何だったのか。自身が勝手に作り上げた強迫観念、あるいは被害妄想だったのだろうか。
流行という現象は不思議なものだ。明らかにテレビや雑誌が仕掛けるような、押し付けがましい流行もあれば、いつの間にか自然発生していたかのような流行もある。流行しているか、という明確な判断はないが、「今はこれが流行っている」というのは、なぜか皆の共通認識としてあるものだ。
私は意識的に流行に乗ろうと思ったことがある。高校生のときに、当時オリコンチャート上位に入っているものを、なるべく借りて聴くようにしていた。話のネタとして有名な曲を知っておくか、という程度の理由で。高校生になればきっとカラオケによく行くようになると思い、そのために歌を聴いているようなものだった。結局借りてもたいして聴かないので、いつの間にか止めてしまったが、流行を追うって大変だな、と思った記憶がある。
そもそも、誰が流行を追っているのだろうか。私は「皆流行に流されちゃって」と卑屈に思っていたが、身の回りであからさまに「流行を追いかけています!」という人はいたのだろうか。思い当たる人はいるが、決して「皆」ではない。それとも意識しないうちに、それこそ「皆流行に流されていた」のだろうか。流行という言葉に何となく不快感を覚えていたが、考えれば考えるほど、流行の実態が見えてこない。
13 受け継ぐ
私の名前は「継人」という。珍しい名前だと我ながら思うが、自分ではこの名前を気に入っている。自分の大切な何かを受け継ぐというのは素晴らしいことではないか。そんなこともあってか、私は何かと懐古主義的なところがある。音楽・映画・テレビ・漫画など、全てにおいて一昔前のものに惹かれてしまう。 あくまでも手の届く範囲での「昔」だが。
映画『ゲット・ラウド』(2011年:デイヴィス・グッゲンハイム)では、3世代を代表するロック・ギタリストが登場する。その中で若手のジャック・ホワイトは、「先輩たちが作った物語を紡ぐ家族の一員になる」ということを言っていた。伝統を受け継いでいくのだ、という姿勢に感銘を受けたし、伝統を受け継ぐには、伝統の中に飛び込んでいかなければいけないと思った。
ミュージシャンは必ず何かしらの音楽に、直接的・間接的な影響を受けている。それは樹形図のように広がっていて音楽界を形成している。私は高校生のとき奥田民生を好きになった。奥田民生がインタビューで、理想のバンドについて聞かれて、「Led Zeppelin」と答えていたので、私はそれまで知らなかったLed Zeppelinを聴いてみた。すると似たような曲があったりして、「奥田民生のルーツはここにあったのか!」と、わかったのが嬉しかった記憶がある。
伝統の中に飛び込んだ人というのは、歴史を感じさせる演奏を聴かせてくれる。これは音楽に限らず言えることだ。そして、そうした人が影響を受けた先人の作品というのは、今見ても面白いものだ。むしろ新鮮に感じて、巷で流行っているものよりも面白いことが多い。黎明期の作品というのは、まだ手法が確立していないため、実験的であることが多い。また一昔前だと、現在のようなハイテク機器がないが、逆にそうした制限があることによってどうにか工夫を凝らして、結果それが個性的な表現となる場合もある。
人間は、遺伝子にはない情報を、さまざまな形で大昔から伝えてきた。今日では情報過多であり、本当に大事なものはわかりにくい。何でもかんでも記録として残そうとするため、情報は溜まっていく一方だ。このような状況の中で、私たちは何をどう受け継いでいくのか、人生の課題であるように思う。
14 無意識
自分とは一体どういう人間なのか。血液型・心理テスト・占いなどで、「あなたはこのような人間です」と自分のことを教えてほしいと思う反面、「人間を一言で簡単に説明することなんて出来るはずないだろう」とも思う。人間の心理はどうなっているのか。思考回路はどうなっているのか。感情はどこから来るものなのか。価値観はどのように形成されるのか。これらのことを考え、心理学に関心をもっていたが、『暗黙知の次元』(マイケル・ポランニー)、『無意識の構造』(河合隼雄)を読むことで、具体的に「無意識」に関心をもつようになった。
私たちの思考・行動は、無意識と切り離すことはできない。だからこそ思い通りに生きることは難しい。やってはいけないことをついやってしまったり、頑張らなければいけないところで手を抜いてしまったり。その通りに実行できたら苦労はしない。どうすれば結果的に良いのか理性ではわかっているのに、それとは違うことをしてしまう。無意識に、私たちはどこかで抑制をかけて、心のバランスが崩れないように注意を払って生きている。
漫画『ホムンクルス』(山本英夫)は、人間の深層意識やトラウマに迫り、『暗黙知の次元』『無意識の構造』と併せて読むと面白かった。主人公は、人のトラウマが「見える」ようになり、深層意識に抑えられた感情を思い出させることを通して、相手を、そして自分を知っていく。人は何かを忘れるといっても、完全に記憶から削除されることはなく、それは深層意識を漂っている。そうした深層意識にあるものが、意識に刺激を与えながら、私たちは生きている。深層意識とは記憶の眠るところであり、そこに自分のヒントが隠されている。
自分自身の知ることのできない領域である無意識からのヒントを、どれだけ逃さずキャッチできるか。外界から無意識に刷り込まれたイメージに、どれだけ自覚的になれるか。私という人間が何なのか、自分でもわからないだけ、自分を対象化していくことにとても興味がある。
15 世界観
人はそれぞれ固有の世界観を持っている。ここで言う世界観とは、その人固有のモノの見方のことである。人の話を聞いていると、自分とは全く違う世界観に驚くこともあれば、似たような世界観で同調することもある。素晴らしい芸術作品というのは、作者の世界観がそのまま表象されているようである。何にせよ、それぞれの世界観と出会うのは、とても刺激的であるし、好奇心をそそるものだ。
私が大学1年生のとき、軽音サークルに入部したときのことである。軽音サークルに入るからには、皆やはり音楽が好きなわけで、似たような価値観をもつ人が多いものだと思っていた。表面的に好きなものは異なるにしても、音楽への関心・愛情という根本的なところにおいては、程度の違いはあれども皆共通すると考えていたのだ。
しかし、私はY君と音楽の話をして驚いた。好きな音楽について聞かれたので、好きだったインストゥルメンタル(ボーカルのない楽器だけの音楽)を聴かせたところ、「歌がなくてつまらない」と一蹴されてしまったのだ。Y君の良いと思う基準と、私の良いと思う基準は、あまりに掛け離れていたのだ。同じ音楽好きであっても、向かうベクトルが全く違うということが、今では興味深く感じられる。
音楽との接し方があまりに違うことから、どのようにY君はこうした価値観を身に付けるに至ったのか、と私は考えるようになった。出身の違いによるものだろうか、年齢の違いによるものだろうか。きっと一言では片付けられない。Y君と話しているうちに、価値観ではなく、きっと見えている世界が違うのでは、と思うようになってきた。モノの見方が違えば、目に映る世界も変わる。
大学3年生のとき、デジタルアート論の講義をしていた鈴木先生の話を聞いて、その思いはさらに強まった。鈴木先生はアーティストであり、自身の手がけた作品を見せてくれた。日常に見られる何てことないようなものを、いくらでも深読みできるような「作品」にしてしまう鈴木先生を見て、私は「この人にとって世界はどのように見えているのだろうか」と、いつも不思議だった。
そのようなこともあり、私は「価値観」より「世界観」のほうがしっくりきて、一人一人が固有の世界観を持っていると考えるようになった。何十年か生きてきた全てのことが、世界観に反映されていることから、世界観とはそれまでの生き方の集大成と言える。だからこそ世界観には、その人の人生が読み取れるような気がして面白いのだ。芸術の面白さは、作者の世界観が作品にダイレクトに表象されていることであり、その世界観が自分のモノの見方に刺激を与えるからこそ面白いのだ。