
1 好かれる悪役 バイキンマン
小さい頃、ヒーローが悪役を倒すという話しのアニメをたくさん見ていた。ウルトラマンや仮面ライダーやセーラームーンやアンパンマン。彼らはいつも悪を倒しみんなの平和を守っている。でもアンパンマンだけはどこか違った。アンパンマンもいつも悪者であるバイキンマンを倒して、みんなを助けている。でもバイキンマンは何回やられても毎回でてきてアンパンマンと戦う。私は当然アンパンマンを応援しながら見ているのだけど、バイキンマンも嫌いではなかった。懲りずにアンパンマンを倒そうとするバイキンマンがおもしろかったのだ。悪者も好きになれるアニメはアンパンマンが初めてだった。
アンパンマンミュージアムでは、アンパンマンだけではなくバイキンマンのグッズも売っている。ぬいぐるみやふうせんやマントがあり、子どもたちはみんなアンパンマンを欲しがるかと思いきやそうではない。バイキンマンのぬいぐるみを持った子や、バイキンマンのマントをつけた子も大勢いる。やはり私だけに限らず、多くの子どもがバイキンマンを好いているのだ。バイキンマンが悪役でありながら好かれる理由はなんなのだろうか。
バイキンマンは確かに悪者だけど、笑えるマヌケさを持った悪者である。ドキンちゃんには怒られているし、アンパンマンにはいつも勝てない。それでも自信満々で戦いを挑む。そんなバイキンマンがかわいく思えてきて、つい応援したくなるのだ。アンパンマンはいつもいい人で、間違ったことをしない。しかし逆にそれが私たちとは違う存在に思えるのではないだろうか。いくらヒーローに憧れてもバイキンマンのような少し悪い心を私たちは持っている。だから私たちはバイキンマンの気持ちもよくわかるのだ。アンパンマンのように正当に生きているヒーローもいいけど、悪役だがちょっとドジでかわいいところがある人の方が私たちには親しみやすく思えるのかもしれない。
小さい子はバイキンマンを怖がったり嫌ったりする。しかしちょっと大きくなってくるとバイキンマンが好きと言う子どもが増えてくる。子どもだけに限らず、大人もたいていバイキンマンが好きである。少し悪い心や、ずるい心を持つようになるとバイキンマンの良さがわかるのかもしれない。でもバイキンマンがアンパンマンに勝つことはない。そこもまたバイキンマンのいいところである。少し応援したくなるようなかわいい悪役のバイキンマンだが、最後には必ず正義にやられてしまう。それがさらにバイキンマンを愛おしく思える理由なのではないだろうか。彼はみんなに好かれる悪役なのだ。

2 衝動買い
今日買ったものはなに?それは前から狙っていたもの?それとも衝動的に買ってしまったもの?人はなぜ「衝動買い」をしてしまうのだろうか。
私はよく散歩へ行く。行き先はどこでもいい。近所でもいいし、電車に乗って都会へ行くのもいい。私の家の近所は自然が多い。畑が広がっていて林にはタヌキも住んでいる。その中を歩くのが好きだ。しばらく歩くと本屋がある。ちょっとよって雑誌を立ち読みしていると、気に入るものがいくつか出てくる。散歩しに外に出てきただけなのでお金をもっていない。そのことに後悔しながら家に帰り、次からはお金を持って散歩することにしようと決めたのだ。それ以来散歩の際、何か気に入るものがあると「欲しい!買いたい!」という衝動にかられることがしばしば起こった。衝動買い。買い物目的で出たわけではないのにどうしていろんなものを買ってしまうのだろう。雑誌だったり、洋服だったり、普段のショッピングでは買わないものも、散歩のときは衝動的に買ってしまう。あとで、なんでこんなものを買ったのだろうと不思議に思うこともしばしばある。一体何が私を衝動的に動かすのだろう。
これにはたぶん「ゆとり」が関係している。といってもお金にゆとりがあるわけではない。心にゆとりがあるのだ。ショッピングの時は、私はいつも予算というものを決めている。だから吟味する。何を買うか、何が必要なのか、余計なものは買っていないかを吟味する。しかし散歩中は予算なんか決めていない。気の向くままに散歩して、気の向くままにお店に入る。何も考えていない。だから心に「ゆとり」があるのだ。だから衝動的に買いたくなってもお金のことなど気にせずに買う。気の向くままに買ってしまっているのだ。
私の衝動買いの引き金は「ゆとり」にあったが、みんながみんな「ゆとり」があるから衝動的に買い物に走れるというわけではない。衝動買いのきっかけはみなそれぞれである。ストレスがたまっている、気分が上がっている、お買い物中毒である、などなど。あなたを衝動的に動かすものはなんだろうか。
3 母親になること
同い年の友達が子どもを産んだ。その友達は、中学、高校と一緒だったのだけど、中退してしまったので疎遠になっていた。しかしこの前、偶然にもその友達に再会した。彼女は結婚していて、お腹に赤ちゃんもいるらしい。私は彼女に子どもができていたことに驚いた。そして心配もした。彼女とは中学生のときに友達になったのだが、すごく天然な性格の子である。私よりも背が低くてかわいらしい子なのだけど、いつもぼけっとしていてしっかりしているタイプではまったくない。そんな彼女が母親になるのかと思うと、少し不安になってきた。
子どもが生まれたという報告を受けたので、彼女に会いにいった。相変わらず天然オーラを出していてこの子が本当に母親になったのか信じられない。母親としてちゃんとやっていけるのかなぁと思いながらもお宅にお邪魔させてもらい、赤ちゃんと会わせてもらった。とてもかわいらしい女の子で、元気に泣いている。ミルクを飲ませようとしたのだが、なかなか飲まない。友達は無理矢理飲ませて泣き止ませようとしていた。赤ちゃんがあまりにも小さすぎて弱い生き物という感じなので、そんな無理矢理飲ませて大丈夫なのだろうかとハラハラした。母親になるとこんな大胆に赤ちゃんに接することができるのだ。しばらくして赤ちゃんが泣き止んだので、だっこさせてもらったり、写真を撮ったりして遊んでいた。手も足も何もかも小さいので感動した。言葉をしゃべれないので何を考えているのかわからない。私もいつか母親になるのだろうかと考えたら自信がなくなってきた。しばらく遊んでいると再び赤ちゃんが泣き出した。しかし私はなんで泣いているのかも、泣き止ませ方もわからず戸惑っているだけだった。絶対母親になんかなれないなとそのとき思っていると、友達が来て赤ちゃんをだっこしてあやし始めた。おむつを替えたりミルクを飲ませたりしている内に、赤ちゃんは泣き止み眠ってしまった。あんなにぼけっとしていた友達が立派な母親になっている。“母親”という存在のすごさを感じた。
直感的育児というものがあり、子どもに対して発達をうながすような働きかけを母親は半意識的にとるのだという。たとえば、母親が赤ちゃんに語りかける時の声は、自然に赤ちゃんが関心を向ける音程と抑揚になるらしい。私の友達も母親になったことにより、こういったことが自然にできるようになったのだろう。子どもを産むことにより、人は自然と母親になれるのだ。私もいつか子どもを産んだら、母親としての意識が目覚めるのだろうか。
4 タトゥー
私は去年の夏に初めてタトゥーを入れた。14歳のころからタトゥーを入れようと決めていたので、念願を達成できて嬉しい。親も友達も、前から私がタトゥーを入れたがっていることを知っていたので、反対はしなかった。理解のある人たちに囲まれて幸せである。横浜のスタジオで入れたのだが、私は、かつてないくらい緊張した。決心はしていたものの怖かった。痛がりということもあるけど、彫り師さんという存在が安全なものかもわからなかったので不安だったのだ。勇気を持ってスタジオに入ると、頭や首にまでタトゥーの入った彫り師さんがいて「あ、この人やばい人だ」と瞬時に感じた。私は生きて帰れるのだろうか不安になったが、お話ししてみると気さくで面白い人で、独断と偏見はよくないのだということを学んだ。タトゥーを入れる時はものすごく痛かったけど、やっと入れることができて大満足である。
タトゥーを入れてからの周りの反応は賛否両論だった。タトゥーを入れることに賛成していた友達も、いざ私がいれると軽蔑するようになった。「タトゥーを入れる人は低俗だ」ということを言われたが、私は自分がけなされてもあまり気にならないので知らんぷりすることができた。友達がそんなことを言ってくるのは悲しかったが、考えは人それぞれなので何も言い返せない。しかし言われて一番嫌なことが私にもある。それは「後悔してるでしょ?」という言葉である。一時の感情で入れたわけではないので、私はまったく後悔していない。タトゥーを入れる前は、入れてないということに後悔していたぐらいだ。タトゥーにはみんなそれぞれ思いや信念や決心が込められているので、そんな簡単に「後悔している」と決めつけてほしくない。後悔している人もいるのかもしれないけど、私はしない。
私のタトゥーのど真ん中にはホクロがある。狙って入れたわけではないのだけど、ホクロが入り込んでしまったのだ。最初は「なんでこんなところにホクロがあるんだよー」と思ったが、今となっては愛着がわいて、ホクロも含めてタトゥーが好きである。タトゥーを入れたことにより、自分の好きな部分がまたひとつ増えた。また自分の好きな部分を増やしにいきたい。
5 子どものダンス
アンパンマンミュージアムでは絶えずアンパンマンの曲が流れている。アンパンマンマーチが流れると、踊りだす子どもがたまにいる。しかしその「踊り」というのがなんとも面白い。アンパンマンマーチにはちゃんとした振り付けがあって、スタッフさんはこの振りを覚えていて踊れる。振りを知っている子どもも何人かいて踊っている。しかし子どもたちは振りつけがわかっているから踊るのではない。アンパンマンミュージアムという場所に来て興奮しているのだ。だから彼らのダンスは喜びの表現なのである。かれらの中にはもちろん振り付けを知らない子もいる。でも嬉しそうに踊っている。
2才と1才の姉妹が踊っていた。お姉ちゃんの方は、スタッフさんに振り付けを教わりながら楽しそうに踊っている。妹の方はまだ歩きはじめたばかりという感じで、たどたどしいダンスをしている。しかし彼女たちの体力は底知れない。アンパンマンで流れている曲はだいたい5、6曲のメドレーで一曲5分ぐらいだ。だから1メドレー30分ということになる。彼女らはそれを2巡も3巡も繰り返し踊っているのだ。私やスタッフさんはさすがに疲れてきた。子どもたちだけはまだまだ疲れていない。大人が踊るのと、子どもが踊るのでは全然違うのだ。しかしそれは体力の違いだけではない。子どもたちにとって、この場所でアンパンマンマーチを踊ることは、「喜びを表すこと」なのである。私やスタッフさんは子どもが楽しく過ごせる環境を提供するために振り付けを覚え、踊っているだけである。しかし子どもたちが踊っているのはこの場所が楽しいからなのだ。だから振り付けなんか覚えなくても何時間でも踊れる。
大人になってから、感情の表し方が小さくなった気がする。言葉というものを覚えたからだろうか。人前で、大声で泣くなんてこともないし、嬉しいからと言っていきなり踊りだしたりしない。しかし幼児は大人みたいに言葉を巧みに操れない。だから精一杯泣いたり、体で大きく表すのだろう。彼らのダンスからは、楽しみや喜び、興奮といったものが伝わってくる。彼らにとっての言葉はダンスなのかもしれない。
6 儚いおもちゃ ふうせん
小さい頃からふうせんが好きだった。ふうせんをタダでもらえるとすごく嬉しかったし、しぼんで浮かばなくなったら自分でふくらませていつまでも遊んでいた。売り物のふうせんはどうしても買ってもらえなかったので、泣いてお母さんにねだった覚えがある。結局買ってもらえなかったけど。ふうせんぐらい買ってくれればいいのにと思いながらしぶしぶ諦めた。なんでふうせんが好きなのかと言われると、浮いているというところが面白いからなのだと思う。浮いているおもちゃなんてふうせんぐらいしかない。ふわふわしていて捕まえたくなるのだ。飛んでいってしまうかもしれないし、われてしまうかもしれない。それでもふうせんが欲しかった。
ふうせんが好きという理由で、アンパンマンミュージアムのふうせん屋さんでバイトを始めた。そこではアンパンマンのふうせんを1個1,000円で売っている。結構いい値段なので、親はふうせんを買うことをしぶる。私が親だったら絶対に買ってあげられないだろう。昔ふうせんを買ってくれなかった母親の気持ちがわかった。それでも子どもたちはみんなふうせんが欲しくて親にねだる。親たちはなんとかして子どもの気をふうせんからそらそうとする。「ボールとかぬいぐるみ買ってあげるから」といってふうせんを諦めさせる。ボールはいいのにふうせんはだめなのだ。なんで大人はふうせんを欲しがらないのだろうか。
私もふうせんに対する見方が大人になってから変わった。ふうせんを好きな気持ちは変わらないけど、ふうせんを子どもに買ってあげられるかと言えばそうでもない。アンパンマンのふうせんが高いという理由もあるが、一番の理由はすぐ遊べなくなってしまうからだ。ふうせんなんて2、3日の命である。どうせならもっと長く使えるものを買いたい。子どもは物の寿命を考えることはない。物にも寿命があるのだということを意識するようになって人は大人になるのだ。
ふうせん屋さんの仕事をしていると、昔の自分に似た子どもに会う。なんとかしてこの子にふうせんを与えてあげたいが、私にはどうすることもできない。儚い命であるふうせんを、親に無理矢理買わせるわけにはいかない。ふうせん屋さんは「夢を売る仕事」だと言うが、夢とは儚いものなのである。
7 周りに流される
「人に流されないように」という言葉をよく聞く。周りの人に流されて、自分の意見や考えを見失わない。他人に合わせてしまっては個性が埋もれてしまう。私は中学生ぐらいからこのような言葉を聞くようになった。この年頃は、周りの人を気にしすぎて、自分をそれに合わせてしまう。一人だけ違うと浮いてしまうので、みんなと同じように行動する、ということが多い。昔はこんなこと気にしなかったのになぁと思うほど、周りを気にしてしまうのだ。周りを気にするようになったのはいつからだろう。いつから人に流されてしまうようになったのだろう。
私はふうせん屋さんで働いているのだが、ここではアンパンマン、メロンパンナちゃん、バイキンマン、ドキンちゃんなどのふうせんを売っている。それぞれの売れ行きを見るとおもしろいことがわかる。いつも売れていないメロンパンナちゃんがすごい売れる日があったり、バイキンマンばかりが人気の日がある。ふうせん自体がまったく売れない日もある。一人の子がふうせんを持っていると、他の子もそれを見て欲しくなる。逆に誰もふうせんを持っていないと、誰もふうせんを欲しがらない。メロンパンナちゃんのふうせんを持っている子がいると、自分もメロンパンナちゃんが欲しくなる。お兄ちゃんがバイキンマンを買うと、弟もバイキンマンを買う。このように幼児も周りの人が持っているものを欲しくなるのである。そして親の意見に流される子どもも多い。親と子どもの意見が食い違ったとき、親は子どもを説得する。「バイキンマンのほうがかわいいよ?アンパンマンでいいの?バイキンマンかわいいんだけどなぁ。」などと言って、子どもを説得する。そうすると子どもはだいたい親の意見に変わる。
大人も子どもも、他人のしていること、持っているものに影響を受けるのだ。周りが同じものを持っていると、自分も欲しくなる。周りが何かしていると、自分も同じことをする。自分の意見が周りと違うと、自分の意見を変えて周りに合わせてしまう。「人に流されないように」といわれるが、私たちは小さい頃から、周りの影響を受け流されながら生きてきたのだ。 しかし子どもと大人では少し違うところがある。大人が周りに流されるのは、自分の判断に自信のない時が多い。みんながこっちを選んでいるから私もこっちにしよう。みんなが持っているなら私も同じものを持たなくてはいけない。このように選択を他人に任せてしまっているのだ。子どもの場合は、自信がないから判断を委ねるのではなく、周りの人がもっているものを欲しくなってしまうのだ。このように大人と子どもでは「流される」理由がちがうのだ。私たちは大人になるにつれて、周りが「気になる」から周りを「気にする」へ変化するのである。
8 アニミズム ぬいぐるみの声
小さい頃、たくさんのぬいぐるみを持っていた。誕生日やクリスマスに買ってもらうプレゼントと言えばぬいぐるみだった。うさぎのぬいぐるみやくまのぬいぐるみ、恐竜のぬいぐるみなどいろいろあった。それら一人一人に名前をつけてどんな性格なのかも決めていた。小さい頃はぬいぐるみの気持ちがわかったのだ。彼らが生きていると思っていたし、寝ている間に動いているのではないかと信じていた。寝る前には布団(ただの布切れだが)をかけてあげた。妹とよくぬいぐるみで遊んでいたのだが、お互いどのぬいぐるみがどのような性格かを把握しているので、本当に生きている友達かのように遊んでいた。このように、生き物以外にも生命が宿っているという考えを「アニミズム」という。子どものころはアニミズム期というのがあり、絵を描く時、生き物ではないものにも顔を描くことがある。
ところが、年齢が上がってくるにつれてだんだんと、ぬいぐるみの声が聞こえなくなってきた。と言うよりも、聞こうとしなくなったのだ。私たちの友達はただの飾りとして部屋に置かれるようになった。アニミズムの考えが完璧になくなったわけではなく、絵を描くときに、太陽やお花などに顔を描くこともある。しかし生き物ではないものにも生命が宿っているという考えは、大人になると「ありえない」と考えられる。ぬいぐるみの声が聞こえるなんて言ったら、「不思議ちゃん」と思われてしまうのだ。でも子どものときに、ぬいぐるみの声が聞こえたのは事実である。なぜ大人になると聞こえなくなってしまうのだろうか。
私がアンパンマンのふうせん屋さんで仕事をしていると、ある2人の女の子がやってきた。一人はものすごい勢いでメロンパンナちゃんのふうせんをたたいている。するともうひとりの女の子が私にこう言った。「あのね、メロンパンナちゃんがね、いたいいたいって言ってたよ。」私はこの言葉に驚いた。自分にはまったく聞こえなかったメロンパンナちゃんの声がこの子には聞こえるのだ。嘘をついているわけではない。本当に聞こえているのだと思う。なぜこの子には聞こえて、私には聞こえないのか。それはこれらがもう私の友達ではないからである。子どもたちは、ぬいぐるみやふうせんに友達感覚で接しているのではないだろうか。私も小さい時はそうだった。しかし大人になると、「ぬいぐるみがお友達」の世界では暮らさない。人間ばかりの社会で暮らす。だから私たち大人には、これらの声が聞こえなくなってしまったのだろう。子どもが大人になるにつれ交友関係や社会のあり方が変わるとき、ぬいぐるみの声はもう私たちには届かなくなってしまうのだ。
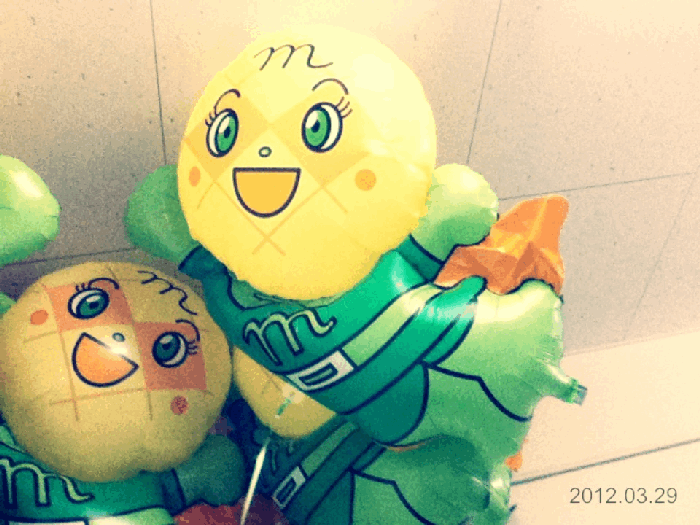
9 迷子
子どもはすぐ迷子になる。勝手に迷子になる。母親が近くにいるのに迷子になることもある。なんで彼らは迷子になるのだろうか。
昔、私はスーパーの二階にあるドラッグストアでバイトをしていた。ドラッグストアの隣にはキッズ用の服屋さんがあったので子どもが多かった。ある日、私が仕事をしていると3才ぐらいの少年と目が合った。少年は何やらものすごく泣いていた。これは迷子かな・・・と思いつつ、「どうしたの?」と恐る恐る少年に声をかけた。そしたら彼は「ままぁー!」と泣き叫びながら私の足にしがみついてきた。私は足などつかまれたことがないのですごく驚いたが、とりあえずこの子の母親を探さなくてはと思い、彼にどこから来たのか聞いてみた。しかし彼は泣きつづけていて何も答えてくれない。隣の服屋さんから来たのだろうと思い、足にしがみついている彼を引きずりながらも探しまわった。なかなか見つからない。うちの店でも探してみた。アナウンスまでかけたのに見つからない。結局、この子のお母さんは1階のスーパーで買い物をしていて、子どもが勝手に2階にあがってきてしまったらしい。やはり子どもは勝手に迷子になる生き物なのだ。
しかしふと、私が迷子になって時のことを思い出した。小さい頃大きめのスーパーに家族で車に乗って行った。買い物しているお母さんの隣を歩いているつもりだったのだが、気がつくと誰もいない。少しドキドキしながら「だいじょうぶ、だいじょうぶ」と言い聞かせて、お母さんを探した。しかしどこにもいない。こんな家から遠くて、広いスーパーで迷子になったらもう一生お家には帰れないような気がしてきて、途方に暮れた。だんだん涙がでてきた。なんで「お母さんはいなくなってしまったんだろう。ずっとそばにいたのに・・・。」と思った。あのとき私は母親が勝手にいなくなったと考えていたのだ。
さて、勝手にいなくなるのは子どもの方なのか親の方なのか。おそらくどっちもなのだろう。自分の興味のある方へ行き、お互い離れてしまったことに気づかない。その結果迷子になる。ただ、親は自分が来た道、帰り方をわかっているから不安になったり、迷ったりしない。子どもは、自分だけでは帰り方もわからない。だから迷子になるのはいつも子どもの方なのだ。
10 双子でいること
私には双子の妹がいる。生まれる前、胎内にいる時から一緒で、ずっと二人で同じように育ってきた。幼稚園から大学まで一緒なので、友達もほとんど共通だ。同じ環境で生きてきたので、相手の考え方もよく知っているし、お互い誰よりもわかり合えるパートナーである。とても仲良しな双子なのだが、たまに双子で一緒にいることをよく思わない人もいる。「いつまでも二人でいても世界は広まらないし、成長しない」と言われることがある。確かに二人でいつも一緒にいて、一人だと何もできないと思われるかもしれない。友達同士で群れていて、トイレに行くときも誰かと一緒でなきゃだめという“一人では行動できないタイプ”の人を見ると、私も良い印象は持たない。しかし双子の場合は違うのだ。
双子は仲良しの友達とは違う。かといって姉と妹という関係とも違う。もう一人の自分というような存在であり、距離感というのが人とは違うのだ。いつも二人でいるといっても甘え合っているわけではない。それぞれの世界を持っているし、一人で行動できないことはない。しかし今まで一緒にいたからあえて離れようなどということは、私たちは考えない。双子でいるということはみんなが思っているような馴れ合いの関係ではないのだ。
大学受験のとき、受験は自分との孤独の戦いだと言われ、みんな必死で頑張ってきた。しかし私には双子の妹がいたので、孤独ではなかった。勉強は一人でやるものだけど、同じように頑張っている人がいつもそばにいるということは支えになる。二人で合格し、二人で同じ大学に行くことになったが、先生は「いい加減離れなさい」と言って止めた。お互いに依存しているように見えるのだろう。依存しいては、これから先一人で生きていけないと心配してくれていたのだ。
双子でいるということは、お互いをよく知っていて支えてくれる人がいるということである。それは依存しているということではない。比べられるということも多いので、負けないようにお互いを蹴落とし合いながら生きているのだ。よいパートナーであり、よいライバルである存在がいつも一緒にいるというのはすばらしいことである。これから先一人でやっていけるのかという人もいるが、その心配はない。私たち双子はたとえ別々の道を歩み、お互い違う社会に出て、違う生活をしようとも、家族であるのでこれからも疎遠になることはない。双子でいることは決してだめなことではなく、むしろお互いプラスに成長できることなのだ。
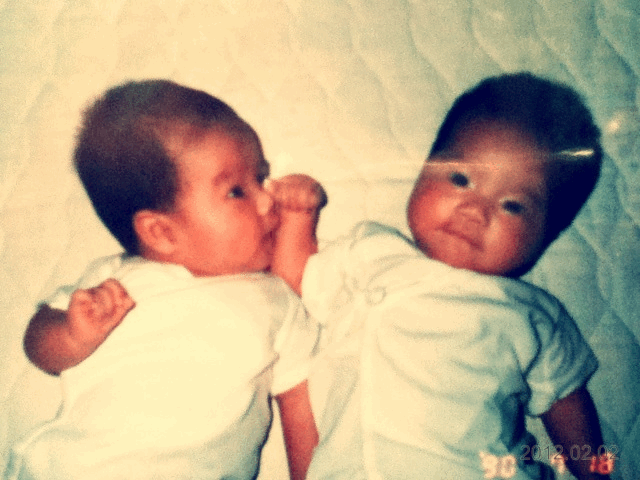
11 チャームポイント
小学生のとき、友達と”プロフィール帳”というものを書いて交換した。プロフィール帳とは自分の名前や、性格、趣味、好きなものなどを書いたり、心理テストに答えたりする項目のある紙である。これを友達と交換するのが当時流行っていた。プロフィール帳は文房具屋さんなどによく売られており、うさぎなどの動物の絵が描かれているものや、キャラクターものなど様々な種類がある。内容や項目は多少の違いはあるが、ほぼ同じである。項目の中で、どのプロフィール帳にも絶対あるというものがいくつかある。そのひとつが「自分のチャームポイントはどこ?」という質問だ。
チャームポイントとは自分の顔、体の中で一番魅力的な部分のことである。私はこの質問に答える時、いつも悩む。自分の魅力など自分ではわからないし、ましてや顔や体のどこかに突出した魅力がある部分などないと思う。みんなは一体自分のどこをチャームポイントだと感じているのだろうか。小学生の友達に書いてもらったプロフィール帳には、この質問に対しだいたいの人が「目」という答えを書いていた。だから私もみんなのまねをして「目」と答えていた。しかし正直私の目はそこまで魅力的ではない。この時は、みんなが書いているので、私の中でチャームポイントは「目」というのが無難な答えとなった。
この前、何人かの友達にこの質問に答えてもらったが、「ここがあなたのチャームポイントなの・・・?」という疑問が浮かぶ。もっと他にもかわいいところがあるのではないか、ここは特にかわいくないだろうと思うことが多い。目が大きくてかわいい子にチャームポイントを聞いても、「口」などと言ってあまり目立たない部分を答える。みんなは何を基準にチャームポイントを選んでいるのだろうか。
おそらくチャームポイントとは客観的にみて魅力的なところではなく、自分にとって魅力的な部分なのだろう。他人にとってはそうでなくても、自分の身体の中で一番好きな部分が一番魅力的なのだ。なので「チャームポイントはどこ?」という質問は、「自分の身体の中で一番好きなところはどこ?」という意味なのである。自分のことをあまり好きではない人もどこかしら好きな部分はあるはずだ。この質問に答えるのが苦手だったが、これは自分の好きな部分を探すきっかけとなるものなのだと考えるといい質問に思える。あなたのチャームポイントはどこだろうか?
12 人気ヒーローの着ぐるみ
子どもはアンパンマンが好きだ。アンパンマンミュージアムでは、たくさんのおもちゃやぬいぐるみ、ふうせんなどを売っていて、子どもたちはそれを買ってもらおうと親にねだる。買ってもらうと笑ってはしゃぎだすし、買ってもらえないと地面を転がりながら泣き叫ぶ。アニメを見たり、アンパンマンの曲が流れると踊りだす子どももたくさんいる。そして色んなところから「アンパンマーン」と子どもがアンパンマンを呼ぶ声が聞こえる。アンパンマンの人気はすごいのだ。
彼らがアンパンマンに実際会ったらどれだけ喜ぶのだろうか。ミュージアムでは、アンパンマンの着ぐるみを着た人がパトロールに来る。アンパンマンだけではなくメロンパンナちゃんやバイキンマンが来ることもある。子どもたちに楽しんでもらうため、スタッフさんが着ぐるみを着てみんなと戯れるのだ。アンパンマンの姿を見てやはり子どもたちは多いに喜ぶ。子どもだけではなく、親も大喜びで、アンパンマンと握手している我が子を写真に撮ろうと必死である。しかしみんながみんな喜んでいるわけではない。着ぐるみを見るなり、大泣きする子どももたくさんいるのだ。なぜ大好きなアンパンマンが会いにきてくれたのに泣くのだろうか。おもちゃやぬいぐるみは欲しがるのに、なぜ実際に動いているアンパンマンを怖がるのだろうか。
アンパンマンの着ぐるみの中には大人が入っている。子どもたちよりもはるかに大きい。遠くから眺めている分にはいいが、近くに来ると子ども目線からでは相当大きく見えるだろう。子どもから見るアンパンマンは下からのアングルなので、顔に陰影ができて少し怖い。この大きさが原因のひとつなのではないだろうか。子どもが想像していたよりもアンパンマンの体が大きい。お母さんよりも大きい。このことが子どもに恐怖を与えている。しかし着ぐるみの中に入るのは大人しかいないのだ。
アンパンマンやバイキンマン、メロンパンナちゃんの着ぐるみの中にはお兄さんやお姉さんが入っている。彼らはただ中に入って動いているわけではなく、そのキャラクターに合った動きを訓練して身につけて入っているのである。ちょっとした仕草もキャラクターによって全部決まっているのだ。ここまで徹底しているのは、よりリアルなアンパンマンたちに子どもたちを見せたいと思うからだろう。
アンパンマンの着ぐるみが、子どもが泣いて怖がるほど大きいのは仕方がない。なぜなら、子どもたちにアンパンマンに会わせたいと願う大人が中に入っているからなのだ。このことを子どもたちが理解できるようになるのはもう少し大きくなってからだろう。そして大人になった彼らがまた着ぐるみの中に入り子どもたちを喜ばせたり怖がらせたりするのだ。
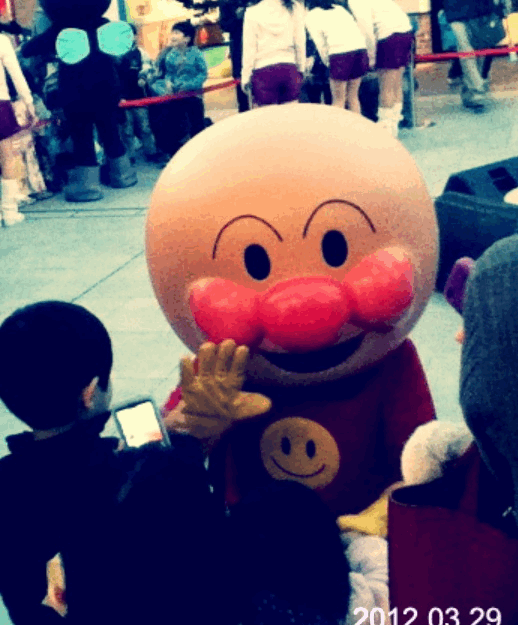
13 子どもらしい格好と大人っぽい格好
子どもらしい格好とはどんな格好だろうか。男の子だったら、蝶ネクタイや半ズボン。女の子だったら、リボンやフリル。子どもらしく外で元気に走り回れるような服装のことだろうか。私が考える子どもらしい格好とは、子どものうちにしか似合わない服であり、明るい色や柄の服や、大人になってからは恥ずかしくて着られないようなものである。私が子どものころもそういったものを着せてもらった。しかし年齢が上がるにつれて、大人っぽい格好を好むようになった。シンプルな格好や、雑誌に載っているような格好をするようになった。昔みたいなピンクのフリフリした格好なんてできないし、あれは子ども時代限定の格好だなぁと思う。しかし最近の子どもを見ていると、子どもらしい格好に変化が起きているようである。
シックな色のコート。シンプルなワンピース。スキニーをブーツイン。このような大人のような服装をしている子どもをたくさん見かける。ブランドものの服を着ている子も多く、親たちの子どもに対するおしゃれの意識が高まっているのだろう。それにしても、私の子どもの時とは違いすぎる。今の私がしている格好と同じような格好をした子がたくさんいて、彼らはまるで小さな大人みたいだ。子どもには子どもらしい格好をさせた方がいいのにと思うが、その“子どもらしい格好”というものの基準自体が変化しているのだろう。
そして大人っぽい格好というのも変わってきているように思える。子どものように大きいリボンをつけた服装や、フリフリのワンピース、派手な色の組み合わせ、といった格好をする大人の人もたくさんいる。大人になったらこんな格好恥ずかしいと思えるものも、普通に着ている人が多い。こうやってみていくと、大人も子どもも基準にとらわれず、それぞれが好むスタイルをしているようだ。子どもの場合は親が買うものを着せられているだけだろうけど、親の好みがよくでている。子どもだからこういう格好をした方がいいとか、大人だからこういう格好はやめた方がいいという考えはない。従来の子どもらしさや大人らしさから新しい“自分らしさ”へと変化しているようだ。今や服装は、大人にとっても子どもにとっても個性を表すものとなっているのだ。
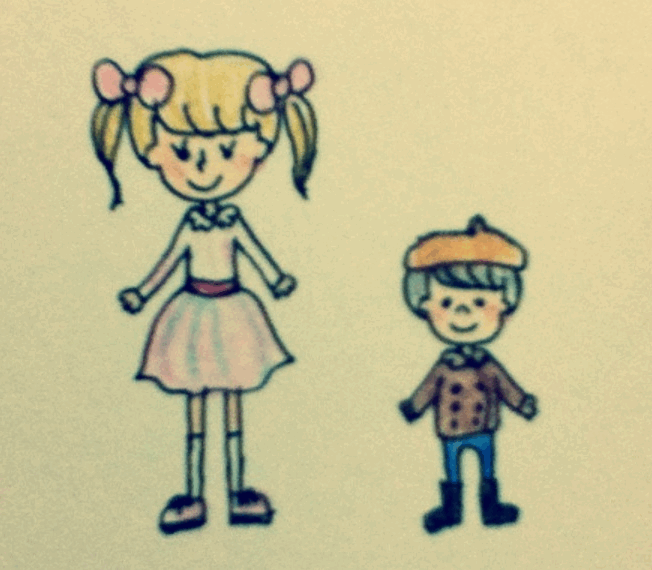
14 ペットと子ども
公園を歩いていると、犬を散歩させている人によく出会う。どの犬もおしゃれな格好をしている。服を着ていたり、首輪がおしゃれだったり、すごくかわいがられていることがわかる。抜け毛の時期は服を着せるとよいということを聞くが、それにしてもおしゃれな服である。最近では、ペット服専門のお店まであり、ペットのおしゃれに対する意識が高いように思われる。ペットスパなどもあり、私たち人間よりいい暮らしをしているのではないだろうか。飼い主たちはむしろペットというよりは、自分の子どものようにかわいがっている。
“親ばか”という言葉があるが、それは自分の子どもがかわいくて一番だと思っている人に対して使われる言葉である。しかしそれをペットの飼い主に対して使うことがたびたびある。私の友達と会話しているとよくペット自慢で盛り上がる。たくさんの写真を見せながら、私の飼っている犬がかわいいなどと言って自分のペットが一番だと主張する。私はペットを飼っていないので何とも言えないが、きっと飼い主の立場から見ると自分のペットが一番かわいいと思えるのだろう。その姿は、まさに“親ばか”そのものである。ここには正当な評価など存在しない。我が子が一番かわいすぎて他のものが目に入らないのだ。
ペットの我が子化が強まる一方で、親の子どもに対する接し方にもある現象が見られる。最近子どもにリードをつける親を多く見かける。リードと言ってもペットのように首につけるのではなく、リードのついたリュックを子どもに背負わせてそれを親が引っ張るのだ。確かにその方が迷子にならなくていいかもしれない。しかしこれでは明らかにペット扱いをしているようにしか見えない。ペットを我が子のようにかわいがる人もいれば、我が子をペットのように接する親もいるのだ。
ペットも子どもも親(飼い主)にとっては大切な存在である。自分たちが育てなきゃいけない、かわいがらなくてはいけないという義務を背負っている。リードをつけたり、おしゃれをさせたり、今ではGPS機能のついた携帯を持たせる人もいる。これから先、ペットの我が子化は進むだろう。その一方で子どものペット化はどうなっていくのだろうか。
15 子どもに特別な名前をつける
私が小学生のころ、クラスにめずらしい名前の子が一人や二人いた。私は自分の名前が「さき」という平凡でクラスに一人はいるような名前なので、めずらしい名前の子がうらやましかった。名前がめずらしいと“特別”という感じがしてかっこよかった。私の友達に「かりん」ちゃんという名前の女の子がいたのだけど、名前も見た目もかわいらしくて憧れていた。自分に「かりん」というかわいらしい名前が似合うかどうかは置いといて、私もこんな名前がよかったなぁと思っていた。漫画を読んでいても主人公はみんなめずらしい名前だし、やはり名前が他の人とは違うと、それだけで個性的に見えるのだ。「自分の子どもにはめずらしい名前をつけよう」とこの時誓った。
しかし最近の子どもの名前をみるとどうだろう。めずらしい名前の子ばかりだ。みんながみんなめずらしくて、ありきたりだと思われた名前の方が逆にめずらしく思える。親はみんな自分の子が特別だから、特別な名前をその子に与えたのだろう。特別な意味や思いを持たせた名前は確かに素敵だし、その子にとっても嬉しいことだろう。でも当て字の子が多すぎて、なんて読むのかわからない子が多い。学校の先生も読むのが一苦労だろう。漫画の登場人物の名前を我が子につける親もいる。「光宙」と書いて「ぴかちゅう」と読む子さえいる。ここまでくると、やりすぎと思わざるを得ない。子どものうちは似合うかもしれないが、大人になった時もこの名前でやっていけるのか心配になる。名前が原因でいじめられたりしないのだろうか。そもそも人間にとって名前とは何なのだろうか。
名前はその子にとって一生の所有物である。自分はこの名前で一生過ごしていかなくてはならない。いくら親の希望を名前につめこんだって、その子がいずれ社会に出るということを念頭に置かなくてはならない。特別な名前をつけたいからといって、めずらしい名前というのは確かにかっこいいが、名前というのはその子を表す最も身近な言葉であり、その子自身なのだ。どんな名前を与えられたとしても、その子はそれを持って成長し、社会の一員として生きる。そのことを考えると、名前というのは単なる呼び名ではない。その子の人生において一生離れることのない大切なものなのだ。私たちは、名前が“特別“であることの意味をもう一度見直すべきなのである。