相田みつを美術館 | ||
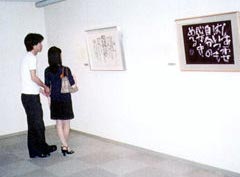 空虚な毎日に嫌悪感を抱いていたある日のこと、生協で一冊の本を手に取った。
「ともかく具体的に動いてごらん 具体的に動けば 具体的な答えが出るから」……ページをめくるたびに、弱った心に響き、染み込んでくる「ことば」の数々。
その本に挿んであった栞に書かれていたのは「相田みつを美術館」という文字と地図。はじめて銀座・数寄屋橋へと足を伸ばした。
書家であり詩人でもある相田みつをの作品が、ゆったりとした空間に展示されている。作品との調和のとれた照明や静かで落ち着いた雰囲気の内装は、ここが銀座であることを忘れさせるほどである。
「書」という形で多くが表現されている相田みつをの作品の印刷物ではわからなかったことが、ここでは発見できる。実際の作品の大きさや、本にはうつらない作品の端にあるごく小さな墨のシミ。相田みつをが実際に作品を書き上げる姿を想像させる、墨の濃淡や筆づかい等。作品の細部に触れることで、作品の迫力、躍動感をよりいっそう感じることができる。
作品には、すべて落款が押されている。これは、相田みつを自身が世に出しても良い作品であると認めた証しであり、納得のいかないものには押されることなく、すべてが処分されたという。一つの作品を書き上げるために、何十枚という世に出てこないものが存在していたのである。額に入れるトリミング作業も、相田みつを自身が一つの作品につき2日間を費やしていたという。美術館の収蔵品数は約350点というから、この作業だけでもかなりの日数を費やしたと想像できる。このことを知ってから作品を見ると、今まで以上にその作品に込められた想いを強く感じることが出来るように思う。
老若男女を問わず年間約30万もの人が来館しているのは、ここにある作品が「ことば」であるからだろう。それは相田みつを独自の言い回しで、しかもわかりやすい言葉で語られている。やわらかく、あたたかい「ことば」は、今ここに生きていること、人のありがたみ、自分について考えることを諭してくれる。「お説教をするのではなく、自分で考えてごらんなさい、というのが相田みつをのとるスタンスであり、これが魅力のひとつです」と案内いただいた総務部次長の成田さんは語ってくれた。
はじめて訪れた人の大部分は、知人からの紹介で来館するという。ここが友人を連れてきたくなるようなところであり、リピーターが多い美術館でもあることは、作品だけでなく、空間自体にも魅力があることを証明していると思う。
訪れるたびに、作品への印象やその言葉に対する解釈が変わるのも面白い。成田さんは「作品がひとつの鏡となって、それぞれが自分を見つめられるようにしてくれる。見る人の状況や状態によって、同じ作品からでも色々なことを感じ取ることができる」と語る。
相田みつをにはもう会うことができない。しかし、作品には会える。こころを育てる栄養を「ことば」から受け取れるのである。
|