情報数理の素養はあらゆる科学の基礎
友だちや家族のような存在のロボット、調べものといえばインターネットによる情報検索、キャッシュレスになりつつある経済活動。一見関係がなさそうなこれらの分野と時代変化の背景に、情報数理の力はどのような影響を与えているのでしょうか。今回は、経済学説史や経済思想史が専門の中野聡子副学長が進行役となり、遠隔育児支援ロボットの研究を進める電気通信大学人工知能先端研究センターの阿部香澄特任助教と、ウィキペディアの構造を分析・研究する大阪大学数理・データ科学教育研究センターの小串典子特任助教に、情報数理分野の重要性や情報数理学部への期待について、お話を伺いました。さらに女性の皆さんから見た「研究職」の魅力まで、多岐にわたり語り合ってもらいました。
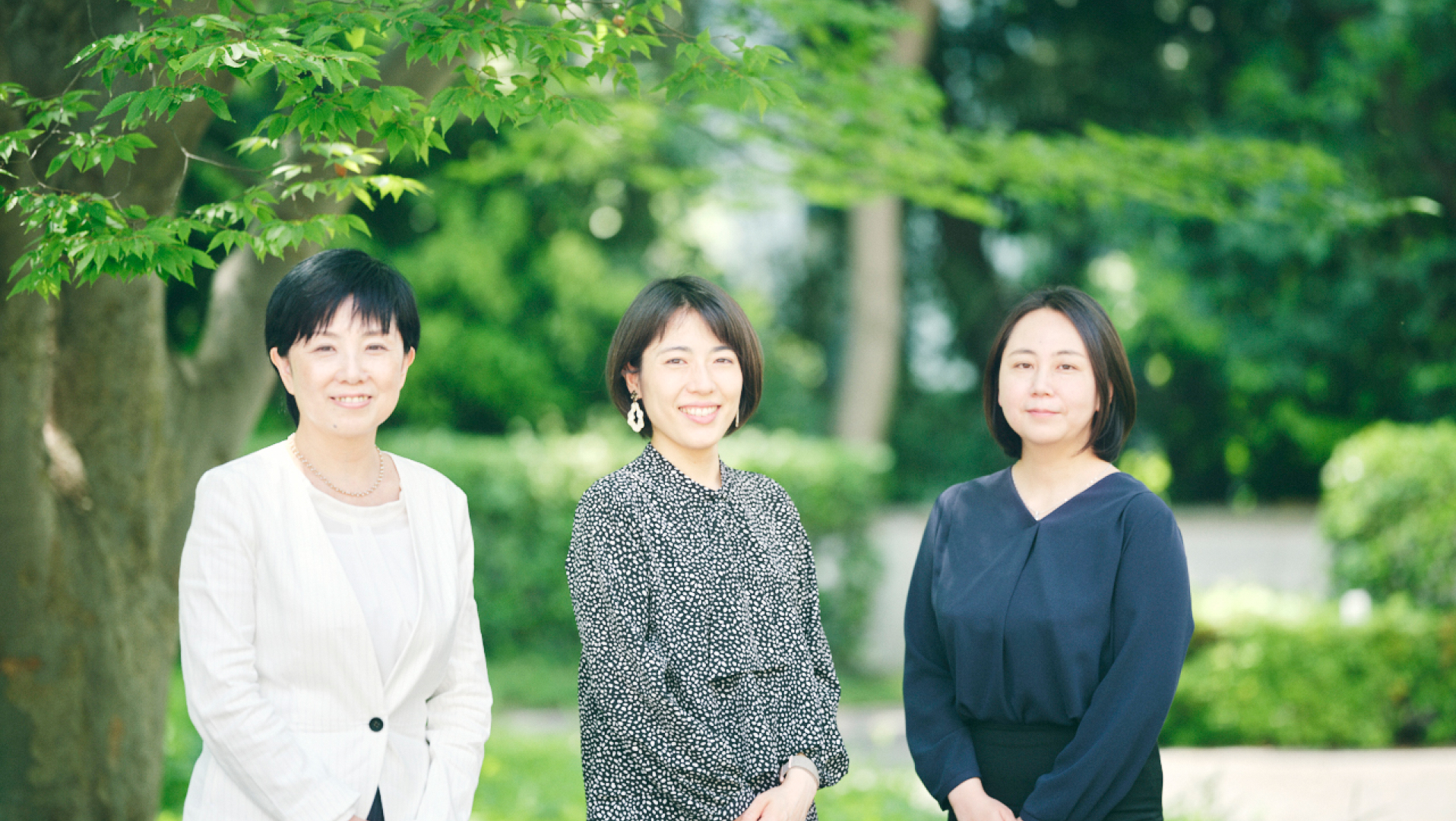

阿部 香澄 Kasumi Abe
電気通信大学 人工知能先端研究センター 特任助教
(株)ChiCaRo 主席研究員(兼務)
(株)国際電気通信基礎技術研究所 客員研究員(兼務)
電気通信大学大学院 情報理工学研究科 知能機械工学専攻修了(博士)。2015年~2020年日本学術振興会特別研究員(電気通信大学 人工知能先端研究センター所属)および株式会社国際電気通信基礎技術研究所連携研究員のち客員研究員。2020年10月株式会社ChiCaRo主席研究員。同年11月電気通信大学 人工知能先端研究センター 特任助教。

小串 典子 Fumiko Ogushi
科学技術振興機構さきがけ専任研究員
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 特任助教(兼務)
2008年 東京大学大学院工学系研究科 物理工学専攻博士課程修了(博士(工学))。2008年から理化学研究所、お茶の水女子大学の研究員などを経て2020年大阪大学 数理 ・データ科学教育研究センター特任助教。2020年よりJSTさきがけ専任研究員。

中野 聡子 Satoko Nakano
明治学院大学 副学長
慶応義塾大学大学院博士課程 (経済学研究科) 修了、博士(経済学)。明治学院大学経済学部教授。専門分野は経済学説史、経済思想史。主要研究テーマは、ミクロ経済学の形成過程、19世紀における経済学と数理手法の結びつき、18世紀イギリス経験哲学と経済思想の関係など。現代の経済学の観点から経済思想を再検討している。
それぞれの専門分野から垣間見える、共通点
中野まずは自己紹介を兼ねて、どのような研究をされているのか、簡単に紹介していただけますか。
阿部学部生時代からずっと電気通信大学に在籍し、現在は人工知能先端研究センターの特任助教をしています。専門分野は、チャイルドロボットインタラクションや、ヒューマンロボットインタラクションなど、インタラクション(相互作用)の研究です。例えば、ロボットにどんなインタラクションが生まれたら、子どもがロボットと仲良くなれるかなどの研究を通して、人とロボットのコミュニケーションの在り方を解明しようとしています。最近では、それらの研究で得られた知見を保育や育児の現場にロボットや情報システムとして「導入」するといった応用にも力を入れており、保育・育児系の課題を解決し、ウェルビーイングを高めることに貢献したいと思っています。
小串本来の所属はJST(国立研究開発法人 科学技術振興機構)の戦略的創造研究推進事業さきがけの専任研究員で、現在は大阪大学の数理・データ科学教育研究センターの助教を兼任しています。統計物理が専門になります。統計物理というのは、ひとつひとつの要素の振る舞いと、要素がお互いに関わり合うことで成り立つシステム全体の振る舞いとの橋渡しをするような分野です。ですからこの分野は、ある意味この世のすべてが研究対象になり得ます。学生の頃は熱輸送を研究対象としていましたが、現在は、要素も相互作用もより多様で複雑な系として、ウィキペディアを研究対象にしています。
中野私はお2人と違って文系で、経済理論の歴史や経済思想史を専門にしています。ただ経済学は数学と無縁ではなく、人が情報をやり取りしながらマーケットで取引する仕組みを分析したり、実証したりする学問です。その経済学と数学が結びつくのは19世紀の中頃ですが、どのように経済学と数学が結びついてモデル分析や実証研究につながっていったのかを、私はそこに貢献した人の思想や残された史料などをもとに、図書館でコツコツ調べていくような研究をしています。しかし、昔のことを調べながらも、今後の経済学がどのような方向に進んで行くべきかには問題意識を持っています。その意味では、経済学と非常に関連の深い情報数理の研究やその成果には高い関心を持っています。

科学のベースは、数理的な見方と解析力だ
中野一方、副学長として大学行政を担う一員としては、新しい時代に人材を輩出し、かつ研究が社会に貢献できるような体制もつくっていきたいと思っており、情報数理学部の開設に向けて、情報数理の分野で先端的な研究をされている先生方のお話をお聞きするのを楽しみにしておりました。先生方の研究と、情報数理との関係をもう少し詳しくお話しいただけますか。
阿部はい。私が行っているチャイルドロボットインタラクションの研究ではロボット作りやそこに搭載するAIや情報システムを作るのに情報数理の知識が必要なのは当然です。加えて、実験で得られたデータを分析する際にも、数理や統計学の知識がものすごく重要な意味を持ってきます。どれくらいそれらを身に付けているかで、ちゃんとした解析ができるかどうか、意味のある知見につなげられるかどうかが決まるからです。
中野どのような実験をしているのですか。
阿部情報システムを実装したロボットを保育現場などに導入し、子どもと会話する実験や、一緒に遊ぶ実験などを行っています。何十人もの子どもを相手に行い、その場面を録画するのと同時に、ロボットに搭載しているセンサーで子どもとの距離や視線を向けた頻度などを計測し、数値データとして取り出して録画データと合わせて解析しています。
小串私は統計物理が専門ですから、数理はツールだと認識しています。阿部先生のお話にもあったように、科学ではまず研究対象を決め、データを取得し、そのデータを客観的に分析して対象の性質を議論するというのがスタンダードなアプローチです。ですから、科学に携わる以上、数理的な解析力は常に基本になるものだと思っています。
中野熱輸送を扱うような統計物理とウィキペディアの研究は、どのようにつながっているのですか。
小串ポイントは、多くの要素が相互作用の結果1つのシステムを作っているという点です。例えば水分子1個はニュートンの運動方程式にしたがって動いていても、コップの水は液体として振る舞いますし、温度が変わると水蒸気や氷になって気体や固体としての性質を示します。多くの相互作用によって、全体が個とは質的に異なる状態を示すわけです。ウィキペディアも、自由に参加した人々が自由に記事を編集することで成り立っています。専門家ではなくいわば「烏合の衆」が書いているにもかかわらず、20年以上も続く情報の集合として、今ではある程度信頼され、随分浸透しています。しかし、何が鍵になってうまくいっているのか、どの要素が大事なのかから評価しないと、うまくいっているシステムとしてのウィキペディアの仕組みはわかりません。ですからデータを取って解析し、理論モデルを立てて議論の俎にのせることが大切で、それには数理の力が不可欠です。
中野物質の分子の運動方程式の数理モデルが、ウィキペディアを分析するときのアナロジーになっているというのは、興味深いですね。ところで、ウィキペディアが崩壊しないのは、どういう状況だからでしょうか。相互作用が安定しているからでしょうか。
小串現在はそれなりに信頼して使っている状況ですが、それを相互作用の安定といっていいかは難しいですし、誰もが自由に編集できるため、水分子のように決まった相互作用があるとわかっている訳でもありません。ただ、これまで破綻もせず拡大しつつ続いていて、なんとなく上手くいっている不思議なシステムだと思います。

「価値」や「質」など抽象的なことも、データを使うから実証が可能になる
中野文系の人間としては、システムが機能しているとか、システムの質的なものを数学のタームでどう捉えていくのかが気になります。先程のロボットの話でも、子どもとロボットの相互作用を見るとき、「これは子どもにとって悪影響だ」「いいインタラクションだ」といった質的な部分は、数学的にどう捉えているのでしょうか。
阿部確かにイメージしにくいかもしれません。例えば、子どもにはロボットが自立的に動いていると説明しておいて、実は幼稚園教諭に遠隔操作してもらった実験を過去に行ったことがあります。幼稚園教諭なら、子どもと仲良くなれるインタラクションができるだろうと考えたからです。しかし、見た目はロボットで、見慣れた先生と合致しないので、子どもは当然いつもと違う振る舞いをします。そこで、ロボットが子どもと会話をした回数、あらかじめ質問紙で回答してもらっていた子どもの性格、その場を観察していた母親の主観を数値化して、3つの関係性を解析します。するとシャイな気質の子どもには、始めからたくさん会話をしても仲良くなれず、社交性の高い子どもは、始めから会話をするほど仲良くなれるという結果が出ました。これは一例ですが、関連すると思われる要素を数値化することで、質的な議論に展開していくわけです。
小串ウィキペディアの場合は、記事と編集者のどちらにもうまく捉えきれていないですが質的な多様性があるところに面白さを感じています。例えば、大勢の人が書いた記事を重要な記事と見なすこともできますが、単に論争性やそのときの人気の高い記事だったりします。よく編集されていて、内容が充実していることを「良さ」として知りたい訳ですが、そのためにはどんな記事を書いた人なのか、どんな人が書いた記事なのか、記事と編集者の性質が互いに関わり合って決まる指標が必要になります。記事や編集者の性質といった捉えづらい特徴もうまく指標を導入できれば議論できるようになるのですが、数理の力でシステムを切り出し議論を進められるようになる点がこうした研究の面白さでもあると思います。
中野非常に面白いですね。実は経済学と数理の結びつきにも似たような話があります。熱力学や流体力学などの統計物理の数理的な構造や手法を経済学に持ち込もうと考えた初期の数理経済学者が19世紀にいました。市場の仕組みつまり価格の動きや人の行動は、人や社会の質的な問題を含んでおり、数理的に分析するには、物理学の手法を援用して今日まで進展してきた部分もあります。現代はコンピューター技術の発展や機械学習の理論など、いろいろなものが数値化されて社会にあふれるようになり、社会や人間に関わる問題は一層複雑なものとなりつつあります。そういうものをどう評価して受け止めていくべきかについては、さまざまな学問分野で問題になっていますが、まさにそうした研究を一つひとつやっていくことが我々に求められているのかなと思います。

テクノロジーと社会、文化。共存、またはよりよい相互作用の道をつくるフロンティアをめざして
中野将来的な目標についてはいかがでしょうか。
小串今取り組んでいる「さきがけ」においての研究では、ウィキペディアに集中しているのですが、次の段階として、ウィキペディアのようなシステムが持つ性質の普遍的な側面と、個別性に興味を持っています。ウィキペディアを通した比較にはなりますが、背景にある参加者の所属する文化とか社会の多様性や普遍性を議論できるようになればいいなと思っています。
中野日本語版のウィキペディアと英語版のウィキペディアでは、ずいぶん違うところがあるのは経験的に知っています。文化や社会の構造に敷衍すると、日本語版は蛸壺的なのでしょうか?
小串意外とそうでもないことがわかってきました。アニメ関係の記事が多いといった特徴はあるにせよ、英語版と同様に、様々な人が色々な記事を書いていますね。
阿部私はコミュニケーションやインタラクションが研究の柱ですが、実は私自身はコミュニケーションがやや苦手なのです。だからこそ逆に、もっと知りたいという探究心につながって今の研究をしているところがあります。こうすれば解決できるのにという問題に気づきやすいからです。育児への応用研究も同じで、良い育児環境づくりのための知見を得ることと、育児支援システムなどの社会実装をめざしています。
中野育児や福祉に携わっている人は、ロボットへの関心は高いのですか。
阿部誤解を恐れずにいえば、新分野、新技術に興味があり、ロボット導入で育児の質を高めたいと考える人と、育児や福祉はやはり人でしょうとロボットを拒む人に二分されます。ただ、実態を知らずに拒否している人もいて、例えば祖父母とのビデオチャットによる育児支援ロボットと子どもが一緒に遊んでいる映像を見せると、技術導入に肯定的になる人もいます。
中野ロボットを社会実装するとなると、倫理的な問題も大きくなると思います。本学が設置を計画している情報数理学部では、コンピュータサイエンスや情報理論、数理理論、統計学などを整備するのと同時に、情報倫理の分野にも力を入れていくつもりです。これまでの科学技術は、技術を使うことと、社会への影響を区別して考えることができました。しかし今日、AIは使わないでおくことはできない状況なのは間違いなく、一方で複雑な既存社会とAIのインタラクションをまだどう評価していいかわかりません。情報倫理は新しい教育研究分野ですから、全学で真剣に取り組めばフロンティアになれる可能性がありますし、社会的な意義も大きいと思っています。

「数学」だけではない「情報数理」という着眼。じっくり取り組む基礎教育に大きな期待
中野情報数理に関わる研究者として、本学が設置する情報数理学部にはどのようなことを期待されますか。
小串今はもうAIや機械学習は本当に身近なもので、中野先生がおっしゃったように使わないという選択肢はなく、日常生活の中に情報数理はますます浸透していくのだろうと思います。そうなると、AIや機械学習の最先端を学ぶことも大切ですが、自分の力で解決の入り口に立てるような数理の基礎的な能力を涵養することの重要性も、ますます大きいと思います。それがあるかないかは大きな差になりますから、新たに設置される情報数理学部は、数理の基礎が学べる場であってほしいと思います。
阿部小串先生と同意見です。基礎の重要性に関して、ふと学生時代を思い出しました。人を支援するロボット作りがしたくて知能機械工学科に入学しましたが、情報が必要だと気づき1年で転科を考えたほどです。しかし、基礎をしっかり教えてくれる大学だったため、結局転科しないまま、情報系の研究に携わることができています。そんな経験も含めて、数理の基礎をしっかりやっておくことは、どんな道に進むにしろ大切なことだと思います。
中野英語を使うと海外の人とのコミュニケーションができるように、“数学語”ができると情報社会を読み解く力を養うことができるということでしょうか。
小串物理の立場から言わせていただくと、数学と同時に物理も必要だと強調したいですね。データが手に入っても解析した結果を把握するには、物事の仕組みの基本的な構造を記述する物理の素養が必要で、数学はそれは与えてくれません。その意味で数学と物理を学べる数理という枠組みは良いなと思いました。
中野情報数理の分野で研究したり、学んだりすることについて、女性として何か感じるようなことはありますか。
阿部研究に関して能力面で違いを意識したことはありません。とりわけ私の場合は、育児と研究がダブルワークのような感覚で、一方のストレスをもう一方で発散していたようで、研究という仕事を楽しんでいます。
小串研究においては、女性ならではの視点とか、男性ならではの視点というものも私は感じたことはありません。個人の違いの方が大きいですね。現状で数理の分野に男性が多いということはあるかもしれませんが、臆せず挑戦してほしいと思います。
阿部明治学院大学は女性の割合が高いですから、サークルなどほかの学生生活で女性のつながりができますし、男性、女性を意識する必要はなさそうですね。
小串性別や安心よりも、興味の対象を大切にしてほしいと思います。学生時代に少数派を経験したことは、私自身はその後強みになったと思っています。
中野ありがとうございます。本学では、情報数理学部と同時に、情報科学融合領域センターを設置し、既存学部との連携を通して新しい研究のフロンティア、特に倫理的な側面を強く打ち出していきたいと考えています。お2人が果敢に新しい分野に挑戦されているように、本学も情報数理学部を起爆剤として発展するよう努力したいと思います。





