
更新日2025年2月11日(火曜日)?!「建国記念の日」?!
| TOP表紙 |
| 研究著作 |
| 研究資料 |
| 社会評論 |
| 大学教育 |
| 学会研究会 |

本音・本質が透けて見えたトランプ発言「パレスチナ自治区ガザ地区について,米国が所有して中東のリビエラへ再開発する」と。 リビエラではなく,天然ガス田の再開発だ。
資源略奪戦争としてのイスラエル・ガザ(ハマス)戦争
――東地中海の天然ガス田をめぐって――
israelgazaV2.pdf へのリンク
『学習の友』2024年8月号掲載版
「戦闘停止。ハマス(イスラム教徒)もイスラエル(キリスト教徒)も」。市井の人々の惨状に思いをはせると,いてもたってもいらません。この戦争は,イスラエルによるガザ住民殲滅のための戦争です。そうです,ガザ沖Gaza Marinガス田横取りのための戦争です。
「ウクライナ戦争とアメリカ・国連帝国主義
――米資源覇権世界戦略の視点から――」涌井秀行
明治学院大学『国際学研究』第63号2023年10月
http://www.meijigakuin.ac.jp/~iism/research/63.html
韓国HANKYOREN,藤田進「戦争の裏に天然ガスあり」もご覧ください。寄稿
イスラエル-パレスチナ戦争で利益を得る者が真の「戦犯」
戦争の裏に天然ガスあり藤田進 | 世界史研究所 Reserch Institute for World History (riwh.jp)
=ジャニーズ問題の底にあるもの==戦後日本を覆うドームのごときアメリカの権威=権力。ジャニー喜多川の性加害問題を,この視点からとらえると,戦後日本が見えてくる。それはこうだ。ジャニー喜多川氏は,1952年に再来日し、アメリカ合衆国大使館に勤務していた間,「ワシントンハイツ」に住んでいた。その時近所の中学生らに、ワシントンハイツ内の野球場で、野球を教えていた。「ワシントンハイツの自分の家に、キタガワ氏は次第に子どもたちを招待するようになっていった。日本の中学生にしてみれば、そこに置いてある家具も電気製品も肱しかったに違いない。」そのようなアメリカン・ライフスタイルに惹かれたこともあって、週末の野球以外でもワシントンハイツに頻繁に遊びに来ていたのが代々木中学野球部の、後に飯野おさみ、真家ひろみ、あおい輝彦、中谷良と名乗るメンバーだった。ある日ミュージカル映画「ウエスト・サイドス トーリー」を見てすっかり魅せられた 4 人は、「ああいう踊り、踊ろうよ」と言い出したという。少年野球団の名前をそのまま残した「ジャニーズ」で、ジャニー喜多川は、 4 人を「歌って踊れるアイドル」として、芸能界にデビューさせたのである。
この「エンターテインメント」こそ、日本人に教えるべきアメリカ文化だった。戦後日本社会をドームのようにすっぽりと覆い、「戦後日本の復興と繁栄はアメリカのおかげ」は、信仰・権威となった。ジャニーズの皇居前広場で行われた「天皇陛下の御即位をお祝いする国民祭典」でのパフォーマンスは、戦後日本を覆っている権威=権力であるアメリカ=象徴天皇制の表象である。
この論考は,明治学院大学平和研究所のHPに載っています。
PRIME = プライム 43巻,p. 69-98, 発行日 2020-03-31
https://meigaku.repo.nii.ac.jp/record/3184/files/PRIME_43_69-98.pdf
また下記拙著『天皇財閥・象徴天皇制とアメリカ』第4章(124~153頁)に転載いたしました。ご覧ください。
『天皇財閥・象徴天皇制とアメリカ』
(かもがわ出版)2700円+税 2022年10月31日
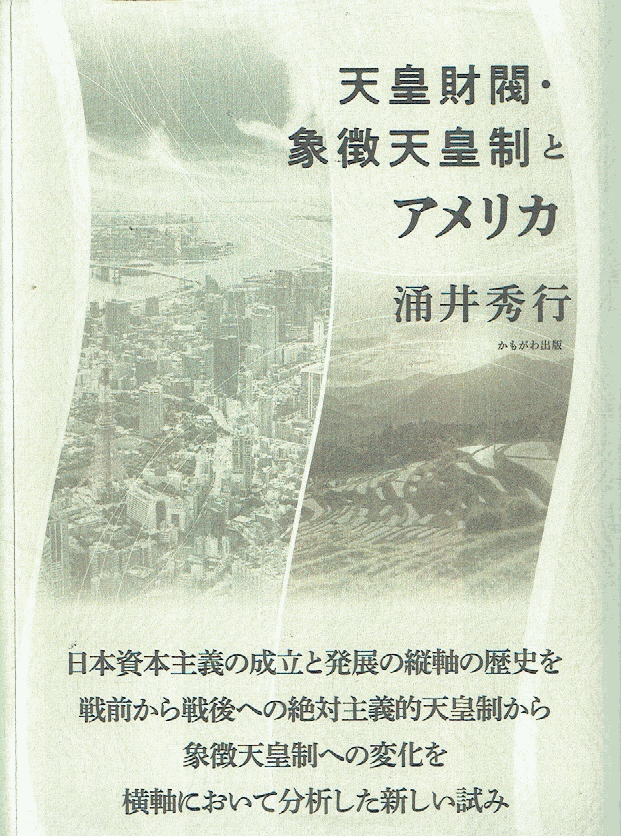 敗戦。皇居前の玉砂利に正座して昭和天皇を遥拝する人々。食料メーデーには「國體は護持されたぞ 朕はたらふく食ってるぞ」のプラカードもあったが,大会決議は昭和天皇陛宛ての上奏文を原案通り可決した。そのなかの一団は、飯米獲得人民大会の名で昭和「天皇への上奏文」をもって皇居にはいった。
国民となった臣民は「人間天皇」の巡行を笑顔で受け入れた。被爆地広島での様子を,中國新聞(ヒロシマ平和メディアセンターHP)は,次のように伝えている.
敗戦。皇居前の玉砂利に正座して昭和天皇を遥拝する人々。食料メーデーには「國體は護持されたぞ 朕はたらふく食ってるぞ」のプラカードもあったが,大会決議は昭和天皇陛宛ての上奏文を原案通り可決した。そのなかの一団は、飯米獲得人民大会の名で昭和「天皇への上奏文」をもって皇居にはいった。
国民となった臣民は「人間天皇」の巡行を笑顔で受け入れた。被爆地広島での様子を,中國新聞(ヒロシマ平和メディアセンターHP)は,次のように伝えている.昭和天皇はポケットから紙を取り出し、『広島市の受けた災禍に対しては同情に堪えない。われわれはこの犠牲を無駄にすることなく、平和日本を建設して世界平和に貢献しなければならない』と述べた。『お言葉』に市民の興奮はピークに達する。沈黙が破れ、市民は帽子を、手を、ハンカチを振りながら、『万歳』と絶叫した。」世界の世論は,広島市民に過酷な犠牲を強いた昭和天皇をどう迎えるのか,注目していた。だが広島市民は原爆ドームを向かって立っていた天皇に「万歳」を唱和したのである。
ファイル:Emperor Showa visit to Hiroshima in 1947.JPG - Wikipedia
昭和天皇に対する憧憬感情は,平成天皇に受け継がれ今日に至っている。戦前そして戦後,絶対主義天皇制から象徴制天皇制へと,二つの敗戦という断絶にもかかわらず,天皇制は深層海流となって流れている。
たしかに,坂口安吾が言うように,その時々の権力者は,歴代天皇を隠れ蓑として「天皇の尊厳」を都合よく使ってきた。その利用の仕方には濃淡があり様々だったが,戦前の絶対主義天皇制下では,「財閥」として富を集中させ神にまで祭りあげ,「国体」として国家の正統思想にまでブラッシュ・アップした。戦後は,主権は国民にあるとしながら,国民統合の象徴として存在し,天皇憧憬感情は,国民大多数のものとなっている。だが問題は,天皇を受け入れた臣民・国民の側の問題である。
どうして大多数の臣民・国民は,そうした天皇制をすんなりと受け入れたのか。ダワーそれを「日本人の一般的な倫理および価値の『ご都合主義』性」と評した。これを解く手掛かり・鍵は,「自粛」にないだろうか。今次のコロナや昭和天皇「崩御」の時にみられた「自粛」現象をどう考えるかである。お上の言うことに,とりわけ一大事には大勢に従う。これがこと天皇に関しては,国民性にまで普遍化し定着しているのではないか。なぜ,どうしてなのだろう。
『経済理論』58巻2号,2021年7月20日経済理論学会
「昭和・平成・令和の天皇代替わりと戦後日本
―戦後日本を覆うドームのごときアメリカ=象徴天皇制―」
『プライム』43号 明治学院大学平和研究所
「アメリカ株価資本主義と世界金融反革命」
神奈川総合政策研究センター『研究と資料』No.209,2018年8月1日号(上),同誌No.210,2018年10月1日号(下)。本論文は『経済理論』54巻4号論文のフルペーパーです。
同誌の投稿論文には字数制限があるため,削除した部分を復活しました。
「アメリカ株価資本主義と世界金融反革命」(上・下)
経済理論学会,季刊『経済理論』54巻4号(2018年1月15日)掲載論文
https://doi.org/10.20667/peq.54.4_68
「戦後日本資本主義の構造としての非正規労働と過労死」
福島大学『商学論集』84巻4号,2016年3月
「戦後日本資本主義の基盤,その生成と衰微
経済理論学会季刊『経済理論』52巻4(2016年1月15日)
同上論文 全文版
『「失われた二〇年」からの逆照射 戦後日本経済分析』
(八朔社,2017年8月21日)2,400円+税
ISBN 978-4-86014-085-4 C3033 四六版 232頁
■日本が今抱えて問題は何ですか。過労死・派遣労働・限界
 集落といった問題です。これらはそれぞれ独立した個別の問題だと思いますか。違います。根は一つなのです。高度成長を実現してきた日本の経済システムが崩れた結果,社会の底に沈みに隠されてきた矛盾が表面に浮き出てきたのです。世の中に漂う漠然とした不安は,「失われた20年」などと言われています。この不安を何とかしてくれるなら,誰でもいい。この不安が託した「希望」が安倍政権の高い支持率を支えています。もちろん安保法制反対の国民的運動,とくにSEALDsのような若者の新しい運動もあるにしても,です。不安の根元を明らかにし,変革すべきモノ=コトを述べたつもりです。
集落といった問題です。これらはそれぞれ独立した個別の問題だと思いますか。違います。根は一つなのです。高度成長を実現してきた日本の経済システムが崩れた結果,社会の底に沈みに隠されてきた矛盾が表面に浮き出てきたのです。世の中に漂う漠然とした不安は,「失われた20年」などと言われています。この不安を何とかしてくれるなら,誰でもいい。この不安が託した「希望」が安倍政権の高い支持率を支えています。もちろん安保法制反対の国民的運動,とくにSEALDsのような若者の新しい運動もあるにしても,です。不安の根元を明らかにし,変革すべきモノ=コトを述べたつもりです。本書は,読みやすさを優先した為,引用文献やデータ等のページ数がありません。それらを以下に電子データで掲載しました。
引用ページ数 参考文献詳細 gyakushoushasanbun.pdf
引用した文章は,★で示しました。それ以外は本文にパラフレーズした参考文献です。
データ ファイル名: hassakuExcel.xlsx
引用される場合は原データ・加工データの出所を明示してください。
====ガザ・イスラエル戦争====
東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/289804
「虐殺に手を貸すな」

「ガザへの軍事侵攻をやめろ」錦糸町駅前にて

===批判的思考の再構築を求めて===
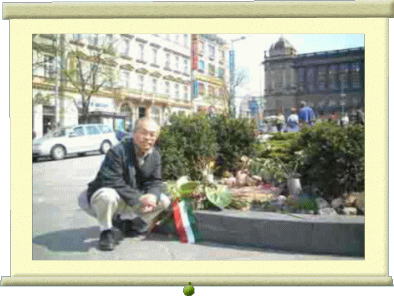
1968年旧ソ連軍のプラハ侵略に抗議して焼身自殺したヤン・パラフの
モニュメントの前で(2003年5月)
このバーツラフ広場は,ハラフの死からおよそ20年の後に,再び歴史の
舞台となった。世界で初めて議会選挙によって社会主義政権を打ち立てた
チェコ人民は,その社会主義政権を平和的に退陣させたのである。チェコ・
ビロード革命である。
今ほとんどの人が,体制全体を揺り動かすような反体制の思想など抱く
ものではないと考えている。だからこそ,自立した精神世界をもち,現在
の体制に批判的に向き合い,それを総体的に点検し,別のあり様を探し,
提示することが求められている。
---------------------------------------
『戦後日本資本主義の根本問題』(大月書店)
シリーズ「戦後世界と日本資本主義」全7巻
第1回配本―戦後日本資本主義の特質を,
土地所有と冷戦体制から読み解く。
The Fundamental Problem of Japanese Capitalism
after the Second World War

書評
黒瀧秀久 『経済』No182 2010年11月号 新日本出版社
山田鋭夫 『経済理論』48巻第1号2011年4月 桜井書店
山田鋭夫氏書評への涌井のリプライ
経済理論学会編『季刊・経済理論』第48巻3号(2011年10月)
新幹線(1964年東京大阪間開通),超高層ビル(1968年霞が関ビル),
東名高速道路開通(1969年)。1970年代以降,日本人,とりわけ都会の
「中間層」は「エコノミックアニマル」などと揶揄されながらも,自分
たちがニューヨークやリやロンドンの人たちとそうは変わらない,と思
っていたに違いない。
しかしそのらしの基盤となる経済構造は,欧米とはかなり違っている。
アメリカ冷戦体制に深く組み込まれていくにつれて,日本は欧米とは違
った独自な「発展」を遂げることになる。その結果生み出された構造が
「外生的循環構造」である。
国民国家の一時代を体験した欧米資本主義とは違って,国外の再生産
構造が国内の構造を代位=補完する構造をもつ。戦後日本は,「下から」
でも,「上から」でもなく,「『外から』の資本主義発展」の道を歩んだ
最初の国である。こうした構造を規定したのは,冷戦体制と零細土地所有
であった。
アメリカ冷戦体制に深く組み込まれ(対米従属)ていくにつれて,日本
独自な経済構造が造形されていく。工業部門への労働力供給の役割をおわ
された農業(農民)が基層におかれ,その犠牲の上に工業が成り立つ。
その工業も大独占企業と中小零細企業という2層構造をもつ。土地の零細
性ゆえに自立の道を断たれた農業。農民は非工業部門での所得で生計を
維持するほかなく,また中小零細企業も下請として大独占に依存するほ
かない。 だがそのいわば食物連鎖の頂点に立つ大独占企業も,原燃料・
技術などの国外依存と国内市場の狭さゆえの輸出のために,対米従属は
決定的となる。
この「構成」成立に際して大きな役割を果たしたのが外資であるが,
同時にれを代位=補完したものが「土地所有」であった。戦後日本の
蓄積「成長」はこの前近代の遺物=土地を資本(擬制資本)に見立て
たのである。以後強蓄積の原資として土地は決定的な役割を演ずること
になる。
既刊 『ポスト冷戦世界の構造と動態』
 八朔社 2013年5月) 3200円+税
八朔社 2013年5月) 3200円+税 誰にでもわかってほしい。本書はそういう思いで,こ
の10年ほどの間に書きためたものを,全体をできるだけ
統一し,欠落しているところを補い,わかり易く書きな
おして,全体を再構成した本である。こうした意図から
研究書と一般書との中間を目指した。
それが成功したか否かについては,読者の判断にゆだね
ざるを得ないが,非常に難しく目的を果たせなかった,
のではないか。これが正直なところである。
書評:宮本幹夫『明治学院大学国際学研究,』45号,127-131頁。
増田壽男「書評」(『(季刊)経済理論』51巻4号,2015年1月,99-101頁)。
 第1巻 21世紀型危機と戦後日本資本主義――増田壽男
第1巻 21世紀型危機と戦後日本資本主義――増田壽男遺稿集として2024年11月22日に刊行されました。
第2巻 戦後日本資本主義分析史と展望
―鈴木春二(第5回配本)
第3巻 戦後日本資本主義と平成金融恐慌
―相沢幸悦(第2回配本)
第4巻 現代グローバリゼーションとアメリカ資本主義
―柿崎繁(第4回配本)
第5巻 戦後日本資本主義の根本問題
―涌井秀行(第1回配本)
第6巻 戦後日本重化学工業の構造分析
―吉田三千雄(第3回配本)
第7巻 戦後日本資本主義における労使関係
―藤田実(第6回配本)