発達障害の子どもの心を支える教育と医療の連携を
現在、発達障害(本稿では神経発達症の意で用います)は地域で暮らす子どもたちの約10%に見られます。発達障害の子どもには特性に合った環境や支援が必要ですが、学校では集団の中での学びに困難を抱え、心の健康が損なわれてしまうことも。小林潤一郎教授は、子どもの心を支援する力を備えた教員をめざす学生が多く学ぶ教育発達学科で、障害がある子どもの心と学びをどう支えていくのかを指導し、教育と医療の連携・協働をテーマに研究・実践を展開しています。


小林 潤一郎
心理学部教育発達学科教授
筑波大学医学専門学群卒業。大学卒業後、静岡県立こども病院に勤務し、小児科と神経科で診療に従事。1998年、本学文学部心理学科専任講師となる。2005年、オーストラリア・モナッシュ大学心の医療部へ留学。2010年より現職。横浜市の療育センターで発達障害の子どもたちを診療し、特別支援学校で精神科校医も務めている。小児科専門医、子どものこころ専門医、日本小児精神神経学会認定医。
教育と医療、難しい情報共有
私は障害児医学、発達小児科学を専門とし、特に発達障害医療が子どもの学校生活にどのようにかかわることができるかを研究しています。
発達障害は脳機能の発達に関する障害であり、代表的なものとして、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(いわゆるLD)などが知られています。その症状は、重度のものから一般の方では気づくことができないほど軽度のものまで、非常に幅が広く、症状の現れ方もさまざまです。近年では軽度の子どもも多数、専門の医療機関を受診しており、地域で暮らす子どもたちのおよそ10%が発達障害と診断されるようになっています。
医療機関を受診し、発達障害の診断を受けても、それだけでその子をこれからどう育てたらよいのかが分かるわけではありません。発達障害の子どもは、社会性、行動コントロール、学習能力、知的機能などに関する脳の機能が育ちにくいため、日常生活や社会生活のさまざまな場面でつまずき、心の健康にとってマイナスのことが生じやすくなります。学齢期の子どもの場合、医師は学校でどんな配慮や支援が必要かを教師と共有する必要がありますし、イライラや攻撃性などの精神症状が現れている子どもの治療のために、日ごろ学校がどんな支援をしているのかを知る必要があります。ところが、そうした情報は保護者を介してやり取りするしかないのが現状です。教育と医療の連携・協働のためのしくみ作りが進んでいないことは、今の日本の大きな課題だと感じています。
学びを支える医療をどう整えるか
現在、発達障害の子どもの人数に対して専門医療機関が少なく、各医療機関で受診待機期間の長期化が問題になっています。発達障害の疑いがある子どもを正しく診断することは、もちろん大切です。ただ、支援のスタートが医師の診断である必要はありません。発達障害をめぐる問題の多くは、家庭や学校といった生活の場で生じています。10%の子どもに見られる「ありふれた問題」なのですから、発達障害を疑ったら、まず家庭や学校でその子に合った支援を始め、医療がその後方支援をするという形の方が、現実的ではないでしょうか。通常の学級で発達障害の疑いがある子に気付いた教師が、その子に合う支援に迷う時、医師に助言を求めやすいシステムがあれば安心できるはずです。発達障害の子どものつまずきを予防するために、教師とともに子どもの学びと心を支える医療をどう整えていくか、教育と医療の連携・協働をどのように進めるのかを大きなテーマとして、研究や実践を行っています。

子どもに合わせた環境や教え方が不可欠
子どもたちは学校で、決められたルールや手順に従い、先生やクラスメイトとともに、時間割や年間計画に沿って生活しています。授業のはじめにあいさつをする、職員室にはノックしてから入る、先生が話し始めたら注目して黙って話を聞くといったことが、学校という場で当たり前に求められます。ところが、自閉スペクトラム症の子どもたちはそうした社会的な場や状況、他者との関係や活動の枠組みに折り合いを付ける力が弱いので、学校生活に混乱して心の余裕がなくなってしまうことがあります。家では気分が落ち着いているのに、学校ではイライラや攻撃性、不安などが現れてしまう子も珍しくありません。
こうした症状は、子どもを学校の環境に合わせさせようとするのではなく、環境を子どもに合わせ、その子が力を発揮できる環境をつくることで解消できる場合があります。たとえば、環境の変化に慣れるのに時間のかかる子には、学期はじめの生活の流れを簡潔にして新しい課題を少なくすると、新しい生活を始めやすくなります。見通しが持ちにくく急に質問されると混乱してしまう子には、質問する順番を伝えておけばあわてずに答えることができます。感覚過敏があって給食の時間に食器のこすれる音や食事のにおいで気持ち悪くなってしまう子は、別の場所で給食を食べることができれば安心して過ごすことができます。個々の特性を理解し、特性に合った支援をすることが、発達障害の子どもたちの意欲を伸ばし、心を守ることにつながります。
一方で、子どもの「場に合わせる力」を育てることも、教育の大切な役割です。意図を理解する力が育ちにくい子どもには、何を考えることが求められているかを分かりやすく示して「考えるよう促す」。理解する力が育ちにくい子どもには、その子は何がどう分からないかを想像して「理解しやすい」教材を示す。注目する力が育ちにくい子どもには、「注目しやすい」場面設定をする。そういう仕掛けが必要であることを教師側が理解していないと、「考えようとしない子どもが悪い」ということになってしまいかねません。
教育発達学科は、心理学を基盤に、教育学や障害科学を融合した学びを通して、子どもの心を支援する専門性を身につけていきます。ただ、そこで学んでいる学生であっても、当たり前のように「児童に考えさせる」「理解させる」「注目させる」というフレーズを使うことがあります。学生は深く考えずに使っているのでしょうが、その言葉の裏側には「教師が指示し、子どもはそれに従うもの」という意識があるように感じます。
私が出会った発達障害の子どもたちは、みんな最初は「分かるようになりたい」と思っています。しかし、なかなか分かるようにならないと、「どうせ自分にはわからない」「勉強しても無理」と意欲を失ってしまいます。子どもが何にどう困っているのかを考えることができ、そのための手立てを柔軟に実行できる教師を育てることも、大学での私の役割だと考えています。

校医が教室を回る精神科健診を実践
大学での勤務のかたわら、横浜市内の療育センターで発達障害の子どもを診療し、特別支援学校の校医や臨床指導医、通級指導担当教員の研修講師などを務めています。その活動の一つで、子どもの学校生活にかかわる医療の方法として実践しているのが、「知的障害特別支援学校における校内巡回方式による精神科健診」です。
この健診は、行動や様子が気になる子どもを事前に担任教師に挙げてもらい、学校医が教室を回ってその子の行動を見る形式で行うものです。子どもの様子を見ながら、必要に応じてその場で子どもと簡単な面接をし、下校後に担任と子どもの状態や対応方針を話し合います。校医の意見を取り入れるかどうかは教師側の判断ですが、指導や支援で迷っている教師にとって、他職種である校医からの助言は参考になるようです。実際、先生方からは「一緒に考えてくれる人がいるとありがたい」という反応を数多くいただいています。
また、発達障害の子どもや大人が所属感を持って参加でき、意欲や自己肯定感といった心の健康のプラスになる要素を得られる場と仲間づくりが重要だと考え、十数年前から本学の心理臨床センターで発達障害の人を対象にしたプログラムを実践してきました。そうした所属の場を、彼らが暮らす地域の中にどのように広げていけるかを検討していきたいと思っています。
知識は実践してはじめて「学び」になる
学部の授業は、特別支援学校教員免許取得に必要な「知的障害の病理」など、障害児医学に関する科目を担当しています。疾患の種類や症状、処方される薬など、医学的要素の強い内容に苦戦する学生もいるようですが、たとえ難しくても、学生には専門的な用語や情報を正確に理解して覚えることを求めています。なぜなら、何か専門的な領域のことを勉強しようとするのなら、基礎となる知識を身に付けていなければ、先へは進めないからです。昨今、大学を含めた教育の現場では、用語や情報を覚えることより考え方を育てることが重視されているように思います。私もそれは間違っていないと思いますが、その領域の基礎知識がなければ専門的な事柄を考えることはできません。専門的な学びの第一歩として、正確な基礎知識を身に付けることは大切だと思っています。
講義で学んだ基礎知識は、その知識を使って考え、実践することで、はじめて確かなものになります。その実践の場になっているのが、ゼミや特別支援臨床実習です。
私のゼミでは、自閉スペクトラム症を中心に、障害のある子どもの教育と医療について学びます。3年次秋学期からは、社会の現実的な課題に対して学生なりの解決法を検討するプロジェクトに取り組みます。これまでに特別支援教育に関する学生向け啓発用小冊子作り、教員と保護者の情報共有のためのツール開発などを実践してきました。知識を使って現実と向き合い、考えたことを形にするステップが、学生の成長に繋がっていると思います。また、プロジェクトの資金は大学のボランティアファンドを利用して学生自身が調達しており、そうした経験も社会に出てから役立っているようです。
3年次の「特別支援臨床基礎実習」、4年次の「特別支援臨床実習」は、本学の心理臨床センターで実際に支援が必要なお子さんに協力していただき、学生たちが子どもと関わりながら支援について学ぶ科目です。教員の指導の下、年10回の支援セッションとその振り返り・準備・教材作成をする年14回のミーティングを繰り返し、お子さんの実態把握、支援目標の設定、支援計画の立案・実行・修正を行っていきます。どんな工夫をすれば子どもに伝わるか、自分の言葉や行動が子どもにどう届いているのかといったことを、実際に子どもと接しながら理解する場になっていると思います。
心理学科時代から現在まで、卒業生の多くが心理士や教師になり、学校、障害児支援などの現場で活躍してくれています。心理臨床センターで行うプログラムのサポートをしてくれている卒業生もいますね。彼らと一緒に仕事をすると、子どもの成長をともに支えることができていると感じられ、嬉しくなります。大学教員として、発達障害の子どもを多職種で支援することやそのしくみ作り、支援する人材の育成にかかわることの面白みを感じる瞬間です。
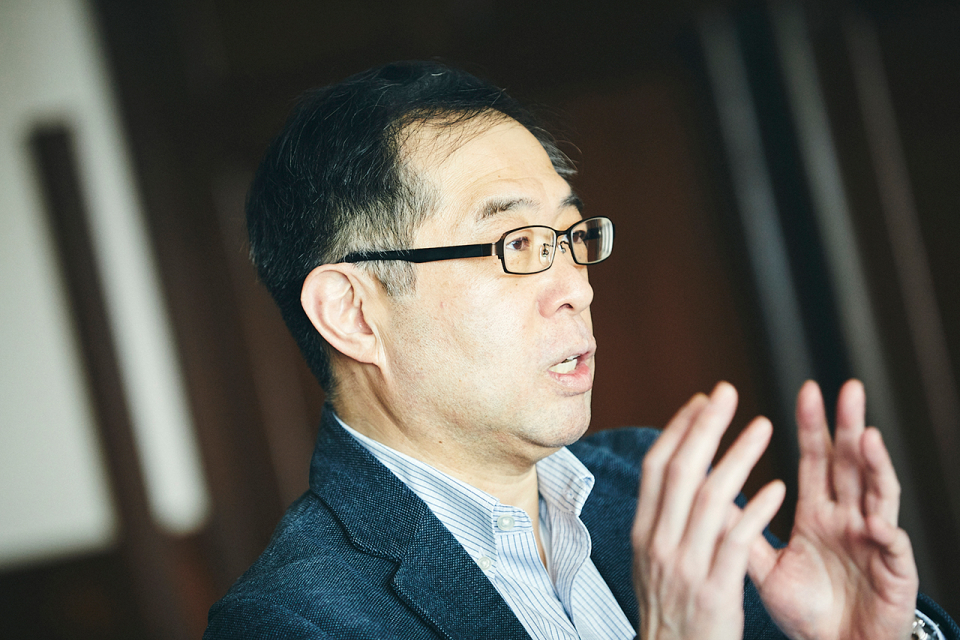
小児科の臨床医から研究・教育の道へ
私が自閉スペクトラム症や限局性学習症のことを初めて知ったのは、医学部3年生の頃でした。「自閉症(当時の疾患名)って何?どういうこと?」「知的な障害がなくて話もできるのに文字を読めないなんてことがあるのか?」と衝撃を受け、その講義をしてくださった小児科医で心身障害学系の教授をしておられた故・長畑正道先生の研究室を訪ねたことが、障害児医学の道に進む最初の一歩になりました。
大学卒業後は、静岡県立こども病院の研修医となり、さまざまな疾患の診療を経験しました。ある時、外来で診ていた発達障害のお子さんに顕著な精神症状が現れたので、薬物療法を始めました。しかし、そのお子さんは、診察室では穏やかなのに、一向に症状が改善しません。その理由を突き止めたくて、思い切って保護者の了解を得て学校にうかがい、お子さんの様子を見せていただくことにしました。
実際に教室の環境を見てみると、そのお子さんの特性に合っていないように感じる箇所がいくつか見つかりました。それを担任の先生に伝えると、すぐに私の話を参考に環境を工夫してくださり、その後、症状は速やかに改善しました。この経験から「診察室でできることには限界がある。医者と一緒に子どもたちを支援する教師や心理士を増やさなければ」という思いを強くし、明治学院大学の教員の公募にダメ元で応募したところ、運よく採用されて今に至っています。
地域の学校をもっと大事にする社会に
教員の業務過多や教員不足によって、学校現場の疲弊は深刻化しています。私が今願うのは、社会全体から学校教育がもっと大切にされ、すべての子どもたちが生き生きと学校生活を送れるようになってほしいということです。
発達障害の子どもへの支援を進めようとすると、学級全体への指導と、発達障害の特性に応じた個別の指導の両立という難題に直面します。1学級の子どもの数が多く、教員の数が少ないことが両立を特に難しくしていますが、学級数や教員を増やすには、公教育を充実させることへの社会的コンセンサスが必要でしょう。また、教科書や学習指導要領を踏まえつつ、学校が何をどう教えるかをある程度柔軟に決められ、学級全体の学習進度について保護者の理解も得られれば、個々の子どもの特性に応じた学びを支援しやすくなります。社会がそうした学校教育の柔軟さを前向きに評価することが、発達障害の子どもも学びやすい学校づくりを後押しする力になるのではないでしょうか。
現在取り組んでいる研究や学生への教育をさらに進めることで、子どもの意欲を引き出し、育てる力を備えた教員が増え、学校が変わり、子どもの心の健康をもっと高めていけると期待しています。発達障害医療は、社会生活でつまずきやすい彼らにとっての「転ばぬ先の杖」となることが理想です。医療の中でも、心の健康問題の治療だけでなく、予防や早期対応がもっと大切にされるよう願っています。

研究者情報
明治学院大学は、研究成果の社会還元と優秀な研究者の輩出により、社会に貢献していきます。
取材・撮影について
本学および勤務員(教員など)の取材・撮影のご相談はこちらからお問い合わせください。
■ 本学に直接関連のない撮影、収録、ロケ地としての貸し出しは原則としてお断りしております。
■ 在校⽣、卒学⽣、勤務員の個⼈情報に関する個⼈的なお問合せには応対しかねます。
■ 企画書等のファイル送信をご希望の場合、以下のアドレスまでご連絡ください。
学長室広報課: koho@mguad.meijigakuin.ac.jp

 入試情報サイト
入試情報サイト