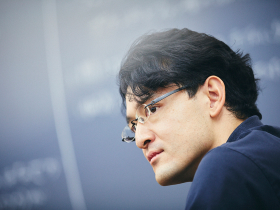
- 大竹 光寿 経済学部 経営学科 准教授一橋大学大学院商学研究科博士課程修了。博士(商学)。2012年より本学経済学部経営学科専任講師を務め、15年4月より現職。専門分野は消費文化理論、市場戦略論。消費文化の形成プロセス、市場認識と組織慣性を主要な研究テーマとし、正統性や組織慣性の観点からブランドマネジメントに関する研究に取り組む。趣味はいろいろな企業の社史を読んで新たな社史のスタイルを考えること。
「らしさ」を超えてブランドを成長させる創造的原点回帰とは
私たちの身の回りには、高級品からリーズナブルなものまで、さまざまなブランドがあふれています。ブランドを確立する上で、そのブランド「らしさ」をつくることは大切ですが、消費者側が感じる「らしさ」のイメージにとらわれると、ブランドが衰退する元凶になることも。大竹光寿准教授は、「らしさ」の呪縛に悩む企業がどうすればブランドの刷新や再構築を実現できるのか、市場や消費者との接点に着目しながら研究を進めています。

経営学でもっとも消費者に近い領域・市場戦略論
経営学は、会計、金融、組織論、経営戦略などたくさんの研究領域を持つ学問です。その中でも私は市場戦略論(マーケティング論)を専門としています。市場戦略論とは、企業がどのように市場のニーズに適合する製品やサービスをつくり(Product)、その存在を伝え(Promotion)、価値に見合った価格(Price)で、届ける(売る場所=Place)のか、という一連のプロセスを理解しようとする研究領域です。マーケティングではこの「4つのP」の活動を市場にフィットさせることが基本であり、重要なテーマでもあります。
市場戦略論のキーになっているのが、市場との「適合」という考え方です。適合にはさまざまなレベルがあり、一番分かりやすいのは「消費者のニーズを調査し、それに合ったものをつくる」という適合です。一方で、ソニーのウォークマンに代表されるような、消費者が全く想像もしていないものを提供して潜在的なニーズを掘り起こす “ハイレベル”な適合も存在します。単に顕在化されたニーズに合わせるだけでなく、消費者の新たなニーズに気づかせるような高次の適合をどうつくるかも、市場戦略論では重要なテーマです。
市場戦略論は、経営学の中でももっとも市場に近い、つまり消費者に近い領域だといえます。そのため、マーケティング論と消費者行動論の両方を研究している学者は少なくありません。私もその一人で、消費者行動論の中でも消費者がブランドの「ほんものらしさ」(正統性)を感じるプロセスに関心を持っています。人は過去の経験から自分に合うブランドのイメージを持っていて、それと関連付けてほんものらしさを判断しているのではないか、という視点から研究を行っています。

「らしさ」の呪縛が新たな挑戦を阻む
実務家と話していると、よく「ブランドを刷新したいのになかなか踏み出せない」という声を聞きます。ブランドの刷新をリブランディングといいますが、これがまさに“言うは易し、行うは難し”。市場の変化に直面してもリブランディングができず、時代に取り残されてしまう企業も少なくありません。
刷新を阻む一つの要因になっているのが、市場の目です。ブランドマネジメントの本質は「らしさ」の追求ですが、市場でのブランドイメージ=「らしさ」をあまりに強く意識するとそれに依った活動や提案しかできず、新たな挑戦を阻んでしまいます。また、マーケティングの研究には「マーケティング・マイオピア」(近視眼的マーケティング)という概念があり、これは企業が自分たちの事業の自己定義を狭くしすぎると他社との競争に負けてしまうことを指しています。自己定義や「らしさ」が一人歩きしてしまい、変わるに変われない「組織慣性」が生じるという現象は、大きなブランドや老舗企業ほど多く、悩みの種になっているようです。
いかにして「ふとんの西川」はリブランディングを実現したか
では、どうすれば組織慣性やブランドの硬直性を打破できるのか。それこそが、いま私が取り組んでいる研究テーマです。
市場という社外の変化に対応するのなら、「外向き」の動きが必要なように思えますが、そうとは限りません。市場と向き合えば向き合うほど他社と横並びになり、変わることができたとしても横並びにしか変われないかもしれない。だとすれば、逆に「内向き」になってブランドの原点を振り返った方が、リブランディングがうまくいくのではないか、というのが私の考えです。
ブランドの硬直化を打破するために、ブランドの原点と向き合うとはどういうことなのか。寝具メーカーの西川株式会社を例に説明してみたいと思います。
“ふとんの西川”で知られる西川は、戦国時代から450年以上続く老舗です。現在の看板商品の一つが、2009年に発売した高機能マットレス「AiR」。トップアスリートをPRに起用し、斬新でカラフルな色遣いが幅広い購買層に支持されて大ヒットしています。
AiRの開発を提案したのは婿養子として創業家に入った現在の社長なのですが、実は商品化前に社内の猛反発に合っています。反対された理由は「西川らしくないから」。西川は購買層の年齢が高く、製品は落ち着いた色のものばかり。「こんなに派手な商品を出したら、大切にしてきた西川のブランドイメージが壊れてしまう」。そんな声が強かったといいます。
ところが社長は、西川の“意外な”歴史を知っていました。西川は江戸時代、地味な色が定番だった蚊帳に鮮やかな色を付けて売り出し、大人気になっていたのです。「昔は斬新な取り組みをしていたけど、最近はできていないじゃないか。また市場が驚くような商品を出そう」。社長はそう説得し、発売にこぎ着けたのだそうです。
※大竹光寿(2017)、「ブランドマネジメントに関する慣性の強化と緩和:創造的原点回帰によるブランドのあるべき姿の再構築」『マーケティングジャーナル』146、96-111。
ブランドを生き返らせるのは、ブランドの“原点”
過去を振り返り、創業期またはブランドが飛躍した時点を「原点」として、そこに向き合う。それも、ただ単に昔に戻るのではなく、原点を今流に解釈し直す「創造的原点回帰」をする。それこそが、ブランドの硬直性を打破する一つの力になります。西川の場合、まず「蚊帳に色を付けて大ヒットした」というブランドの原点を振り返り、単にそれを再現するのではなく、「色を付けたことで蚊帳の機能性にも訴求できたはずだ。AiRも凹凸に合わせて色を変え、機能性をアピールしよう」と解釈し直したことが、ブランドの刷新を成功に導きました。創造的原点回帰はまったく市場の声を聞いていませんが、実はその方がブランドの「らしさ」や存在意義を表現でき、他社と違ったものを生み出せる可能性があるのだと思います。
「ブランドの創業者の思いや背景にしっかり向き合い、価値の高い製品やサービスを提供する」。これはいたって当たり前のことのようですが、現場を観察していると、その時々の市場の声に耳を傾けるあまり、自分たちの本質を見失ってしまう企業が数多くあることに気づかされます。原点に思いを巡らせることは、他の存在と異なる際だった「ブランド」をつくり、変化する市場に適合していくためには、とても大切なことなのです。
実務と学問の橋渡し役をめざして
私がマーケティング研究の道に進んだのは、学生時代にインターン先の企業でプロモーション活動に参加して興味を持ったことがきっかけでした。知識を身につけるために、経営戦略論で国際的に高い業績を持つ伊丹敬之先生、マーケティング論の石井淳蔵先生、消費研究の松井剛先生の論文や著書を読み、理論を知るとこれほど世の中が深く理解できるのかと感銘を受けたことを、今でもよく覚えています。
特に伊丹先生は、多くの企業の社外取締役を務めるなど、企業の実務と近い距離で研究をされている先生です。その影響を受け、私も実務と学問の橋渡しをするような研究者をめざしています。実務家との勉強会やワークショップを開いて最新の事例に触れ、私の研究の知見を提供する機会をつくっていますし、創造的原点回帰の研究も、さまざまな企業の方との対話で生まれた気付きが出発点になっています。
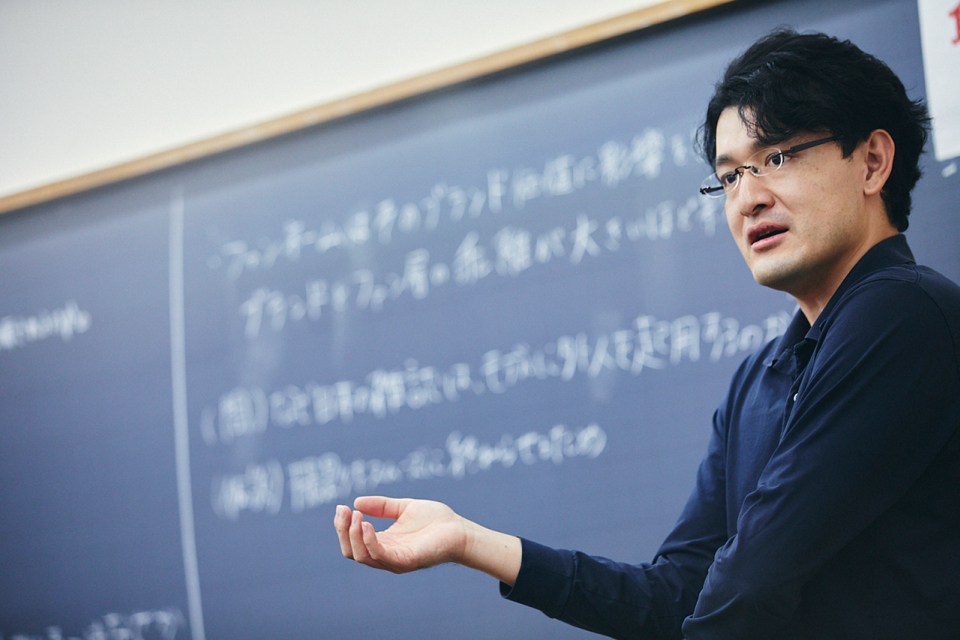
現場と実践でマーケティングを学べるゼミ活動
現場との関わりは、学生への教育でも重視しています。ゼミでは、学生がブランディングなどに関わる実務家と接し、社会に何らかの貢献をするプロジェクトを企画・実行する活動をしています。これまで、高校生にマーケティングの面白さを感じてもらうイベント、ブランドに関わる人たちに直接取材をして写真や文章でブランドの本質を伝える「ブランドブック」の制作などを行ってきました。
将来マーケティングを仕事にしたい学生にとって、現場に触れて自分に何が足りないのかを知ることには大きな意義があります。さらに、ゼミ活動を通じて、マーケティングを実践で学ぶことができます。ブランドブックの場合、単に取材して企業やブランドを「知る」だけでなく、ブランドブックというコンテンツを使って自分たちでマーケティングを「する」経験ができるのです。こうした経験を経て、学生は学問への興味を高め、卒論執筆のモチベーションアップにもつながっているようです。また、中には活動中にインターンシップ先を見つけ、就職につなげている学生もいます。学びとキャリアをうまくリンクさせることができるのは、経営学という学問領域の良さの一つかもしれません。
今後は、私の研究テーマに興味を持っているゼミ生と一緒に論文を書いてみたいと思っています。いずれは学生と“研究仲間”になり、互いに教え合いながら研究をしていきたいですね。

木工家具を作る父の姿が私の“原点”
今回自分の研究をお話しするに当たって、私も自分の「原点」は何かなと考えてみました。あらためて振り返ると、私の原点にあったのは、父の姿でした。
父は、私が生まれた頃からずっと、小さな木工家具の製作所を営んでいます。典型的な零細の町工場で、仕事のほとんどは図書館の家具や備品を扱う大手メーカーからの請負です。幼いころ、私が不思議だったのは、父はこんなに一生懸命働いているのに、なぜ父が作った家具には「大竹」という名が表示されずに世に出て行くのか、ということでした。私にとっては「うちの会社の製品」なのに、お客様にとっては「大手メーカーの製品」。そう思うと、父がかわいそうで、なんだかむなしいような、複雑な気分でした。これは私自身の考えで、父自身はそんなことは思っていませんでしたけどね。
ただ、経営学の中でも市場戦略論やブランドに興味を持った背景には、あの時のモヤモヤとした感情があるのかもしれません。今はそんなふうにきれいに振り返っていますが、おそらく過去を取捨選択し、良い意味で多少脚色して解釈しているのでしょう。これもひとつの「創造的原点回帰」ですね。
コロナ禍はマーケティング研究を変える?
コロナ禍による経済的不安などを背景に、自動車から日用品にいたるまで、モノを必要なときだけ借りたり、他人と共有したりするシェアリングサービスが社会に広がっています。シェアリングの加速化は、マーケティングの研究にもさまざまな影響を及ぼしています。なぜなら、マーケティング論や消費者行動論の多くは、モノを「買うこと」を前提とした購買意思決定のプロセスを理解する研究だからです。
私自身の研究でいえば、モノを買う前提で見る時と、借りたりシェアしたりする前提で見る時では、ほんものらしさの源泉も違うのではないか、という新しい視点が生まれています。100万円の時計に対して、買う前提で見るのと、借りる、もしくは「飽きたらフリマサイトで70万円ぐらいで売れるかな」と思って見るのとでは、自分にフィットするかどうかの感覚は違ってくるのかもしれません。そうなると、シェアリングエコノミーには、これまで研究されてきた購買意思決定プロセスのモデルを当てはめるのが難しくなる可能性があります。
シェアリングの拡大のような社会の顕著な変化は、新しい研究テーマを見つけるチャンスですし、研究者としてのモチベーションを刺激するものでもあります。現実の変化に伴って、研究の視点も変わります。これからも、私の論文や本を読んで、実務家が少しでも新しい視点を得られたり役立ったと感じられたりする研究テーマを見つけ、取り組んでいきたいと考えています。

研究者情報
明治学院大学は、研究成果の社会還元と優秀な研究者の輩出により、社会に貢献していきます。
取材・撮影について
本学および勤務員(教員など)の取材・撮影のご相談はこちらからお問い合わせください。
フォームでのお問い合わせ
- 本学に直接関連のない撮影、収録、ロケ地としての貸し出しは原則としてお断りしております。
- 在校⽣、卒学⽣、勤務員の個⼈情報に関する個⼈的なお問合せには応対しかねます。
- 企画書等のファイル送信をご希望の場合、以下のアドレスまでご連絡ください。
総合企画室広報課: koho@mguad.meijigakuin.ac.jp
