法と経営学専攻 (修士課程)
企業活動に不可欠な法と経営学とを融合的に学び、実社会のリーダーとなる
現代は企業や行政の専門化が高度に進んだ社会と言えますが、我々はそのメリットを享受する一方、「縦割り組織」によって生じうる弊害にも直面しています。そこで法と経営学専攻のカリキュラムは、経営学と法学の双方から学際的に、健全かつ合理的な企業経営の在り方を探求することができるように編成されています。また、事業活動で不可避的に生じる諸問題に適切に対処するために、豊富な事例研究を多用して経営学および法学双方の理論を融合的に学ぶことができるように工夫されています。
たとえば必修科目の「ビジネス総論1・2」では経営学の教員と法学の教員2名が常に教室に入り、医薬品のネット通販に対する厚生労働省の規制が最高裁で否定された事案のような両分野にまたがる事例を題材にして、自由闊達な議論を重ねながら両学問の視点から分析し、総合的な解決策を練り上げていきます。法と経営学専攻は、経営学と法学との広い視野に立った問題意識を持ち、自身の専門分野について深い洞察力のもとで理論と実践とを架橋することに挑戦する意欲的な方々の入学を願っています。
TOPICS
事業承継者、起業家の育成
事業を維持し発展させていくためには、経営上の意思決定力と、組織の法令遵守や資産管理上の法律知識とを習得することが重要です。中小企業の後継者不足は深刻化しつつあり、事業展開を担うには経験が不足している者であっても、短い期間で企業経営で生じうる諸問題に適切に対処する能力をつけることが必要です。法と経営学研究科は、経営学と法学とにわたる多彩なバックグラウンドを有する教員と充実したカリキュラムによって、事業経営能力の獲得を可能にします。
専門的職業人の育成
営利企業であっても短期的な収益追求だけではなく、法令遵守さらには社会的責任に対する要求が強まっている今日、企業に進む学生が付加価値を高めるためには、経営学と法学にまたがった問題意識や問題解決のセンスを磨くことが重要です。本研究科ではこれらに加えて、専門科目の履修や修士論文作成を通じてそれぞれの専門領域における分析力や知識、表現力を習得することで、経営コンサルティング、法務部のスペシャリストなど企業でリーダーとなりうる専門的職業人を育成します。
税理士試験の科目免除
修士論文を税法に属する科目等で研究した場合は税法に属する科目について、会計学に属する科目で研究した場合は会計学に属する科目について、税理士試験の試験科目免除申請をすることが可能です。ただし、科目免除は国税庁が定める所定の審査に合格した場合であり、審査で不合格になる場合もありますので、ご注意ください。詳しくは税理士法その他関連法令をご覧ください。
マスター消費生活アドバイザー
一般財団法人日本産業協会からマスター消費生活アドバイザーに係る大学院指定を受けています(全国で5大学院のみ)。本研究科ではこの資格を取るために必要な要件の1つを満たすことができる科目が提供されています。詳しくは「明治学院大学 法と経営学研究科」のオリジナルサイトをご覧ください。
インタビュー
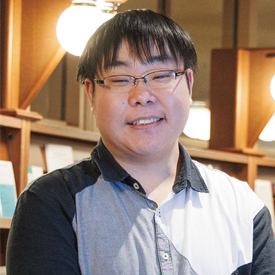
稲田 水咲
法と経営学専攻 修士課程
2024年3月修了
法律と経営学を学際的に学修・研究できる環境で得た知見を活かして活躍したい
明治学院大学法学部の1年次に消費者法の講義を受けて、私たちの日常生活に密着した法律で、知っていることで商品の安全性や悪徳な勧誘などのトラブルから身を守れるところに興味を惹かれ、より深く学びたいと考え大学院進学を決めました。法と経営学研究科を選んだのは、「マスター消費生活アドバイザー」の資格取得に対応した指定大学院だったこと、経営学の知識を学ぶことで事業者側の視点からも消費者法について考えられることが大きなポイントでした。大学院で「消費者契約法9条1項1号の射程」というテーマで修士論文を執筆し、さまざまな関連法令や50本以上の判例研究に取り組み、何とか満足いくものが出来上がりました。また、徳島県で開催された消費者庁の地域推進フォーラムにパネリストとして参加するという貴重な体験もできました。修了後は自動車部品メーカーにて働きますが、総務や法務関連の部署で学部~大学院で学んだ消費者法や会社法、知財法、会計学などの知見を活かして活躍したいと考えています。
修了後の進路 (過去3年間の実績)
アクティアス、アバー・インフォメーション、EY、エフテック、オリエントコーポレーション、ぎょうせい、三英堂商事、シャープマーケティングジャパン、信金中央金庫、DTS、手島&パートナーズ会計、東京国税局、TOTAL、日清不動産、日本年金機構、日本経済廣告社、NexTone、PwC、日立リアルエステートパートナーズ、ビックカメラ、船井総研ホールディングス、ベルシステム24ホールディングス、三菱電機エンジニアリング、山田&パートナーズ、横浜銀行
2026年度 専門分野/開講予定科目 担当教員紹介
| 氏名 | 専門分野/開講予定科目 | 授業内容 | ※1 |
|---|---|---|---|
| 飯田 浩司 教授 | 知的財産法研究 (知的財産の法と実務) | 企業活動と関連が深い著作権法、不正競争防止法等の知的財産法に関して、過去の判例や事例を題材として、実務上の留意点を踏まえつつ検討する。 | 〇 |
| 岡崎 哲二 教授 | コーポレート・ガバナンス研究 | 企業経営を効率化するための制度的・組織的な仕組みを研究する分野がコーポレート・ガバナンス論である。この授業では米国の標準的教科書を用いてコーポレート・ガバナンス論を体系的に学ぶ。 | 〇 |
| 川端 康之 教授 | 税法研究1(税法の基本原理) | 租税法学の学修の入口として、租税法学の「総論」を主に扱う。租税法律主義と法の下の平等を前提に、租税法律関係の性質、私法との関係、租税回避行為の租税法上の効果等を学ぶ。 | 〇 |
| 来住野 究 教授 | 会社法研究1 (企業組織の法と実務) | 株式会社における所有と経営の分離・機関設計の多様化を確認した上で、コーポレート・ガバナンスにおける各機関の役割及びその実効性確保のための法規制を学び、実務上・立法上の課題を探究する。 | 〇 |
| 赤渕 芳宏 准教授 | 環境法研究(企業と環境問題) | 企業には、環境問題の発生を未然に防ぎ、生じた環境問題を解決することが求められる。そのためのルールたる環境法とはいかなる法であり、それにはいかなる特徴と限界とがみられるか、検討する。 | 〇 |
| 大竹 光寿 准教授 | 経営学研究論 | 組織や経営現象を対象とした研究の方法について学ぶ。方法論の文献のみならず、多様な実証研究の検討を通じて、問いと仮説の設定、データ収集や分析方法、表現方法などに対する考えを深める。 | 〇 |
| 木川 大輔 准教授 | 経営戦略研究1(中小・中堅企業の持続的競争力構築) | 企業が持続的な競争力を構築・維持・強化していく上での課題を組織内部・外部の両面から検討する。理論面の基礎知識の習得はもちろんのこと、先端事例の現象面を読み解く機会も重視する。 | 〇 |
| 田原 慎介 准教授 | 経営組織・労務研究3(経営と組織) | 組織の適切な運営について、組織と環境の関わり、組織の中で働く人の行動というマクロとミクロの両視点から体系的に学ぶ。理論に偏らず実践的な視点を取り入れた事例分析を重視する。 | 〇 |
| 福島 成洋 准教授 | 消費者法研究(消費者保護の法と実務) | 誇大広告や製品の欠陥など、事業者・消費者間の取引(BtoC取引)に付随して様々な問題が生じている。どのように消費者を保護すべきか、事業者側の視点も踏まえつつ、具体的に検討する。 | 〇 |
※1 修士課程の研究指導
入試情報

 入試情報サイト
入試情報サイト