ブランディングプロジェクトについて
ブランディングプロジェクトとは
「明治学院大学ブランディングプロジェクト」は、明治学院大学と社会の関係を深めるためのシステムであり、大学の知名度をあげることだけを目的とする、いわゆるPR活動とは一線を画します。
通常「ブランド」とは、一種の商品イメージのことであり、消費財やサービスを提供する企業とそれを需要する消費者の間に生まれる概念です。大学も、基本的には、教育という"サービス"を、学生という"消費者"に提供していますから、各大学には社会的に共有されるブランドイメージが存在します。しかし、「商品一般のブランド」と「大学のブランド」には決定的な違いがあります。
「大学のブランド」の場合、サービスを提供する大学と需要する学生の関係のなかだけでブランドが成立するのではありません。社会というモメントも考慮しなければなりません。なぜなら、大学の使命は、研究と教育を通じた社会貢献にあるからです。つまり、大学のブランディングでは、「その大学はどんな社会貢献ができるのか?」という観点から、他大学との差別化を図ることがポイントになってきます。ほかの大学にない、その大学にしかできない社会貢献。それをいかに世の中に伝えるかは、各大学にとって重要な課題です。そこがきちんと世の中に対してアピールできている大学は、「ブランド力」があると言えるでしょう。
大学のブランディングにとってもっとも重要な契機はアイデンティティ (関係者によって共有され関係者の心を一つに結ぶ役割を果たすもの) です。それがなければ、大学は社会に存在感を示すことはできません。明治学院大学のアイデンティティは、1859年に来日して33年間にわたって日本と日本人のために尽くした、本学の創設者であるヘボン (James Curtis Hepburn) の生涯を貫く信念に求めることができます。それは、新約聖書にある言葉「Do for others what you want them to do for you (人にしてもらいたいと思うことはなんでも、あなた方も人にしなさい) 」そのものでした。
“Do for Others”こそが、明治学院大学の学生、教職員、保証人、卒業生の心をひとつにできるアイデンティティの役割を担うことができるのです。ですから、明治学院大学は“Do for Others”を教育理念として掲げています。
ところで、教育理念も、学生、保証人、そして卒業生という大学関係者自身がそれを自覚しなければ意味がありません。“Do for Others”をまず学内関係者のあいだに浸透させていく仕組みが必要でした。そのために生まれたのが、MGのロゴとイエローのスクールカラーでした。これをデザインしたのは、アートディレクターの佐藤可士和氏です。佐藤氏は、“Do for Others”という教育理念にふさわしいロゴをデザインし、カラーを選びました。
明治学院大学の学生は、白金校舎のパレットゾーンに掲げられている大きな垂れ幕やレストランのトレー、学生証や学生手帳など、学内のさまざまな場面で、MGのロゴとイエローを目にしています。日々それらに触れる中で、“Do for Others”というメッセージに接しています。このようなプロセスをへて、いまやこの教育理念は学内の隅々まで浸透するようになりました。
学内だけでなく、同時に社会に対しても積極的に“Do for Others”というメッセージをロゴとスクールカラーに託して発信しています。明治学院大学がいま、教育の分野でおこなっている社会貢献を、広告やウェブサイト等でアピールしようとしても、現代の情報洪水の中ではなかなか社会に受け入れてもらえません。しかし、このロゴとスクールカラーに"アイコン"の役割を果たしてもらえれば、明治学院大学の情報は社会に容易に受け入れてもらえるようになります。
まるで"アイコン"をクリックするように、明治学院大学 (Do for Others) にコンタクトできる仕組みが明治学院大学ブランディングプロジェクトです。この仕組みによって多くの人びとに明治学院大学の社会貢献を知ってもらうことができるようになります。したがって、明治学院大学の社会的な存在感も高まります。ひとたびこのような水準に到達すると、社会は明治学院大学を意識し、明治学院大学は社会を意識するという循環的な関係が生まれます。ブランディングプロジェクトは、明治学院大学と社会の関係を深めるシステムの構築を目差しています。
ボランティアファンドについて
ヘボンの生涯を貫く信念に由来する教育理念“Do for Others”は、大学関係者が自らの存在を、社会との関係のなかでいつも意識しなければならないことを示唆しています。私たちは、大学関係者の心を一つに結ぶ「明治学院大学ボランティアファンド支援グッズ」を共有しようとしていますが、大学の理念を実現するために、グッズの購入という形を通じて社会に貢献する仕組みを創りました。明治学院大学公認ロゴマークを用いて企画販売される「明治学院大学ボランティアファンド支援グッズ」の本体価格の10%を、明治学院大学ボランティアセンターが管理・運営する「明治学院大学ボランティアファンド」に積み立てられます。
「明治学院大学ボランティアファンド」は、明治学院大学ボランティアセンターが企画する活動への支援に運用されます。

明治学院大学ボランティアファンド支援グッズ
文房具からアパレル、菓子、記念品に至るまで様々なグッズラインナップです。

ボランティアファンド積み立て報告
| 年度 | 期間 | 積立金 |
|---|---|---|
| 2021年度 | 2021年4月 - 2022年3月 | 247,269円 |
| 2020年度 | 2020年4月 - 2021年3月 | 219,048円 |
| 2019年度 | 2019年4月 - 2020年3月 | 443,074円 |
| 2018年度 | 2018年4月 - 2019年3月 | 446,741円 |
| 2017年度 | 2017年4月 - 2018年3月 | 965,615円 |
| 2016年度 | 2016年4月 - 2017年3月 | 784,806円 |
| 2015年度 | 2015年4月 - 2016年3月 | 787,636円 |
| 2014年度 | 2014年4月 - 2015年3月 | 1,052,312円 |
| 2013年度 | 2013年4月 - 2014年3月 | 586,745円 |
| 2012年度 | 2012年4月 - 2013年3月 | 853,195円 |
| 2011年度 | 2011年4月 - 2012年3月 | 722,077円 |
| 2010年度 | 2010年4月 - 2011年3月 | 906,980円 |
| 2009年度 | 2009年4月 - 2010年3月 | 854,633円 |
| 2008年度 | 2008年4月 - 2009年3月 | 889,196円 |
| 2007年度 | 2007年4月 - 2008年3月 | 774,625円 |
| 2006年度 | 2006年4月 - 2007年3月 | 860,373円 |
| 2005年度 | 2005年10月 - 2006年3月 | 335,838円 |
お問い合わせ先
学長室広報課 03-5421-5165
アートディレクター紹介
Kashiwa Sato
アートディレクター/クリエイティブディレクター
佐藤可士和
スマップのアートワーク、明治学院大学のブランディング、NTT DoCoMo「FOMA N702iD / N703iD」のプロダクトデザイン、ユニクロNYグローバル旗艦店のクリエイティブディレクション、国立新美術館のVIとサイン計画等、進化する視点と強力なビジュアル開発力によるトータルなクリエイションは多方面より高い評価を得ている。東京ADCグランプリ、毎日デザイン賞ほか多数受賞。著書に「佐藤可士和の超整理術」 (日本経済新聞出版社) 。
http://kashiwasato.com/


ブランディングプロジェクト1200日の軌跡
2004年10月にスタートしたブランディングプロジェクト。「Do For Others」の教育理念やMGのロゴマークは、その後どのようなプロセスをへて、グッズやファシリティへと多面的に展開されていったのだろう。トークセッションほかのイベントも開催してきた「ブランディングプロジェクト1200日」の軌跡を追う。
2004年
10月12日
アートディレクター・佐藤可士和氏が明治学院大学を訪問。大塩武学長と面会する。学長が大学の歴史と現状、新ロゴマーク構想について説明し意見交換。

白金キャンパス訪問
12月初旬~
佐藤氏のクリエイティブスタジオ「サムライ」にて、ブランディングプロジェクトのコンセプトメイキングなどが行われる。佐藤氏は300ものシンボルマーク案をデザインし、それをひとつにしぼりこんでいった。

様々な検証をへてこのロゴマークに決定した
2005年
1月25日
ロゴ選定委員会で、佐藤氏がMGのロゴマーク、スクールカラー(イエロー)のプレゼンテーションを行い、その案が委員全員の賛成をもって承認される。

ロゴ選定委員会
4月1~5日
入学式。新入生にロゴ入りのビニール袋が配布される。学生証や学生手帳も新しいものに。大学ホームページトップにも新ロゴがお目見えした。

入学式
5月20日
学長、大学企画・広報、生協、業者などによる定例ミーティング(月2回)がスタート。翌21日は佐藤可士和×天野祐吉トークセッション(モデレーター:菅付雅信)が行われる。

トークセッション
6月6日
佐藤氏が新しいユニフォームデザイン案を各学生団体にプレゼンテーション。

各団体にプレゼン
7月4日
定例ミーティング。テーマは、Tシャツ、海外交流用のみやげ品、一般向け大学案内など。Tシャツ等のグッズは「学生が日常使用することができる」「大学のグッズでここまでやるんだという驚きがある」クオリティを目指すことに。Tシャツにプリントするメッセージは、「Do For Others」に決まった。カラーは黄、白、黒の3色。横浜の老舗洋菓子屋「かをり」とのコラボレーション・ギフトを作るアイデアも出た。
7月7日
佐藤氏が横浜キャンパスを訪問。ベンチ、テーブル、ダストボックスなどの備品を含め、空間をトータルにリノベーションするプロジェクトについて打ち合わせ。

横浜キャンパス ベンチ
8月10日
定例ミーティング。シールやネクタイのほか、A6リングノート、B5バインダー、PC壁紙、学生名刺、ビニールバッグ、ピンバッジ、ペン、マグカップ、名刺ケース、腕章、校旗、大学案内についてディスカッション。

ネクタイ
9月9日
定例ミーティング。「Do for Others」の理念を学生により広く浸透させるため、グッズの売上の一部(10%)を、ボランティア活動に寄付する仕組みを作る構想を学長が発表。「明治学院大学ボランティアファンド支援グッズ」として、生協にて販売開始。ファンドはボランティアセンターにより、災害被災者支援、環境保護活動支援に運用される。ボランティアセンターは、阪神大震災の際、多くの本学生が被災地に向かったことがきっかけで誕生した学内組織。
11月18日
定例ミーティング。ボランティアセンターのロゴマークに関するデザインの方針についてディスカッションが行われた。テレビ番組の取材が入る。

ボランティアセンターロゴマーク
12月2日
定例ミーティング。MGS(株式会社明治学院サービス ※大学が必要とする業務を行う大学出資の企業)のロゴ案を検討する。
2006年
3月6日
渋谷駅でのサインボード掲出が始まる。

渋谷駅サインボード
5月30日
本学で開催した佐藤可士和作品展の設営を手伝う、学生サポーターの面接が行われた。サムライにて。

佐藤可士和作品展の面接
6月19日
定例ミーティング。横浜キャンパスC館1階にオープンするMG Caféについて打ち合わせ。基本レイアウトからイスなど備品の種類や色、食器、メニューボードに至るまで、佐藤氏がディレクション。ボランティアファンド支援グッズを陳列する棚も設けることに。
6月25日
佐藤可士和作品展(白金キャンパス)設営。白金キャンパスパレットゾーンにて。明治学院大学、キリン「極生」、ミュージシャンのアートディレクションなど、佐藤氏の仕事が10のゾーンに分けられており、各ゾーン2~4名の本学生が、グループで作業に当たる。学生らは、独力で作品を並べてみた上で、「コンセプトを決めたほうがいい」「ちょっと置く位置を変えただけで印象はガラッと変わる」といった佐藤氏のアドバイスを受けながら完成させていく。

作品展の設営
7月16日
受験生向けオープンキャンパス開催。そのプログラム、パンフレット、アンケート、グッズ(リングノートとボールペン)、当日のチラシなどを新たにデザイン。佐藤可士和氏とコラムニストの天野祐吉氏によるトークセッション「それって、カッコいい? 大学選びってなんだろう」も行われた。

トークセッション
10月11日
クリスマスカードやMGワインのラベル、パーカー、サブレ缶、ポストカードのデザイン案、横浜キャンパスの改良点などについてディスカッション。
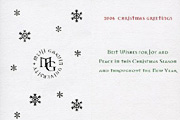
クリスマスカード
2007年
1月26日
定例ミーティング。2007年4月にリニューアルする、Webサイトの方向性について打ち合わせ。YouTubeを活用し動画を見られるようにする。
3月24日
オープンキャンパスに1500人超が来場。佐藤氏デザインによるDMを持参する来場者が目立った。次回は来場者に、MGロゴの入ったミネラルウォーターを配布することに。

オープンキャンパス
4月11日
定例ミーティング。MG NEWS、横浜キャンパスのグラウンド(ヘボンフィールド)、グッズカタログなどについてデザインその他を検討。2006年度のグッズ売上は約860万円だった。

ヘボンフィールド
5月25日
定例ミーティング。スクリーンセーバー、壁紙、ポストカードに使用する写真を新たにフォトグラファーの瀧本幹也氏に依頼することに。

壁紙
7月18日
定例ミーティング。新設される横浜キャンパス10号館学生ラウンジ等について打ち合わせ。
10月11日
クリスマスカードやMGワインのラベル、パーカー、サブレ缶、ポストカードのデザイン案、横浜キャンパスの改良点などについてディスカッション。

東急線シリーズ広告
10月10日
定例ミーティング。本学で開催されたカナダフェスティバル(11月26日―30日まで)のイベントロゴやポスターデザイン等について打ち合わせ
12月5日
定例ミーティング。MGロゴやスクールカラーを使用する際のルール・展開例を「ロゴマニュアル」として作成することに
2008年
1月18日
定例ミーティング。MG WATERのベンダーのデザインや日本の大学では初となるYouTube公式チャンネル等について打ち合わせ。

YouTube公式チャンネル
3月12日
定例ミーティング。法科大学院が入る高輪三丁目校舎のデザイン計画について話し合いが行われる。

 入試情報サイト
入試情報サイト