「人と人との出会い」を社会心理学の視点から ―婚活イベント・マッチングアプリに着目して
私たちの社会は、さまざまな対人関係によって成り立っています。恋愛関係や友人関係など、身近な対人関係における人々の心理や行動のメカニズムと、それらに文化や社会環境がどのような影響を与えるかについて、社会心理学の観点から研究を進めているのが鬼頭教授です。近年は特に、社会問題化している日本人の未婚化・晩婚化にスポットを当て、個人特性や行動に注目した婚活イベントやマッチングアプリに関する実証研究に力を注いでいます。


鬼頭美江
社会学部社会学科 教授
カリフォルニア州立大学チコ校心理学科卒業(Honors)。マニトバ大学大学院心理学研究科社会・性格心理学専攻博士課程修了。Ph.D.(Psychology)。日本学術振興会特別研究員(PD)、明治学院大学社会学部社会学科専任講師、准教授を経て、2025年4月より現職。専門は社会心理学。著書に『つながりの社会心理学-人を取り巻く「空気」を科学する』(弘文堂,2023年)など。
恋愛関係を“研究しにくい”日本の事情
少子化は、現在の日本でとても大きな社会問題となっています。特に婚外子の少ない日本において、その背景の一つとして考えられているのが、未婚化・晩婚化です。もちろん結婚するかどうかは個人の自由であり、社会や他者に強要されるものではありません。ただ一方で、結婚を希望しているのに「適当な相手にめぐりあわない」という理由から独身でいる方が多いことも明らかになっています。なぜ日本ではそうしたことが起きているのか、原因や対策を追究したいと考え、婚活やマッチングアプリに関する研究をスタートさせました。
元々私はカナダの大学院で、良好な対人関係とはどのような関係か、また、良好な関係性を予測する要因とは何かについて研究をしていました。帰国後、研究対象の一つとして恋愛関係を扱う中で、恋人がいる人を対象とする調査の難しさに悩まされるようになりました。北米では独身者の6~7割に恋人がいますが、日本では3割程度にとどまるというのが、その大きな理由です。私の留学中の経験を振り返っても、アメリカやカナダでは友人たちがマッチングサービスで恋人候補と出会ってカジュアルにデートをしていましたが、少なくとも私が帰国した2012年ごろの日本ではそんな話をあまり耳にしませんでした(近年、20~30代を中心に変化しつつありますが)。では、恋人がいない人は「結婚を希望していない」のかというと、必ずしもそうではなく、「結婚を希望してはいるが、出会いの機会がない」「どうしていいか分からない」という人が大勢いることが見えてきました。こうした日本の状況を、個人の心理や行動と、文化や社会環境の影響の双方から検討することが重要だと考えるようになりました。
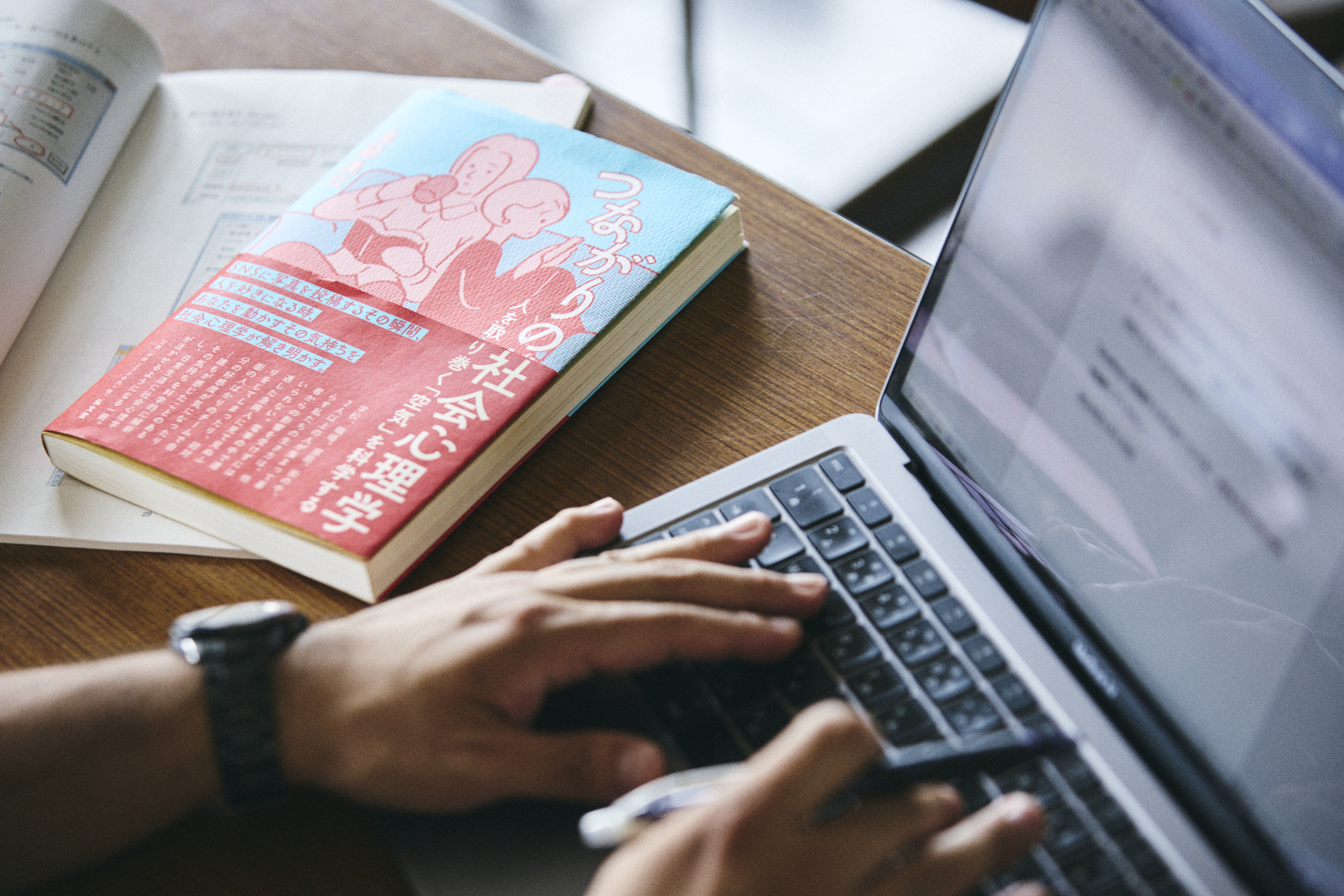
婚活での出会いを左右する個人の特性とは
かつての日本では、お見合い結婚や職場結婚が主流でした。しかし、時代は変わり、近年はさまざまなマッチングサービスを利用して“婚活”する人が増えています。こども家庭庁が2024年に実施した調査では、過去5年間に結婚した既婚者の25%が結婚相手との出会いの場を「マッチングアプリ」と回答したことも話題になりました。企業だけでなく、自治体が婚活イベントを企画するなど、出会いの場は年々多様化しています。現在は、そうした多様な出会いの場での人々の心理や行動について、特にパートナーとの出会いや関係の形成・維持を促す要因に関する研究を進めています。
そのような研究関心のもと、これまでに、1)婚活イベントにおける相手からの評価と外見的魅力や性格特性との関連、2)マッチングアプリの利用経験・利用動機と個人特性との関連、3)結婚支援におけるメタバースの有用性などについて、質問紙調査や実験による量的研究を行ってきました。
このうち、婚活イベントに関する実証研究では、事前に性格特性、恋愛に対する態度、社会的地位、学歴などを測定した独身の男女に3分間対話してもらい、対話後に相手をどの程度魅力的だと思ったか、どの程度交際したいと思ったかを調査しました。その結果、外見の魅力度と学歴が高い女性ほど、男性からより魅力的であると評価されていることが分かりました。一方で、男性からの魅力度評価と性格特性などとの間に関連は見られず、女性からの魅力度評価とはっきりとした関連が見られた男性側の要因も確認されませんでした。日本における婚活イベントに関する実証研究はまだ始まったばかりであり、今後も継続していく必要があると考えています。
また、埼玉県本庄市社会福祉協議会が実施する結婚支援事業への連携協定、マッチングアプリを運営する株式会社エニトグループのアドバイザリーボードへの参画など、現場で活動されている方々との協働や支援にも力を入れています。連携を始めてみると、本庄市社会福祉協議会の担当者の皆さんやエニトグループの方々も、熱い思いを持って真剣に取り組んでいらっしゃることが伝わってきます。そうした皆さんを学術的なアドバイスなどを通じてサポートし、研究で得た知見を現場に還元していきたいと思っています。

参加型授業で社会心理学を“使える”人を育てる
学部の講義科目では現在「社会心理学」「対人関係論」を担当しています。例年200人近くが履修する講義ですが、毎回学生が参加する授業内課題を出しています。授業で扱う概念に関する心理尺度に回答してもらい、その場で集計して、その結果を先行研究と比較したり、授業で解説した理論を日常生活での事例に当てはめてグループで議論してもらったり、単に私の話を聞くだけの時間にならないよう努めています。そうすることで、学生は授業の内容を自分の生活に関連付けて考えることができるようになるからです。社会心理学や対人関係は学生にとっても身近なテーマが多く、仕事や日常生活の中に関連する事象があふれています。授業内で自ら考え、学びを自分のものにすることで、卒業した後も社会心理学をうまく“使える”人になってほしいと願っています。
また、ゼミでの研究は学生の主体性を尊重しています。卒業論文のテーマは、社会心理学や対人関係に関連していて、量的調査ができる内容であれば、基本的にはどんなテーマでも受け入れています。友人関係や恋愛関係といった典型的なテーマはもちろん、最近はSNS上のコミュニケーションや印象形成、マッチングアプリを取り上げる学生も増えています。特に多いのは、学生自身の趣味や“推し”に関するテーマです。学生が興味を持ちやすい研究領域ではあると思うのですが、私のゼミでゼミ論文や卒業論文を書くには、英語の文献を読み込み、多くの文系学生が苦手とする統計的な分析も必要なので、学生の間では「やる気がないと難しいゼミ」ということになっているようです(笑)。ゼミの学生には、社会調査や心理学実験の基礎的なスキルを身に付け、自分が不思議に思ったことを研究して解明していく面白さを感じてもらいたいですね。
学生がフィールドに出てデータを集め、分析する「社会調査実習」の授業では、マッチングアプリなどをテーマに学生と一緒に調査を行いましたが、私自身が面白いと感じるような結果もこれまでにいくつか出ています。たとえば、マッチングアプリに関する日本とアメリカの比較文化研究では、利用者のプロフィール写真の違いが印象的でした。集まった写真はそれほど多くなかったものの、日本人は本人が写っていない写真も少なからずあり、写っていても横顔や後ろ姿など顔が分かりにくい写真が多くありました。一方で、アメリカ人は真正面から撮った証明写真のようなものが多く、学生たちは「こんな写真をアップしたらナルシストだと思われる……」と驚いていました。そうした違いがなぜ生じるのかまで調べたり考察したりできたら面白いですね。
また、ゼミで実施した、自分の魅力を“盛る”ことの影響を調べる実験も印象に残っています。元々魅力度が60点の人が、90点に見えるように盛っていたことが分かった時と、60点のまま見せた時を比較すると、ありのままを見せた方が相手からの印象が良く、盛ると逆に印象が下がるという結果になり、これには私も驚きました。最近の学生は「多少盛るのは許容範囲」と考えているようですが、素のままの自分を見せればいいというメッセージになったかもしれません。

個性に合った出会いの場の創出に期待
日本における少子化や未婚化は、すでに社会学などの領域で広く取り組まれている重要なテーマです。そうした研究は日本社会全体を俯瞰した視点で行われていますが、それだけでなく、個人の行動や心理にも焦点を当てた社会心理学的視点からの研究も重要だと私は考えています。
たとえば、未婚化・晩婚化の原因としてよく「非正規雇用の男性の増加」とそれに伴う「収入の不安定さ」、「女性における有職率の増加」という点が挙げられますが、そうした社会的・経済的な要因を解決すれば未婚化・晩婚化が解消されるのかといえば、おそらくそうではないでしょう。雇用形態や収入の安定はもちろん大きな要因ではありますが、それだけではなく、独身者の個人特性や、初対面状況でどのように振る舞ったらよいかなどの行動にも注目して検討することで、「結婚を希望しているものの、どうしたらいいか分からない」と感じている人に対してきっかけやヒントを提示することができ、未婚化・晩婚化対策の新たな糸口になるかもしれないと考えています。
また、婚活イベントやマッチングアプリなどの台頭によって、結婚につながる出会いの場は多様化していますが、多様化したからこそ、自分に合うサービスが分からない、選びきれないという新たな課題も生まれています。手当たり次第にサービスを利用して、うまくいかない経験が続くと、「婚活疲れ」「アプリ疲れ」でやる気を失ってしまう人もいるでしょう。しかし、それぞれの個人特性に応じた出会いの場を科学的根拠に基づいて提案することができれば、出会いの場とのミスマッチによる婚活疲れや自信喪失を防ぎ、継続的な婚活を促進する一助になると考えられます。
未婚化・晩婚化の抑止に取り組むことは、人口減少や孤独・孤立の予防など、より広範な社会問題の解決にも寄与する可能性があり、婚活による出会いの研究は、応用的な意義を持つ魅力ある領域だと感じています。今後の研究を通して、結婚を希望する人がその人の特性に合った出会いの場で、自信を持って関係発展につながるパートナーを見つける支援ができるよう、力を尽くしていきたいと考えています。


 入試情報サイト
入試情報サイト