新たな問いを立て、価値を創造する。明学で育んだ「哲学」を胸に。
株式会社 NODEにてマネージャー/クリエイティブディレクターとして、新しい体験をデザインすることで、今より良い世の中をつくることができると信じていると語る井上晃徳さん。広告業界の第一線でキャリアを積み重ねてきた中で、常に自身の「問い」と向き合い、価値を追求してきました。その根底には、明治学院大学の教育理念“Do for Others(他者への貢献)”を通して培った他者を見つめる視点があります。キャリアの転機や、母校のプロモーション動画制作に込めた想い、そして「明学らしさ」についてうかがいました。


井上 晃徳
株式会社NODE マネージャー/クリエイティブディレクター
2008年 心理学部 心理学科卒
明治学院大学卒業後、株式会社大広九州、株式会社電通、株式会社リクルートコミュニケーションズ(現・株式会社リクルート)を経て、2025年より株式会社 NODEにて現職。2024年12月に公開した明治学院大学の高校生向けプロモーション動画『Hello My Philosophy』の企画制作に携わる。
広告業界への扉を開けた、衝撃的な新聞広告
大学卒業後、広告業界を志したのは、福岡県の企業「お仏壇のはせがわ」の新聞広告に心を掴まれたことがきっかけでした。その圧倒的な表現に衝撃を受け、誰がどうやって作ったのかを調べていくうちに、広告代理店という業種、クリエイティブと名のつく職種を知りました。ネクタイもせず、スーツも着ていない人たちが、私の想像していた社会人の枠を軽やかに超え、自分の創造性を拠り所に楽しそうに仕事をしている姿に、自由と憧れを感じたんです。会社に所属しながらも独自の領域を築き、主導権を自分で握っているように見え、「ここしかない」と思い、広告業界を目指しました。
大学卒業時から、「人の心が揺れるようなコピーを書きたい」という想いは根底にありましたが、キャリアを重ねる中で、それは「目的」から「手段」へと変わっていきました。今は、「クライアントさんが心を込めて創った商品やサービスの価値を伝える」ための手段の一つとしてコピーを書くという考えです。どんな商品やサービスにも必ず価値があると信じ、その原石を見つけたり、磨いたり、繋ぎ合わせたりする仕事にやりがいを感じています。


問を立て、仮説を持ち、価値を届けるクリエイティブワーク
広告コピーやクリエイティブの世界はセンスだと思われがちですが、実は多くの地道なプロセスが存在します。重要なのは、深い思考量を経て得られる質の高い「問い」の設定力です。「何を解くべきか?」という問い次第で答えが変わるため、良い問いを設定できるように心がけています。思考量があれば、自然と答えへの道筋やバリエーションも見えてきます。生成AIの時代でも、制作者自身が圧倒的な当事者意識を持って深く考え、悩まないと良いものは創れないと思っています。
私は複数回の転職をしていますが、ネガティブな理由で辞めたことは一度もありません。自分でコントロールしているジョブローテーションのようなものなんです。自分の中に、今、向き合うべき問いを設定して、その問いを解きにいくためにどうすれば良いか。これを繰り返しています。2025年から所属している株式会社 NODEでは、「体験の変革」をデザインしていくことを目指しています。誰かが一人で頑張るボランティアでもなく、お金儲けだけでもない、ビジネスとして成立させて持続していくための新しい仕組みや体験をデザインする仕事です。その結果として、「うれしい」とか「勇気をもらった」、「こうなったら良いと思ってた」といったお客様からの声を聞くことを目指しています。
苦悩を経て気づいた、自己表現と価値創出の違い
これまでのキャリアの中で苦労したのは、20代後半から30代前半にかけて、社会で働くことに慣れてきた頃です。根拠のない自信から、「なんで周りは理解してくれないんだ」と思っていました。スキルやセンスは知識や経験、学びと実践の繰り返しで構築されるものなのに、ろくに学びもせず勢いだけで突っ走っていたため、企画が独りよがりになってしまっていたんです。
誤解を恐れずに言うと、芸術家とクリエイターの大きな違いはここにあると気づきました。自分がやりたいことは「自己表現ではなく、携わる人や企業の価値創出」なのだと。それに気づいてからは、クライアントさんや一緒に働く仲間とも、健全で前向きな議論ができるようになりました。時にぶつかることもありますが、価値創出という共通の目的があるので、最終的には必ず良いアウトプットに行きつきます。良いアウトプットには、必ずと言っていいほど良いプロセスがあります。クライアントさんや仲間から「また一緒に仕事しよう」と言われるたびに、今のスタンスは間違っていないと感じています。
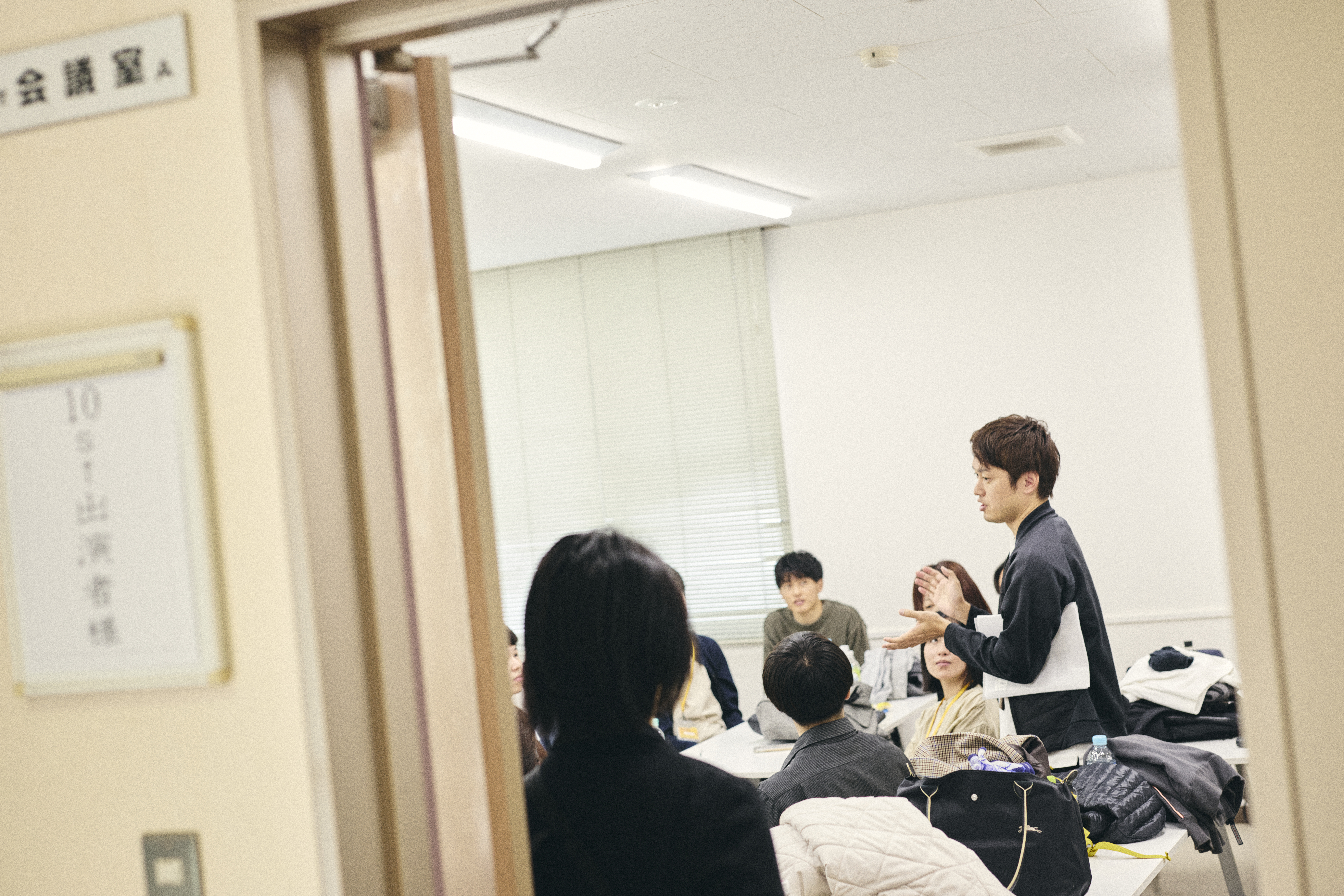
『Hello My Philosophy』に込めた想い
株式会社リクルート在職中、クリエイティブディレクターとして母校である明治学院大学の高校生向けプロモーション動画『Hello My Philosophy』の企画制作に携わりました。母校の仕事をできる機会なんて一生に一度かもしれない。おおげさではなく全身全霊をかけようと誓いました。企画段階で、偶然にも在学時のゼミメンバーやお世話になった井上孝代先生(現・名誉教授)と10年以上ぶりに集まる機会があり、先生から教えていただいた「LOVE&Network(互いの背景を知り、それを背負い、理解し合うことを諦めず、繋がり続けること)」という概念が今の自分の礎になっているとあらためて感じ、企画を前に進める大きなきっかけとなりました。
卒業生としての主観と、外部から見た客観的な視点を交えながら、正直な想いを企画書にまとめ、「今、この時代に意味のある、明学にとっても意味のある問いを立て、それを映像で表現しませんか」とプレゼンテーションしました。明学には教育理念である“Do for Others(他者への貢献)”があり、一人ひとりの物語や考え、夢、目標、価値観を尊重する独自の文化があります。時代錯誤とも思える長年変わらない偏差値至上主義の日本の大学システムに対し、画一的な評価指標で計らない明学に「未来への希望」を見出し、この企画に行きついたんです。
『Hello My Philosophy』は、“Do for Others”と対の関係にあります。明学の学びを通じて得られるものは何かという問いに対し、学生一人ひとりが揺れながらも確立していく考え(哲学)こそが未来の自分の拠り所となり、それは自分自身の光、ひいては社会を照らす光にもなる、と考えました。この価値は、自由で利他の精神の空気が流れる明学だからこそ得られるものだと思っています。Philosophyという抽象概念を、日々の学びの中で明学生が体得し、自分の言葉として紡ぎ出す瞬間を丁寧に切り取ることで、見た人自身も問い直す体験を提供することを目指しました。このことを表現するために、17学科全ての学生に出演してもらうことは必須でした。全員にインタビューをさせてもらい、学科の特性と学生の個性を繋ぎ、それを映像で表現しています。学科の先生と話をさせていただく機会もあり、ここまで丁寧に学生を見て緻密にカリキュラムに落とし込んでいることに、あらためて驚かされました。今回の映像ではその部分の表現はしていませんが、高校生にはそこも含めて明学を見てほしいと思っています。
弱者の視点を忘れないこと、それが明学らしさ
明学に進学したのは、人の心の探求ができる学問に興味があったからです。オープンキャンパスでキャンパスの佇まいや人柄に触れ、「心の広さ」を感じて素敵だと思いました。入試で親友となる友人と出会い、運命も感じましたね。大学時代は、決して優秀ではなかったですが、真面目に課題に取り組み、演習や議論できる授業が好きでした。体系立てて学び、構造化して前向きに議論を進める時間が楽しかったです。個人的にとても苦労した統計の授業では、毎回友人に助けてもらいました。あらためて、助け合うことの大切さを学びました。

明学の教育目標は全て大切ですが、特に「他者を理解する力を身につける」が社会で生きる上で必要だと感じています。学んだスキルや知識を「妄想」で終わらせず、それを実行に移す「構想」力が社会では求められます。他者理解とは、相手を思いやりながら自分の考えを主張できる力であり、ビジネスシーンでも不可欠な力です。
私は、明学らしさは「性弱説」にあると思っています。「人は弱い」という前提に立って物事を考えるということです。正しい解決策だけでなく、それが弱者にとって使いやすいかという視点で設計する精神です。世の中はリテラシーや効率性が前提の言動やサービスに溢れていますが、「そうではない側=弱者」の視点を忘れない精神があることこそ、明学らしさだと感じています。
在学生の皆さんには、好き嫌いせず、少しでも興味を持ったら短期的な損得だけで考えず、アクションを起こしてみてほしいです。体を通した経験からしか得られないものがあり、たとえ失敗しても、明学はそれを許容してくれる場所です。いつか明学で、広告クリエイティブについての講義ができたら最高ですね。


 入試情報サイト
入試情報サイト